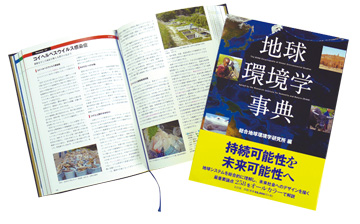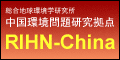![]()
![]()
地球研では、研究成果を広く社会に還元するため、一般の方や研究者を対象にしたシンポジウム、フォーラム、セミナーなどのイベントを開催しています。また、総合地球環境学に関するさまざまな刊行物を積極的に出版しています。
地球研国際シンポジウム

第7回地球研国際シンポジウム
地球研の研究成果を世界に発信することを目的として、国内外の研究者コミュニティを対象に毎年開催しています。その年度に終了する研究プロジェクトの研究発表を中心に、最新の研究活動や海外諸国の地球環境研究の現状を紹介しています。
| 回数 | タイトル | 開催日 | 場所 | |
| 第7回 | 複雑化・単純化するアジア 生態系、ひとの健康と暮らし |
2012年10月24日-26日 | 総合地球環境学研究所 講演室 |
詳細 |
地球研フォーラム

第11 回地球研フォーラム
地球研の理念や研究成果に基づいて、地球環境問題について幅広い提起やディスカッションを行なうことを目的に、毎年開催しています。2004年度からは広く一般の方の理解に供するために、その成果を「地球研叢書」として刊行しています。(地球研叢書について)。
| 回数 | タイトル | 開催日 〈場所:国立京都国際会館〉 |
|
| 第11回 | “つながり”を創る | 2012年7月8日 | 詳細 |
地球研市民セミナー
地球研の研究成果や地球環境問題の動向をわかりやすく一般の方に紹介することを目的に、地球研または京都市内の会場において定期的に開催しています。会場からは熱心な質問が毎回よせられています。2010年度から、夏休み期間中に小学生を対象とした地球研キッズセミナーを始めました。専門用語や難しい概念を使用せず、環境の大切さを伝えるよう努めています。外国の生活や調査のようすを研究員から直接聞けるということで、参加者から好評をいただいています。

第48回地球研市民セミナー
| 回数 | テーマ | 開催日 | |
| 第46回 | 新しいインダス文明像を求めて | 2012年5月11日 | 詳細 |
| 第47回 | 東南アジアの環境破壊と食卓のゆくえ | 2012年6月22日 | 詳細 |
| 第48回 | 遠い世界に思いをはせる —アフリカでの開発支援をめぐって | 2013年1月18日 | 詳細 |
| 第49回 | 参加体験型セミナー「自分という自然を生きる」 | 2013年2月15日 | 詳細 |
地球研キッズセミナー

第3回地球研キッズセミナー
| 回数 | テーマ | 開催日 | |
| 第3回 | 「アルベド」って何だろう? | 2012年 8月3日 | 詳細 |
地球研オープンハウス

2012年度地球研オープンハウス 実験室へ行こう!ツアー
地球研では2011年度から、広く地域の方々との交流を深めるために、地球研の施設や研究内容を紹介するオープンハウスを開催しています。2012年度は、キッズセミナーやオープンハウスセミナー、実験室見学ツアー、スタンプラリーやプロジェクト訪問などを実施し、地球研内を自由に歩き回りながら楽しく身近に感じていただけるよう工夫しました。
| 開催年度 | 開催日 | ||
| 2012年度 | 地球研オープンハウス | 2012年 8月3日 | 詳細 |
地球研地域連携セミナー

第11 回地球研地域連携セミナー
国内の大学や研究機関と協働で行なうセミナーです。地域には地域固有の地球環境問題があります。一方で、世界のさまざまな地域でも同様の地球環境問題がみられます。世界と日本で共通する課題について、地元の大学・研究機関・行政とともに、問題の根底を探り、解決のための方法を考えていきます。
| 回数 | テーマ(開催日・場所) | |
| 第11回 | 東アジアの「環境」安全保障:風上・風下を超えて (2012年6月10日 福岡県福岡市) |
詳細 |
| 第12回 | 分かちあう豊かさ:地域のなかのコモンズ (2012年10月13日 山梨県富士吉田市) |
詳細 |
その他
地球研では、その他に次のようなイベントを行政組織、経済団体、学術・研究機関等と連携して開催し、「総合地球環境学」の構築へ向けて幅広く議論を行っています。
■ 地球研東京セミナー

第4回地球研東京セミナー
地球研の成果と今後のさらなる進展について、国内の研究者コミュニティや一般の方に理解と協力を呼びかけていくため、東京でのセミナーを開催しています。日本を代表する研究者や現場の問題を扱う行政関係者などを招いて、最新の成果と課題を討論します。2012年度は、2013年6月に「国際コモンズ学会第14回世界大会(北富士大会)」が開催されるのに合わせて、「コモンズ」をテーマとし開催しました。
| 回数 | テーマ | 場所 | 開催日 | |
| 第4回(人間文化研究機構第20 回公開講演会・シンポジウム) | コモンズ:豊かさのために分かちあう | 有楽町朝日ホール | 2013年1月25日 | 詳細 |
■ 日文研・地球研合同シンポジウム

第5回日文研・地球研合同シンポジウム
人間文化研究機構における新しい人間文化研究の可能性として、日本文化の研究が地球環境問題にいかなる貢献をすることができるかについて提案することを目的としています。
日本文化と地球環境問題、大きく異なる2つの分野の研究を行なう国際日本文化研究センター(日文研)と地球研が中心となり、地球環境問題の本質について積極的に対話しています。
| 回数 | テーマ | 開催日 | 開催場所 |
| 第5回 | 文化・環境は誰のもの? | 2012年9月14日 | 日文研講堂 |
■ 京都環境文化学術フォーラム・国際シンポジウム
地球温暖化をはじめとする地球環境問題を解決するため、京都府、京都市、京都大学、京都府立大学などとともに、環境・経済・文化などの分野にわたる国際的な学術会議を2009年度から開催しています。生活の質を高めながら自然との共生や持続可能な社会を形成する新たな価値観や経済・社会のしくみを、京都から世界に向けて発信・提案することを目的としています。本国際シンポジウムは、「京都地球環境の日(2月16日)」の記念行事と位置づけ、「KYOTO地球環境の殿堂」表彰式と同時に毎年2月中旬に国立京都国際会館で開催しています。

第4 回京都環境文化学術フォーラム スペシャルセッ ション「エネルギーと地球環境の未来-グローバル コモンズを目指して-」
■ KYOTO 地球環境の殿堂
「京都議定書」誕生の地である京都の名のもとに、世界で地球環境の保全に多大な貢献をした実務家、研究者などの顕彰を行ないます。その功績を永く後世に引き継ぎ、京都から世界に向けて広く発信することにより、地球環境問題の解決に向けたあらゆる国、地域、人々の意志の共有と取り組みの推進に資することを目的としています。本顕彰は、「KYOTO地球環境の殿堂」運営協議会(京都府・京都市・京都商工会議所・環境省・国立京都国際会館・地球研)が中心となり、環境分野の専門家、学識者、活動家などで構成する選考委員会で選考されます。
| 殿堂入り者 | 職位 | 業績 |
| 第4回 ヴァンダナ・ シヴァ氏 |
環境哲学者・物理学者 | 伝統的スタイルに根ざした価値観や社会構成の重要性など、環境と共生する思想の普及に貢献した |
| エイモリー・ B・ロビンス氏 |
ロッキーマウンテン研究所理事長 | 術研究の成果をもとにした先進的な戦略「ソフトエネルギー・パス」を提唱した |

写真左:第4回KYOTO地球環境の殿堂 表彰式にてあいさつを述
べるヴァンダナ・シヴァ氏
写真右:エイモリー・B・ロビンス氏
■ 地球研セミナー
地球環境問題に関する最新の話題と研究動向を共有し、広い視座から地球環境学をとらえようとするセミナーです。講師は、主として地球研に滞在中の招へい外国人研究員ですが、国内外を問わず、ほかの研究機関の研究者に依頼することもあります。公開セミナーであり、所員だけではなく所外からも多数参加しています。
■ 談話会セミナー
原則月2回、昼休憩を利用して行なうランチセミナーです。地球研で求められているのは、多様な研究分野間の相互理解と、共通テーマである地球環境問題に関する不断の議論です。談話会セミナーでは、地球研の若手研究者が中心となって、各自の研究背景をふまえつつ、多くの所員に共通の話題を提供し、研究者相互の理解と交流を深めています。
■ 刊行物
地球研の研究や成果を学問的に分かりやすく紹介する出版物です。
| タイトル(著者・編者)、出版社、出版年月日 | |
| 生物多様性 子どもたちにどう伝えるか? (阿部健一 編)昭和堂 2012年10月 |
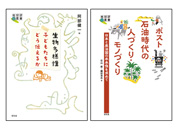 |
| ポスト石油時代の人づくり・モノづくり—日本と産油国の未来像を求めて (石山俊、縄田浩志 編)昭和堂 2013月3月 |
地球研の研究成果を国際社会に向け広く発信する、英文での出版物です。
| タイトル(著者・編者)、出版社、出版年月日 | |
| The Dilemma of Boundariess (谷口真人、白岩孝行 編) Springer 2012年5月 |
 |
地球研ニュース(Humanity & Nature Newsletter)
地球研として何を考えているのか、またどのような所員がいて、いかなる研究活動をしているかなどの最新情報を、研究者コミュニティに向けて発信するもので、隔月で刊行しています。特に、地球研にかかわっている国内外の研究者を対象に、コミュニケーションの場のひとつとして機能することをめざしています。
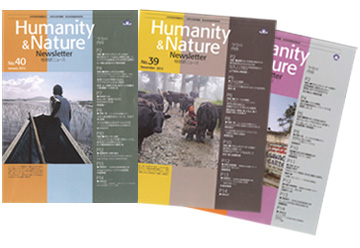
地球研では上記のほかにも多様な刊行物があります。たとえば、さまざまな分野にまたがる研究プロジェクトの成果を事典という形でまとめた『地球環境学事典』を刊行しています。学術的な専門用語を使用せず、高校生にもわかるよう平易に記述するなど、工夫を凝らしています。
また、研究プロジェクトで取り入れている多様な地球環境学の研究手法を、大学生や自治体、研究者にわかりやすく紹介する『地球環境学マニュアル(仮)』や、最新の研究成果を研究者に向けて発信するための新しい出版の枠組みとして「地球研和文学術叢書(仮)」の準備を進めています。