
PR責任者 :Janet Dwyer / Professor of Rural Policy, University of Gloucestershire, UK
プロジェクト概要
先進国では、商品生産と経済的収益の追求のための土地利用の目標と推進力が断片化し、人間と自然の間の長年にわたる相互依存関係が崩壊し、弱体化して、重大な環境破壊をもたらしています。「里山」は、そのような被害を修復し、生物多様性を維持し、気候危機に適切に対処するために、農村地域における土地管理と、人と自然の相互依存関係に関する長年の文化と知識を認識し、それらを生かすことの重要性に光をあてています。この研究は、現在および将来にわたって、文化的ランドスケープに関する土地利用ガバナンス、所有権、管理を強化するための選択肢を特定し、理解し、促進することを目的とします。
詳しくはこちらをご覧ください。(地球研のHPへジャンプします。)
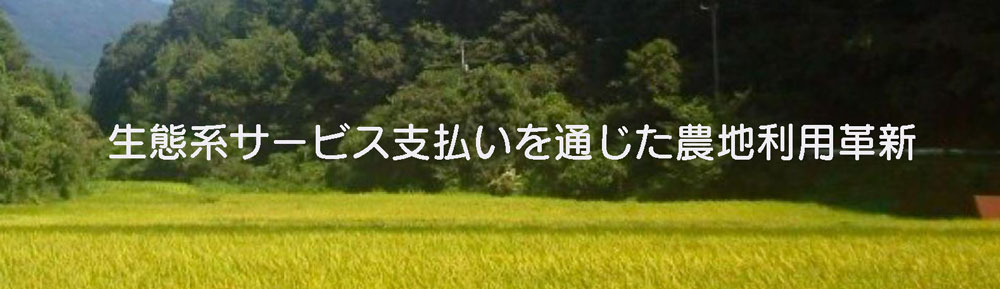
FS責任者 :神井 弘之 / 日本大学大学院総合社会情報研究科 教授
プロジェクト概要
農地の持続可能でない利用が地球環境問題の要因とされる一方で、農業生産活動などの農地への働きかけ次第では、多様な生態系サービスの提供により問題解決に貢献することも可能です。この研究では、問題解決につながる農地利用の革新を促す仕組みとして、多様な主体の参画による『生態系サービス支払い』に着目し、その普及のため、社会実験をデザインし、実践を提案します。
詳しくはこちらをご覧ください。(地球研のHPへジャンプします。)
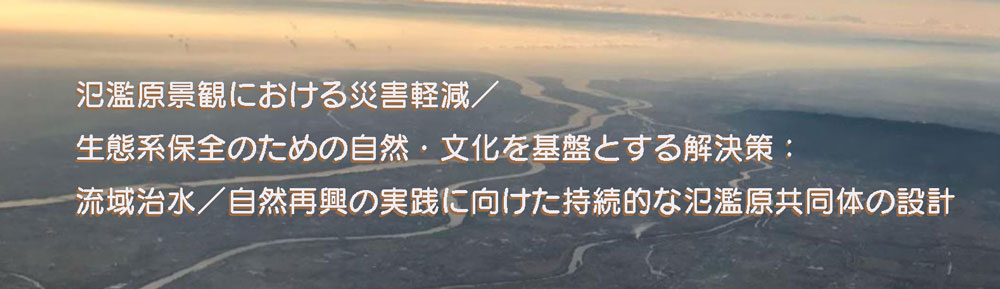
FS責任者 :田代 喬 / 東海国立大学機構名古屋⼤学減災連携研究センター 特任教授
プロジェクト概要
多くの都市が立地する氾濫原は、洪水、高潮や津波による災害に見舞われています。近年、河川・海岸や土地の改良が進み、利便性と安全性が増す中、多様な生物の生息場所やそれらが連なる生態系ネットワークは変質していきました。私たちは、氾濫原に培われてきた自然・社会共同体に注目し、流域治水/自然再興を実践する水・土地利用の変革を通じて、新たな「氾濫原共同体」を設計します。
詳しくはこちらをご覧ください。(地球研のHPへジャンプします。)
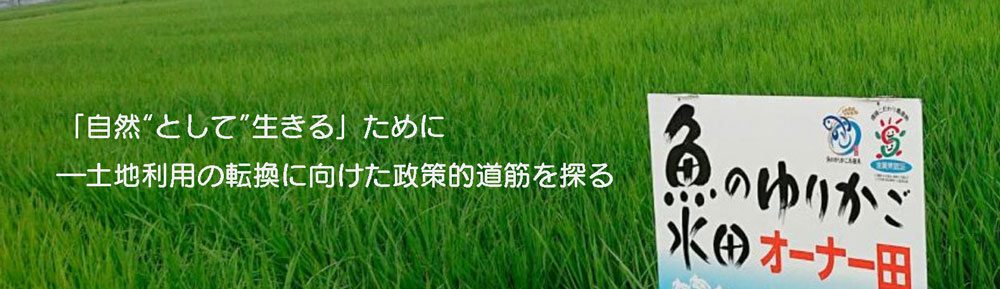
FS責任者 :田村 典江 / 事業構想大学院大学 専任講師
プロジェクト概要
人間中心的な自然利用は生物多様性の危機を招いています。この研究はIPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)の提唱する「自然として生きる」というものの見方について、その日本社会での実践可能性を、土地利用制度の観点から探ります。具体的には、オルタナティブな農林業の検証、多様な自然利用の可視化のためのデジタルツール開発、ヨーロッパの政策を調査して日本の社会変革に生かす取り組みを行います。
詳しくはこちらをご覧ください。(地球研のHPへジャンプします。)
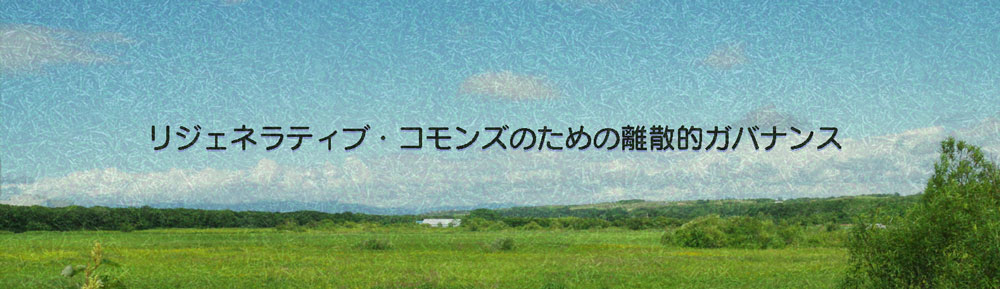
FS責任者 :中島 弘貴 / 東京大学大学院工学系研究科 特任講師
プロジェクト概要
地球環境問題が解決しないのは、身近な暮らしを良くする活動と結びついていないからだと考えます。近年、場づくりを通じて地域と地球の問題解決を同時に目指す活動が見られます。その中では、地続きではない複数の地域の人々が集まったり、離れたりして、柔軟に連携しています。この研究では、こうした新たな動きを継続的かつ実効的な仕組みにするために、実践と研究を一体的に行います。
詳しくはこちらをご覧ください。(地球研のHPへジャンプします。)

FS責任者 :長野 宇規 / 神戸大学大学院農学研究科 准教授
プロジェクト概要
脱化石燃料時代を担うとされているバイオエコノミー(バイオマスの高度利用が生む経済)は国土利用と産業配置を大きく変えることになります。この研究は生態系サービスとのバランスを保ちつつ、地域内の資源循環を高めるバイオエコノミーを地域自治のレベルで計画し、農林水産業、二次産業、自治体、市民の間の合意形成を容易にするツール群を開発してきます。
詳しくはこちらをご覧ください。(地球研のHPへジャンプします。)
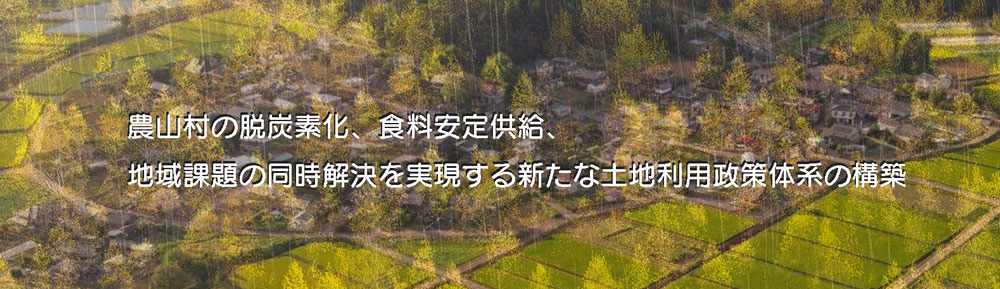
FS責任者 :野津 喬 / 早稲田大学大学院 環境・エネルギー研究科 教授
プロジェクト概要
農山村は脱炭素化の実現に貢献するための場として大きな期待を集めています。しかし、例えば農地に太陽光発電を導入すれば、エネルギー生産と食料生産とのコンフリクトが生じます。
この研究は農山村における土地利用の問題に着目し、従来の二項対立の議論を超えて、脱炭素化、食料安定供給、地域課題の解決を同時実現する新たな土地利用政策体系の構築を目指します。
詳しくはこちらをご覧ください。(地球研のHPへジャンプします。)