ニューズレター(Humanity & Nature Newsletter)
地球研とは何か、どのような活動を行なっているのかなどの最新情報を、研究者コミュニティーに向けて発信するもので、隔月で刊行しています。No.16から内容体裁をリニューアルし、それに合わせて編集室を充実させました。特に地球研に関わっている研究者を対象に、コミュニケーションの場の1つとして機能することを目指しています。
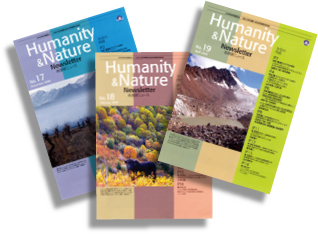
| No.48 | 特集1:成果発信の方法を考える<1> 多様なステークホルダーとともに「あるべき姿」を語る場をつくる シンポジウムの検証 (出席)川端善一郎+半藤逸樹+飯塚理恵 (進行)橋本(渡部)慧子 パネリストインタビュー (話し手)福井晴敏×龜石太夏匡 (聞き手)半藤逸樹 特集2:成果発信の方法を考える<2> 展示をとおしてプロジェクトの成果を統合し公開する (話し手)石山俊+三村豊+小木曽彩菜 (聞き手)寺田匡宏 |
| No.47 | 特集1:広報と成果発信のあり方を語る 地球環境学の魅力を発信し、地球研「コミュニティ」の拡大を狙う 阿部健一+田中樹+寺田匡宏+熊澤輝一 特集1:広報と成果発信のあり方を綴る ストーリーとストレージ デザインの世界に学ぶ「刷新」の手法 林 憲吾 「データ」発信の功罪 影響力を活かしたプラットフォームづくりを見すえる 内山愉太 当事者であることを確認しあう場づくり 菊地直樹 言葉だ、言葉、言葉 鞍田 崇 |
| No.46 | 特集1:研究者と社会の共創による同位体環境学の構築に向けて 第3回同位体環境学シンポジウムを終えて 中野孝教 松本拓也+平田岳史+申基澈 特集2:2013年度地球研研究プロジェクト発表会を終えて 参加者の総括とコメント 窪田順平 田中雅一+森壮一 |
| No.45 | 特集1:所長と語る 地球研アーカイブスはいかにあるべきか 安成哲三×遠藤愛子×安富奈津子 特集2:プロジェクトリーダーに迫る! 水とエネルギーと食料の連環を測り、政策につなげる 谷口真人+遠藤愛子 菊池直樹+中川千草 |
| No.44 | 特集1:フォーラムの検証 第12回地球研フォーラム「“共に創る”地球環境研究」SNS導入で地球環境研究を変革する 半藤逸樹+橋本(渡部)慧子+渡辺一生+辻 はな子+竹山哲治+三宮友志 特集1:開催報告 第12回地球研フォーラム特別企画「地球環境研究を“共に創る”ワークショップ」多様なステークホルダーとともに実効的な地球環境研究をめざす 辻 はな子 特集2:中国環境問題研究拠点 座談会 日本から見る中国、中国から見る日本の姿 窪田順平+北川秀樹+達 良俊+谷 人旭+張 文明+朱 珉 |
| No.43 | 特集1:日文研×地球研 座談会 人文学がみる文化・社会・環境—たとえば「おっさんはなぜきれいな女の子が好きなのか」について 井上章一+稲賀繁美+阿部健一+鞍田 崇 特集2:座談会 < ことば >から考える地球環境学【フィールドワーク編】 藤原潤子+石山 俊+市川光太郎+濱崎宏則+寺田匡宏 |
| No.42 | 特集1:新所長へのインタビュー 地球研が日本の地球環境学の発信地であり続けるために 話し手 安成哲三 ・ 聞き手 半藤逸樹+鞍田 崇 特集2:シンポジウムの報告 第2回同位体環境学シンポジウム地球研がめざす同位体環境学の創出に向けた次のステップへ 中野孝教・日下宗一郎 |
| No.41 | 特集1:所長退任にあたって 残心 立本成文 特集2:機構シンポジウムの報告 コモンズ—豊かさのために分かちあう —寺田匡宏 |
| No.40 | 特集1:プロジェクトリーダーに迫る! 統合的なテーマ設定と理解を通して、シベリアの温暖化とその影響を紐解く 話し手 檜山哲哉 ・ 聞き手 岡本侑樹 特集2:国際シンポジウムの検証 第7回地球研国際シンポジウム「複雑化・単純化するアジア —生態系、ひとの健康と暮らし」 複雑でもあり単純でもあるアジアから学ぶ未来可能性 西本 太+髙野(竹中)宏平+小坂康之+熊澤輝一+中村 亮 |
| No.39 | 特集1:国際コモンズ学会に向けて(2)研究成果はだれのものか 電子化、ネット化時代の学術情報発信から・・・コモンズについて考える 山下幸侍×阿部健一 イベントの報告:日文研・地球研合同シンポジウム 現代において可能な分かち合いの方途を探る 鞍田 崇 特集2:フォーラムの検証 第11回地球研フォーラム「“つながり”を創る」 専門の枠を超えた・・・協働がもたらす豊かな可能性 縄田浩志+鞍田 崇+石山 俊+加藤久明+辻田祐子 |
| No.38 | 特集1:プロジェクトリーダーに迫る! 貨幣価値に換算されない開発のあり方を追求する
石川智士×増田忠義 特集2:イベントの報告 第2回地球研オープンハウスを開催しました 特集3:国際コモンズ学会に向けて 新たなコモンズを日本から世界へ マーガレット・マッキーン+秋道智彌+阿部健一 |
| No.37 | 特集1:国際会議の検証 Planet Under Pressure 国際的な研究の枠組みを踏まえ、活用する 特集2:プロジェクトリーダーに迫る! 地域の知を理解すれば、科学はもっと地域に寄与できる 佐藤 哲×熊澤輝一 |
| No.36 | 特集1:所長と所員による鼎談 地球研のあるべき研究活動のフレームワークとは 立本成文+酒井章子+林 憲吾 特集2:国際動向の検証 第5回ベルモント・フォーラム 地球環境研究の新しいステージの構築をめざして 谷口真人+村松 伸+鞍田 崇+髙野(竹中)宏平 |
| No.35 | 特集1:国際シンポジウムの検証 崩壊の真相を探り、未来社会への地平を開く 阿部健一+石本雄大+安部 彰+遠藤 仁+渡邊三津子 特集2:プロジェクトリーダーに迫る! 地域レベルの水管理に資する統合知の構築を 渡邉紹裕×伊藤千尋 特集3:プロジェクトリーダーに迫る! 中国の環境問題を地球の問題として考える 窪田順平×槙林啓介 |
| No.34 | 特集1:国際会議の検証 持続可能な社会のための科学と技術に関する国際会議2011 世界の研究動向のなかで、地球研の針路を確かめる 谷口真人+阿部健一+安富奈津子+熊澤輝一+髙野宏平 特集2:シンポジウムの報告 山野河海イニシアティブ 国際シンポジウム「東アジアにおける生態学的持続性とその知恵」 アジアの知見を地球の未来のために 安渓遊地 特集3:シンポジウムの報告 第1回同位体環境学シンポジウム 同位体環境研究の可能性を活かすネットワークを形成する 中野孝教+竹内 望 |
| No.33 | 特集1:震災についての座談会 当事者として真摯に考え、局外者として冷静に発信する 佐藤洋一郎+門司和彦+窪田順平+安部 彰+鞍田 崇 特集2:フォーラムの検証 第10回地球研フォーラム「足もとの水を見つめなおす」 水と人との関係が環境問題の本質を照らしだす 湯本貴和+内山純蔵+檜山哲哉 特集3:イベントの報告 地球研オープンハウスを開催しました |
| No.32 | 特集1:出版物による成果統合のあるべき姿 地球研らしい情報発信と社会還元 秋道智彌×湯本貴和×阿部健一×窪田順平×鞍田 崇 特集2:プロジェクトリーダーに迫る! 環境変化だけでは語れないインダス文明の崩壊 長田俊樹+酒井 徹×小林菜花子+湯本貴和 特集3:プロジェクトリーダーに迫る! 人間の営みと自然とのかかわり――1万年前から変わったこと、変わらぬこと 内山純蔵+林 憲吾 |
| No.31 | 記念特集1:日文研×地球研 所長対談 めざすのはヘテラーキーなコミュニタス――所員の声が、これからの地球研をつくりだす 猪木武徳×立本成文 記念特集2:シンポジウムの検証 地球研創立10周年記念シンポジウム「地球環境研究の統合と挑戦――国際共同研究と未来設計イニシアティブ」 研究所としての国際戦略 谷口真人×久米 崇×鞍田 崇×半藤逸樹×アイスン・ウヤル |
| No.30 | 特集1:プロジェクトリーダーに迫る! 食リスクの管理――フィリピンでの知見をアジアに生かす 嘉田良平+梅津千恵子×久米 崇 特集2:プロジェクトリーダーに迫る! 都市を通じて人類の未来可能性を考える 村松 伸×林 憲吾+ 源 利文 特集3:研究プロジェクト発表会を終えて 参加者のレポートと総括 湯本貴和 大西健夫+ 神松幸弘+ 早坂忠裕+ 槙林啓介 |
| No.29 | 特集1:地球研第二期にむけて 水資源管理のための統合知を 渡邉紹裕×谷口真人×中野孝教×窪田順平×檜山哲哉 特集2:プロジェクトリーダーに迫る! 農業から透視する環境問題―共生と連帯のためのLesson 佐藤洋一郎+安部 彰 特集3:所内共同研究会のあり方について(1) 「環境思想セミナー」をふりかえって 鞍田 崇×村松 伸×林 憲吾×神松幸弘 |
| No.28 | 特集1:地球研コロキアム〈総括〉地球研の次なるステップへの布石 立本成文×秋道智彌×阿部健一×坂本龍太×中村 亮 特集2:プロジェクトリーダーに迫る! 地上と地下との境界を越えて考える 谷口真人+安富奈津子 特集3:フォーラムの検証 第9回地球研フォーラム「私たちの暮らしのなかの生物多様性」 多様であることの価値を探る 山村則男×湯本貴和×内山純蔵×安部 彰 |
| No.27 | 特集1:国際動向調査 世界をめぐって「地球環境学」の方向と課題を見極める 渡邉紹裕×阿部健一×アイスン・ウヤル×林 憲吾 特集2:終了プロジェクトの報告 ボーダレスに環境問題の解決をさぐる 白岩孝行×岩下明裕×大西健夫×花松泰倫×阿部健一 特集3:地球研コロキアム〈第10回〉 豊かさ・幸福・生の質──人間開発(梅津千恵子) |
| No.26 | 特集1:地球研の第Ⅱ期にむけて(3) 地球研がめざす設計科学とは 遠藤崇浩×大西健夫×鞍田 崇×槙林啓介×源 利文×細谷 葵ほか 特集2:地球研コロキアム〈第8回〉 多様性と調和─共生と進化(湯本貴和) 特集3:地球研コロキアム〈第9回〉 生物・生命・生存・(生業・生活)(門司和彦) |
| No.25 | 特集1:COP10に向けて 座談会「COP10に向けて」 湯本貴和×川端善一郎×山村則男×酒井章子×神松幸弘×遠藤崇浩 特集2:大学生と語る 学生には学生なりに環境学を学ぶ意義がある 阿部健一×中野孝教×神松幸弘×同志社大学・京都精華大学・京都大学のみなさん |
| No.24 | 特集1:地球研の第Ⅱ期にむけて(2) 地球研のめざすもの──研究諮問委員会の意見を受けて 阿部健一×渡邉紹裕 特集2:シンポジウムの検証 第4回地球研国際シンポジウム「越境のジレンマ――新しい流域概念の構築に向けて」 個々のプロジェクト成果を超えた未来可能性を模索する試み |
| No.23 | 特集1:プロジェクトリーダーに迫る! 重層するガバナンスを環境史年表で腑分けする 湯本貴和×西本 太 追悼:日髙敏隆地球研前所長を偲ぶ:追悼の詞 立本成文/ 熱帯林・環境問題・地球研 阿部健一 |
| No.22 | 特集1:地球研の第Ⅱ期にむけて(1)これからの地球研のありかたとは─第I期をふりかえって 立本成文×湯本貴和×福嶌義宏 特集2:プロジェクトリーダーに迫る!ポスト石油時代の社会像を提示したい縄田浩志×渡邊三津子 |
| No.21 | 特集1:地球研コロキアム〈第1回〉 Sustainability 論から見えてくるもの─未来可能性(立本成文) 特集1:地球研コロキアム〈第2回〉 食料生産における持続可能性と未来可能性(佐藤洋一郎) 特集2:第5回 世界水フォーラムに参加して 「水問題解決のための架け橋」はどこまで実現可能か(渡邉紹裕×阿部健一×久米 崇) |
| No.20 | 特集1:領域プログラムを語る 自然と人間の関係性を踏まえた循環の理想型を探る(循環領域プログラム 谷口真人+花松泰倫) 特集2:プロジェクトリーダーに迫る! 生活環境の厳しい地域で生活習慣病がなぜ頻発するのか(奥宮清人×遠藤崇浩) |
| No.19 | 特集1:領域プログラムを語る 未来の地球環境をデザインしたい(文明環境史領域プログラム 佐藤洋一郎+岡本雅博) 特集4:これぞ地球研スピリッツ 高解像度の日降水量グリッドデータで温暖化予測に貢献(谷田貝亜紀代×鬼頭昭雄×安成哲平) |
| No.18 | 特集1:領域プログラムを語る 「ecosophy-地域のみんなの知恵」をキーワードに(地球地域学領域プログラム 渡邉紹裕+児玉香菜子) 特集3:第3回国際シンポジウム 多角的なアプローチを繋ぐ試みが 新たな統合的研究のかたちに(秋道智彌×横山 智×東城文柄) |
| No.17 | 特集1:領域プログラムを語るなぜ、多様性が必要なのか(多様性領域プログラム 湯本貴和+鞍田 崇) 特集2:プロジェクトリーダーに迫る!人間による環境改変が感染症を引き起こすことを、実証したい(川端善一郎+神松幸弘) |
| No.16 | 特集1:領域プログラムを語る「資源」の視点が拡げる可能性と展開(資源領域プログラム 秋道智彌) 特集2:プロジェクトリーダーに迫る!寒冷地の温暖化リスクを現地の言葉で発信したい(井上 元+谷田貝亜紀代) |
| No.15 | 巻頭鼎談:互いに学びあい切磋琢磨を(大塚柳太郎 国立環境所理事長、立本成文 地球研所長ほか) |
| No.14 | 巻頭座談会:地球研の要としての研究推進戦略センター本格始動!(秋道智彌 研究推進戦略センター長ほか) |
| No.13 | 巻頭鼎談:改革の一年をふりかえって(立本成文 地球研所長, 秋道智彌 地球研副所長ほか) |
| No.12 | 巻頭鼎談:未来可能性のための提言を!(古澤 巌 鳥取環境大学長ほか) |
| No.11 | 巻頭鼎談:地球研はアカデミーとしての自己設計を!(米本昌平 東京大学先端科学技術センター特任教授ほか) |
| No.10 | 特別鼎談:終了プロジェクトについて聞く-人間活動と大気中の物質循環-(巌佐庸 九州大学大学院教授・評価委員ほか) |
| No.9 | 特別鼎談:終了プロジェクトについて聞く-流域環境学構築の意義-(岩坂泰信 金沢大学教授・評価委員ほか) |
| No.8 | 巻頭対談:地球研を触媒作用で光を放つ場に!(立本成文 地球研所長, 秋道智彌 地球研副所長) |
| No.7 | 巻頭座談会:地球研初代所長としての6年(日高敏隆 地球研所長, 斎藤清明,鄭躍軍ほか) |
| No.6 | 巻頭座談会:第1回国際シンポジウムを終えて(佐藤洋一郎 第1回国際シンポジウム実行委員長ほか) |
| No.5 | 巻頭対談:地球研の哲学を語る(日高敏隆 地球研所長 鷲田清一 大阪大学理事・副学長) |
| No.4 | 巻頭対談:文(あや)をなして明るい未来可能な地球環境学を(日高敏隆 地球研所長ほか) |
| No.3 | 巻頭対談:オオタカと共生する地球研を(日高敏隆 地球研所長, 湯本貴和 地球研教授) |
| No.2 | 巻頭インタビュー:おのずと省エネ、おのずとコミュニケーション(岡本隆 日建設計設計部門設計室長ほか) |
| No.1 | 巻頭インタビュー:今までなかった学問、今までなかった研究形態(地球研所長 日高敏隆) |