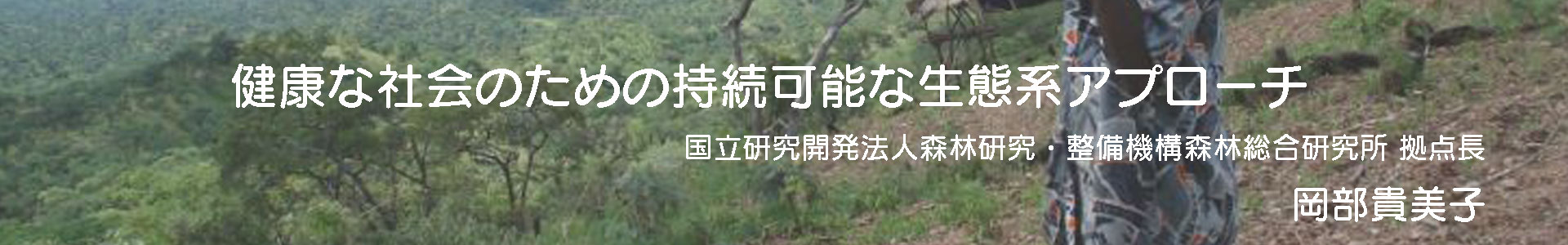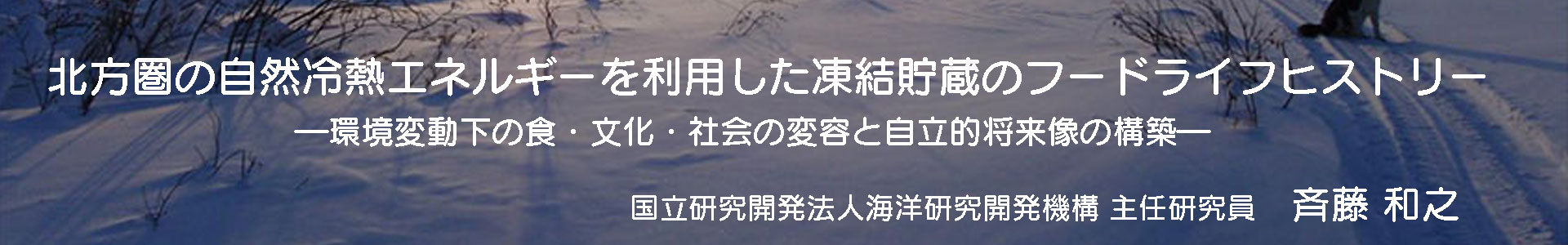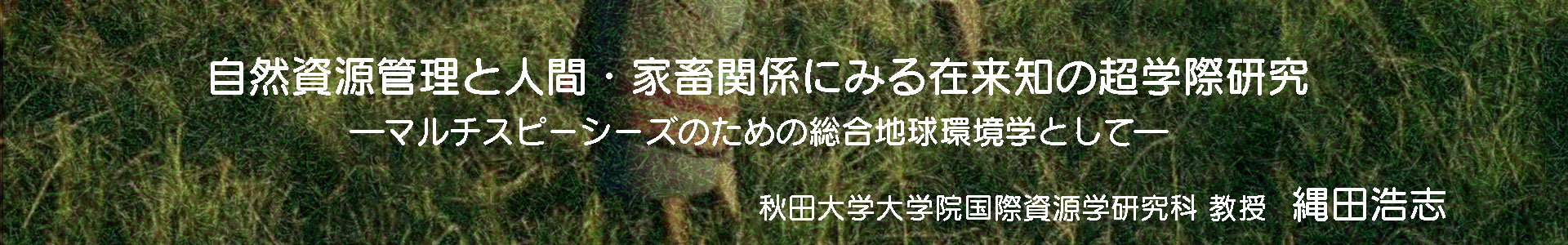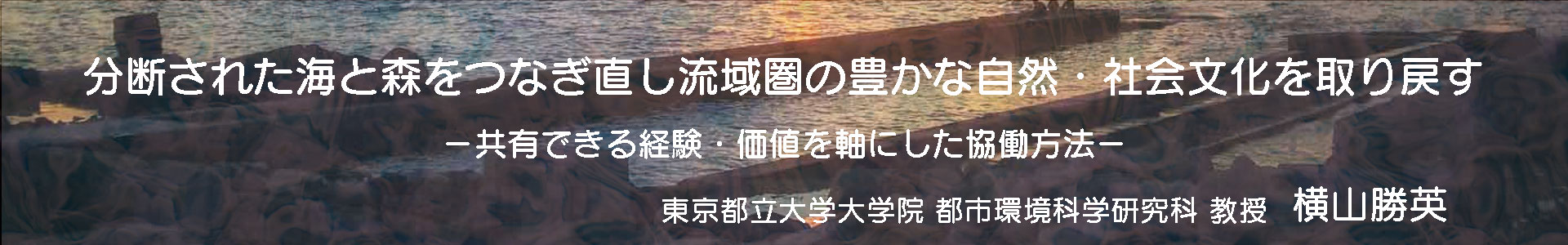2022年度
終了プロジェクト
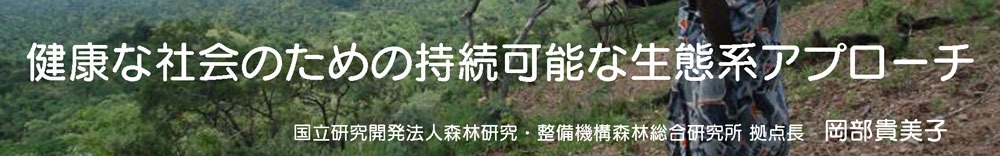
プロジェクト概要
新興感染症はもともと自然生態系の中にあった病原体が、生物多様性や生態系の劣化などによって人の社会に広がってくることが原因であり、環境問題の一つです。しかし病原体の根絶は不可能であり、また人は自然生態系なしには生きてゆけません。そこで新たな感染症が発生するリスクを抑える人と自然のかかわり方を探り、持続的な社会のために必要な行動変容について研究します。新興感染症の75%は、人以外の動物に由来する人獣共通感染症と考えられています。感染症は社会の大きなリスクであることから、複数分野の研究者や政策担当者などが連携する「人、動物、環境の衛生に包括的に取り組む」ワンヘルスという対策アプローチが進められてきました。ワンヘルスの視点による分析から、病原体が自然生態系から人の社会に広がることによる感染症の新興化は、生物多様性の減少、土地利用変化、気候変動、移動や物流のグローバル化、都市化などが主要因であることが明らかになりました。このため国連環境計画(UNEP)などの国際機関は、COVID-19の拡大を受け、新たなパンデミックを防ぐためには環境対策が必須であるとしています。その一方で具体的な対策は、まだ十分に検討されていません。たとえば森林保全が進んでシカなど野生動物が増加・分布拡大した結果、シカを宿主とするマダニも増え、北米や日本でマダニ媒介感染症が拡大してきたと考えられています。新興化リスクの抑制には、生態系保全と新興感染症対策のバランスが必須であり、新たな生態学的アプローチが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。(地球研のHPへジャンプします。)
プログラムへの貢献について PDから一言
野生生物に由来する新興感染症は、現代世界における安心と安全に対する大きな脅威となっています。これに対処するためには、単に医学、感染症学の視点だけでは十分ではなく、生物多様性や気候変動、生態系の劣化への歯止めなどの視点、さらにはこうした環境や疾病を意味付ける文化に対する視点などを総合した新しい思想と行動が必要とされています。 本プロジェクトでは、生態系の劣化の中で出現する人獣共通感染症への学際的対策、コミュニティや社会の生態系や健康と病気の意味を規定する価値観へのアプローチ、さらには、それらを総合して人々の行動変容や社会の健康対策を射程に入れた健康ガバナンスへのアプリーチを展開することで、医学、健康科学と生態学、文化研究を連携させる新しい枠組構築を目指しています。
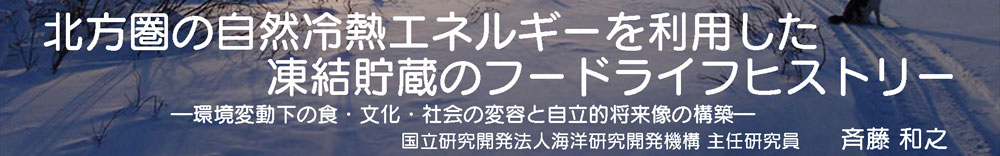
プロジェクト概要
本研究プロジェクトでは、北方圏—なかでも凍土圏という共通環境基盤を持つシベリアからアラスカ、カナダに亘るベリンジア域周辺—での自然冷熱エネルギー(主に凍結)を利用した食糧の保存・貯蔵とその役割・意義について、その歴史的推移や現状をcommunity-basedアプローチで明らかにするとともに、その成果を用いて地域住民自身による将来像描出を支援する
気候変動(温湿潤化、永久凍土の融解)や植民地主義(近代化、国境の設定、貨幣経済)のもたらした全球規模の変化により、在地的社会基盤が不安定化した。その結果、持続可能な伝統的生活様式やその基盤となるコミュニティの紐帯と自律性が世界各地で脅かされ、その将来像を描けなくなってきている。
温暖化の影響が著しい北方圏で、凍結貯蔵はその状況を如実に著している一方で、現地の生活文化のなかで重要な位置を占めていながらこれまで見落とされがちであった。貯蔵施設の機能不全は、ベリンジアの先住民文化や社会だけでなく、食の主権、安全、健康など基本的人権にも影響を及ぼす。また今般のウクライナ侵攻に伴う食糧とエネルギー供給事情の大変動はこの凍結貯蔵の問題をより深刻かつ明瞭にしてゆくだろう.この問題は、気候変動、エネルギー、先住民政策(植民地化)など多様なアクターが関わる問題群であり、学術的には人文社会および自然科学による複合的アプローチが求められる。
この問題に取り組むために我々はフードライフヒストリー(Food Life History,FLH)という思考的枠組みを提案し、地域の社会-生態システムにおける「食サイクルの現状 (Food Life)」という共時的側面と「人間集団の生活史/誌 (Life History)」という通時的側面の統合的アプローチを目指している。
詳しくはこちらをご覧ください。(地球研のHPへジャンプします。)
プログラムへの貢献について PDから一言
地球温暖化は、地球環境問題の中心的な課題です。この温暖化は、影響を受ける社会の基盤を不安定化させ持続可能性に打撃を与えます。本プロジェクトでは、こうした社会としてアラスカとシベリアにまたがる凍土地帯を対象として、そこで人々が作り出してきた食文化、中でも保存、貯蔵の思想と技術に着目します。 凍土を利用した地下貯蔵は、当然、近年の温暖化によって多くの問題に直面しますし、それだけではなく、極北の少数民族社会が経験する近代化や市場化といった社会変化によって、かつての伝統的生態学的知識や実践が揺らいできています。 本プロジェクトでは、こうした環境変化を精確に把握するとともに、凍結保存のために用いられるアイスセラーなどの装置に込められた複数の役割を、地元のコミュニティとともに探り、その意味から人類未来社会の在り方(知識や生の営みのための複数のシステムの保持と活用)を展望しようとする点で、「科学と文化の対話」の一つの方向性を示しています。
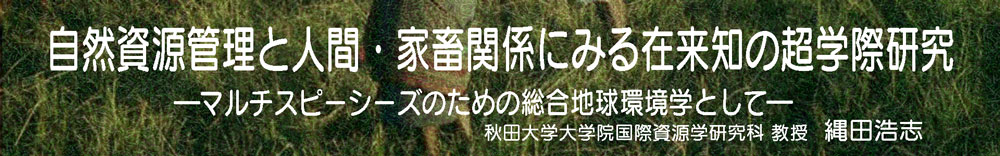
プロジェクト概要
人間にとって(もしくは自民族,自国,自身にとって)の未来を優先的に考えがちな問題意識から脱却し,他種(もしくは他民族,他国,他者)の見え方・考え方・価値観を相対化しつつ,人間以外の種も含む複数種すなわち「マルチスピーシーズ」としてのあるべき「生き方」と「未来可能性」を示していく「総合地球環境学」の構築を目指す.そのために,自然資源管理と人間・家畜関係にあらわれる在来知に着目して,「地球環境問題の根源である文化の問題」に迫る学際的かつ超学際的なプロジェクト研究を推進していく。
プログラムへの貢献について PDから一言
地球環境問題に「資源」を切り口にアプローチしようとするのが本プロジェクトです。その際の方法論として採用したのが「マルチスピーシズ」という手法と思想です。これまで資源は、「人間にとっての」という意味で認識されてきました。しかし無生物も含めた存在を資源として認識するには、その主体も人間以外のマルチスピーシズを想定する必要があります。これまで環境や資源を捉えてきた視座そのものの転換と相対化・複数化を試みようとする野心的で実験的な研究です。資源化に作用する重要な要員として、文化を措定し、その文化も脱人間中心化しようとする研究は、科学と文化の対話プログラムにもう一つの可能性を与えてくれます。
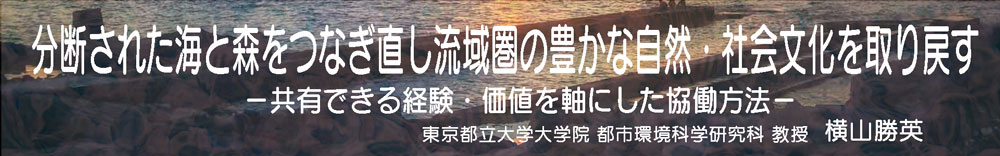
プロジェクト概要
海と陸を隔てる大規模堤防の建造は、自然環境の分断だけではなく、住民の賛成・反対への分断や、目を背ける意図的無関心層の増加をもたらし、コミュニティー文化が破壊されることが多い。 そこで、つながりの再構築を⽬指して、三陸リアス海岸(宮城県気仙沼市)と有明海(柳川市・諫早市)で研究を行う。 気仙沼では森は海の恋人運動によって「つながり意識」の変容に成功しており、また、東日本大震災後に津波防潮堤を建設せずに湿地・干潟を再生した地域がある。⼀方、諫早湾では潮受け堤防や陸と海の間としての干潟の保全再生を巡って裁判が20年間続き、地域社会が分断されている。 そこで、森は海の恋人活動を人文社会学的に評価し、また、防潮堤の有無による生態系構造の違いを自然科学研究により評価し、両者から分断修復の方法論を見いだす。そして、ウナギが遡れる森川里海づくりとして、有明海柳川市において市民・学生・行政・研究者の協働による小規模な社会実験を行い、さらに諫早湾流域圏に適用して検証する。
プログラムへの貢献について PDから一言
森と川と海の連関は、現代社会においては常に切断・分断の危機にあります。それだけでなく、社会にも多種多様な分断線が引かれ、固定化されることで共生を困難にしています。本プロジェクトはこうした状況を対象化して、その分断されたもの同士をつなぎ合わせる試みをすることで、人々の生活、社会・文化の継承、そして環境の保全を図ろうとする野心的な試みです。 切り離されたものを再びつなぎ直すためには、従来の科学的知識の啓発や近代技術による統御では十分ではありません。そのために、環境問題の現場で作動する地域の知恵を生かし協働を可能にする方策(それが環境文化の創成につながります)を提案するのがこのプロジェクトです。
2023年度終了プロジェクトはこちら