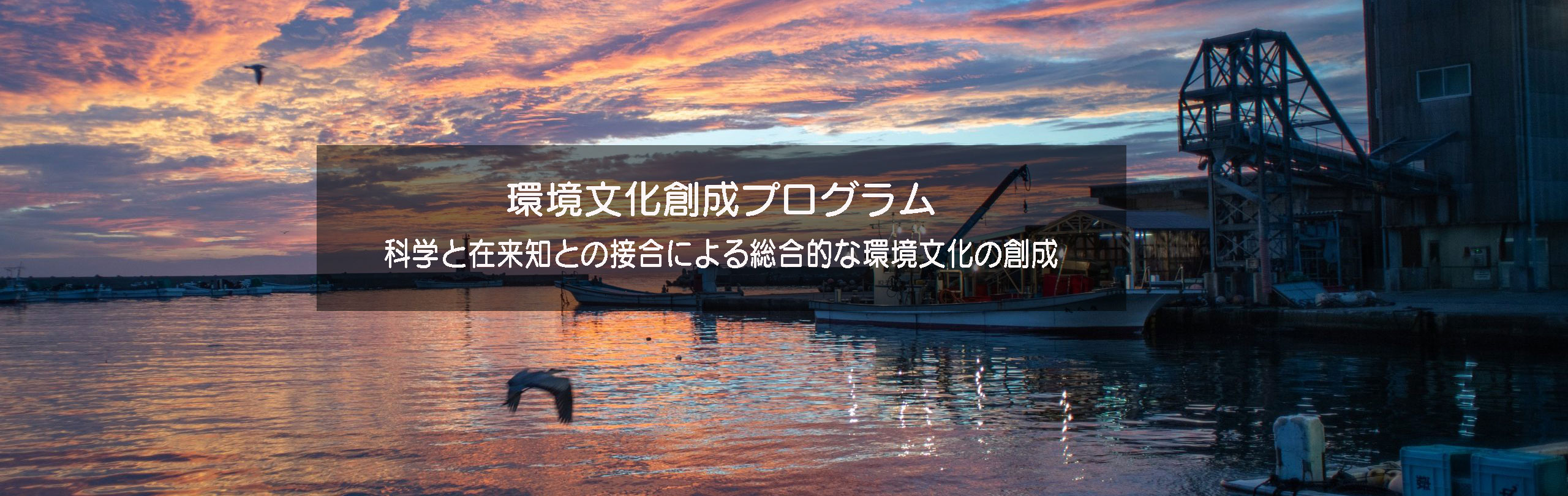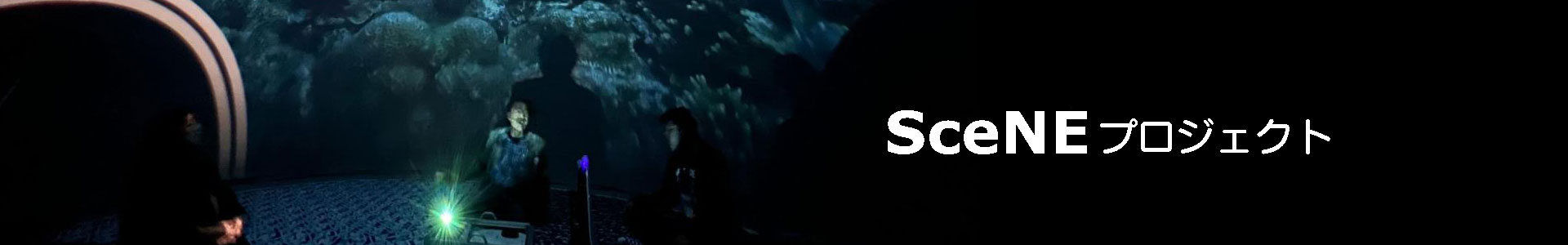このプログラムは環境文化創成プログラムと言いますが、そもそも環境文化とは何でしょうか?
それを説明するために、まず本プログラムの基本的認識を述べます。環境問題が地球規模で喫緊の課題となっていることは間違いありません。その解決のために「科学的に正しい知識」を提示・提供することは重要です。しかし正しい知識を与えるだけでは、ただちに人々や社会の行動様式や価値観の変容を導くことはありません。人々の生き方や価値観の変容をもたらすには文化の視点が核心になります。
本プログラムが目指す環境文化の創成とは、科学と文化がお互いの「絶対的正しさ」を一旦括弧にくくって、相互に対話することで、新しい価値観の創造につなげていくプロセスなのです。
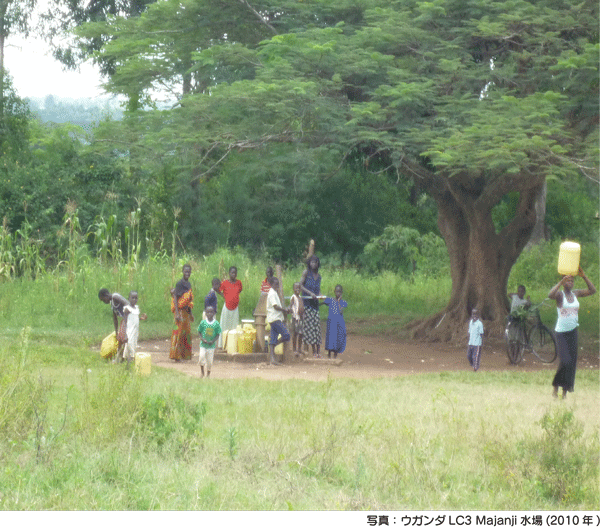
NEWS
【大山修一教授と塩谷サブリーダー 日本沙漠学会第36回学術大会で受賞】
2025.7.10 有機物循環プロジェクトリーダー・大山修一教授とサブリーダー・塩谷暁代(京都大学特定助教)が学術大会発表賞を受賞しました。
※詳細はこちら【大山修一教授の活動が日本公式SNS「JapanGov」で紹介されました。】
2025.6.17 有機物循環プロジェクトリーダー・大山修一教授の活動が、日本公式SNS「JapanGov」で紹介されました。
※詳細はこちら→(Facebook) (X)【SceNEプロジェクト ギャラリーオープニングイベント】
2025.6.7 ギャラリー・伏見港「珊瑚庵」がオープン記念展示を行いました。
※詳細はこちら【終了FS論文】
2025.5 終了FS「北方圏の自然冷熱エネルギーを利用した凍結貯蔵のフードライフヒストリー」(代表:斉藤和之)の論文 ” Integrated analysis of socio-ecological impacts on underground food storage in Beringia” が専門誌Environmental Researchに掲載されました。
※詳細はこちら【終了FS論文】
2025.1 終了FS「健康な社会のための持続可能な生態系アプローチ」(代表:岡部貴美子)の論文 ”Forest Fragmentation and Warmer Climate Increase Tick-Borne Disease Infection” が専門誌EcoHealthに掲載されました。
※詳細はこちら【環境文化創成プログラムセミナーを開催しました。】
2025.4.2 地球環境問題にとって 文化とは何か」というテーマでセミナーを開催し、3プロジェクトのリーダーと外部専門家による発表と対話を行いました。 ※詳細はこちら (PDFが展開します)
【金沢21世紀美術館「すべてのものとダンスを踊ってー共感のエコロジー」地球研DAYS】
2025.2.15-16 金沢21世紀美術館で開催された「すべてのものとダンスを踊ってー共感のエコロジー」に有機物循環プロジェクトとSceNE プロジェクトが出展しました。 ※詳細はこちら
【RIHN-KLASICA Workshopを開催し、渡邊剛准教授が講演を行いました。】
2025.2.11 地球研とKLASICA(環境教育プログラム・社会変革のための知識と学習: Knowledge, Learning and Societal Change Alliance)の共同主催で、「科学とアート 新たな創造的関係を探る」を開催し、SceNE プロジェクトリーダーの渡邊剛准教授が講演を行いました。
※詳細はこちら (PDFが展開します)【大山修一教授 第11回ワールドおもしろいアワードを受賞】
2025.2 有機物循環プロジェクトリーダーの大山修一教授が、第11回ワールドおもしろいアワードの受賞者に選ばれました。この賞は、グランフロント大阪のナレッジキャピタルが授与する賞で、「Omosiroi(面白い)」をコンセプトに、世界を面白くする人に対して与えられるものです。
※詳細はこちら【終了FS論文】
2024.9 終了FS「北方圏の自然冷熱エネルギーを利用した凍結貯蔵のフードライフヒストリー」(代表:斉藤和之)の論文 ” Food life history and cold storage in Greater Beringia. Part I: Preliminary interdisciplinary investigation” が専門誌Polar Scienceに掲載されました
※詳細はこちら【大山修一教授 有機物循環プロジェクト 京都新聞に掲載されました。】
2024.9.8 京都市内のホテルの協力を受けて、レストランの食品ごみを材料に、独自のコンポストを開発する取り組みが紹介されました。
※詳細はこちら【フェローシップ外国人研究員のご紹介 REBBER, André】
2024.7.25-9.25 アンドレ・クレベル博士を受け入れました。※詳細はこちら
【SceNEプロジェクト シンポジウム開催のご報告】
2024.7.17 SceNEプロジェクトが「時間のものさしシンポジウム」を開催しました。※詳細はこちら
【招へい外国人研究員のご紹介 ROSSBERG, Axel Gerhard】
2024.6.3-8.16 アクセル・ロスベアグ博士を受け入れました。※詳細はこちら
【大山修一教授 有機物循環プロジェクト 洛タイ新報で小学校での事業が紹介されました。】
2024.6.6 地球研と京都府教育委員会の連携事業の一環として、京都府内の井手小学校と多賀小学校が取り組んでいる総合的な学習「食品ごみで肥やしを作ろう」と題した授業が紹介されました。この事業は地球研の有機物循環プロジェクトの京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の塩谷暁代特定助教と青池歌子研究員が協力しています。
【SRIREPプロジェクト(2024.03終了)地球研市民セミナー開催のご報告】
2024.6.6 地球研市民セミナー・SRIREPプロジェクト「文化は経済を超えられるのか?」を開催しました。※詳細はこちら
【サプライチェーンプロジェクト(2024.03終了)地球研市民セミナー開催のご報告】
2024.4.29 地球研市民セミナー・サプライチェーン・プロジェクト「食べものの足跡をたどると、生きものたちへの影響が見えてきた。」を開催しました。※詳細はこちら
【大山修一教授 中日新聞で高校での講演が紹介されました。】
2024.3.6 有機物循環プロジェクト(PR)リーダー大山修一教授が2024年3月2日に市邨高校のイベント「第6回 市邨高校難民支援の夕べ」において、「映画『グレートグリーンウォール』の鑑賞にあたって」と題して、西アフリカのサヘル地域における人口増加、飢餓や貧困、紛争・テロの拡大、政情不安について講演をおこないました。
(中日新聞2024年3月6日付け 朝刊 第14面に掲載)【松田PD・特任教授の論文が『文化人類学研究』に掲載されました。】
2023.12 『文化人類学研究』24巻(2023)「在来知と科学知のコンヴィヴィアルな関係性のための試論」
※詳細はこちら (PDFが展開します)【大山修一教授 洛タイ新聞で小学校での事業が紹介されました。】
2023.12.8 地球研と京都府教育委員会の連携事業の一環として、京都府内の井手小学校と多賀小学校が取り組んでいる給食食材の廃棄生ゴミを肥料として利用する学習が紹介されました。
この事業には地球研の物質循環プロジェクトの大山修一教授と京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の塩谷暁代特定教授が協力しています。【国際会議SRI 2023セッション発表】
2023.6.26-30 パナマ共和国にて国際会議 Sustainability Research & Innovation (SRI) 2023で環境文化創成プログラムのセッション発表があり、プロジェクトリーダーとプログラム研究員が研究発表します。
大山修一(PR研究プロジェクトリーダー)
タイトル:Waste management for green space promotion in Niger, Niamey
Alimata Sidibe(プログラム研究員)
タイトル:Cultural related air pollution and health: case of the urban city of Bamako in Mali.※詳細はこちら
【榊原正幸教授 朝日新聞で研究内容が紹介されました。】
2023.4.13 朝日新聞でSRIREPプロジェクト(FR)リーダー榊原正幸教授の研究が紹介されました※詳細はこちら
【大山修一客員教授の活動が「外務省ODA開発協力白書」に掲載されました。】
ニジェールにおける緑化活動が『2022年版 外務省ODA開発協力白書 日本の国際協力』に掲載されました。
「都市を綺麗に、土地を緑に、生活を豊かに」 JICA草の根技術協力事業(草の根協力支援型)
該当ページ抜粋 ※詳細はこちら
開発協力白書全体 ※詳細はこちら (PDFが展開します)
【大山修一客員教授のプロジェクトがJ-Storiesで紹介されました。】
日本の科学・技術を紹介するJ-Storiesで大山(PR)プロジェクトが紹介されました。
(日本語)『ゴミの力で砂漠を緑化、アフリカの農村が得る収入と和解京大研究者が挑む「争いのない社会」への取り組み』 ●詳細はこちら
(英語)『Greening the desert with trash Japan research helps green Niger desert, improving the environment and reducing conflict』
※詳細はこちら
(YouTube英語) #50 Greening with Garbage【大山修一客員教授 松下幸之助 花の万博記念奨励賞を受賞】
バイオマス循環プロジェクト(FS)リーダー 大山修一客員教授が第31回(2023年) 松下幸之助記念志財団 花の万博記念奨励賞を受賞しました。
※詳細はこちら(松下幸之助記念志財団HP)
※受賞記念講演会のご案内・申し込みはこちら(申し込み先着200名)。
講演タイトル「ごみで地球をすくう-農業の起源と『ごみの野積み』理論」【渡邊FS研究プロジェクト 喜界島演劇「ユラウ」東京公演のおしらせ】 詳細はこちら
喜界島の人と自然の研究データ、フィールドワークの結果をもとに制作した演劇作品「ユラウ」を上演します。
2022.12.20~22 3日間4回公演 ※上演詳細については上のリンクからご覧ください。【榊原正幸教授 NHKワールドTVで研究内容が紹介されました。】 ※詳細はこちら
2022.9.1 NHKワールドTV でSRIREPプロジェクト(FR)リーダー榊原正幸教授の研究が紹介されました。
【松田特任教授のインタビューがWORKSIGHTに掲載されました。】
コクヨワークスタイル研究所のオンラインマガジン・WORKSIGHTに松田特任教授のインタビューが掲載されました。
前編:分断を乗り越える「パラヴァー」の教え: ※詳細は こちら
後編:対話から辿り着く「真実」がある: ※詳細は こちら
【金本圭一朗准教授 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞】 ※詳細はこちら(文部科学省HP)
サプライチェーンプロジェクト(FR)リーダー 金本圭一朗准教授が若手科学者賞を受賞しました。
【榊原正幸教授 バンドン工科大学よりGanesa Widya Jasa Adiutama賞を受賞】 ※詳細はこちら(地球研HP)
SRIREPプロジェクト(FR)リーダー 榊原正幸教授がインドネシア国立バンドン工科大学のGanesa Widya Jasa Adiutama(Ganesa Award)を受賞しました。