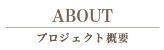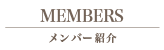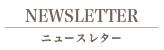住民社会・企業・統治班
地域社会の特質や問題点を踏まえ、どうしたら住民が積極的に泥炭地回復を積極的に行うのかを研究する。その過程で、住民の土地権を強化し、住民の所得を向上させ、住民により多くの選択肢を提供する方策を考える。
すなわち、地域住民、企業による泥炭地管理、泥炭火災予防に関わる行動と戦略に関する研究、パルディカルチュアモデル構築に向けた地元民・移民の村の相違と土地権の多様性を踏まえたコミュニティ研究、企業モノカルチュア活動のフェーズアウトに資する世界と地域の泥炭開発史と統治研究にむけた予備的調査を行う。
また地域住民の特性を踏まえた環境脆弱地域の変容や泥炭問題を資源国の経済発展の方向から研究する。さらに、環境を犠牲にしない経済発展を歴史的にまた今日の問題として考察する。また、18世紀からの泥炭社会やその周辺地域の社会経済史を再構築する。
国際比較研究班
研究目的:
国際比較研究班では、泥炭地をめぐる開発史、泥炭地管理に社会経済的分析、泥炭地開発による社会的影響などについて、国際的な比較研究を行う。環境ファイナンス研究については、泥炭地でREDD+認証コンセッションにおいて事例研究を実施し、泥炭地管理実施の評価手法のための指標を検討する。現在比較対象地域、国としては、インドネシア・中カリマンタン、マレーシア、ペルー、ロシアでの調査をすすめている。
研究内容:
- 1)泥炭開発史の比較
植民地期から現在までの泥炭開発史を、文献資料、関係者への聞き取りなどによって明らかにする。今年度は主にその分析のための基礎的な文献資料を収集する。
- 2)泥炭地管理の社会経済的要因
泥炭地開発をめぐる社会経済的な要因について明らかにする。泥炭地利用、森林伐採、アブラヤシ、アカシア園開発など、土地、資源管理に関する研究を行う。
- 3)泥炭地の修復に向けた環境ファイナンス研究
泥炭地におけるREDD+ , ERC, High Carbon Stock, についての事例研究を行う。REDD+については、中カリマンタン・REDD+サイト(生態系修復コンセッション)において、事例研究を実施する。今年度は社会的基礎調査の予備的研究を実施する(レジリアンス、健康被害調査も含む)。
- 4)国際泥炭研究ネットワーク構築
国際的な泥炭研究ネットワークの強化、UNFCCC, GCFなどの国際交渉プロセスの評価/分析、ASEANヘイズ対策についての取り組みについて、関連国際会議での成果発表を予定している。
物質循環班
2015年の泥炭火災ではインドネシア全土において約210万ヘクタール(四国と同程度)の範囲が延焼した。この年は3ヶ月で4500万人が被災し、50万人以上が上気道感染症を患い、さらには、1万人がぜんそくを発症し、12人が死亡した。泥炭火災の防止対策として、政府は軍隊を動員して消火活動の実施を決定し、また、企業に対する新規泥炭開発許可の発行を停止した。泥炭火災の長期的な解決策として、泥炭地の再湿地化を求める声があがるとともに、大気汚染観測および健康被害調査の必要性が高まっている。
今日の深刻な泥炭火災をもたらした要因として以下が挙げられる。
1)泥炭湿地林が人間による攪乱に対して大変脆弱な生態系であること
2)泥炭地域社会は社会資本蓄積が少なく、実効支配のない国家管理地域であり、社会制度的にもきわめて脆弱であること
以上を踏まえ物質循環班では、人口増加・移民など熱帯泥炭湿地林から乾燥泥炭地(プランテーション・荒廃地)へ急激に変化する東南アジア地域において、森林から焼け跡・草地などへの変化が動植物相や炭素など物質循環に及ぼす影響についての現地調査を行う。また、頻発する泥炭火災からの煙害に起因する温室効果ガス排出や大気汚染粒子の排出量調査や、火災発生源の地域における住民の呼吸器の健康被害について疫学的調査を行う。