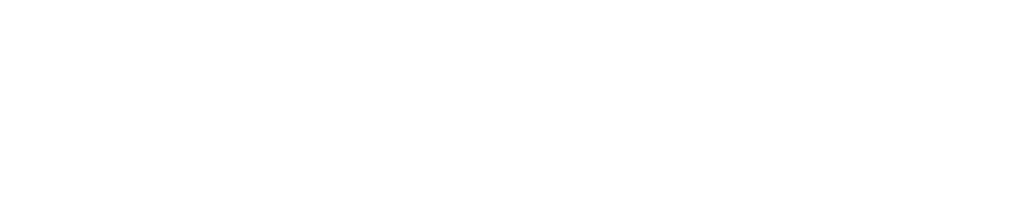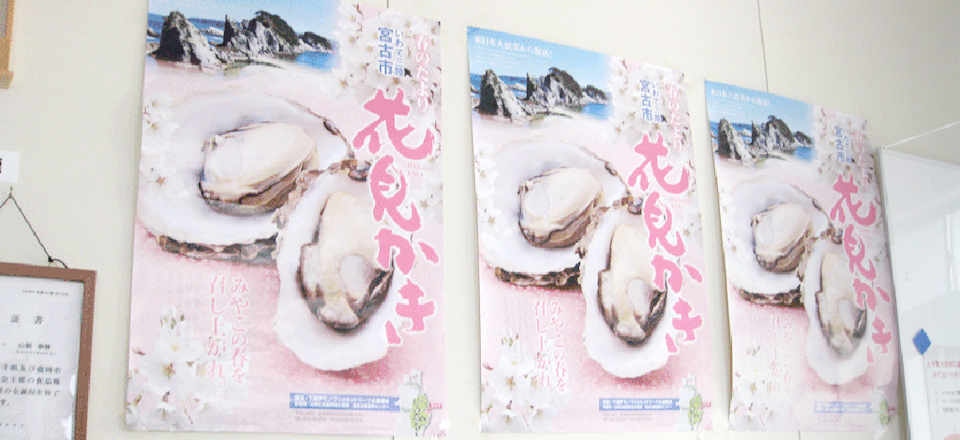OBJECTIVE 背景と目的

川井集落における旧焼畑地でのヒアリング
サクラマス
川井村の民俗資料(北上山地民族資料館にて)
直売所
地域社会の在来知が持つ、
地域のレジリアンス*(再生力)と未来への可能性
本研究では、東日本大震災後の岩手県閉伊川流域を中心とした東北地方を対象として、
ヤマ、カワ、ウミに関する生産活動を調査・研究しています。
在来知*は、小規模だけれども多様な生産活動を可能にし、環境負荷が少ない持続可能な人間社会を営む基礎を担ってきました。本研究では、歴史的に保持されてきた在来知とそれにもとづく生活の知恵が、東日本大震災後の地域社会の緊急支援時期から、その後の生活再興期にわたって多様な形で地域社会を支えてきたことに着目しています。在来知が、流域を中心とする環境保全に果たしてきた役割の重要性を検討し、学際的な観点から在来知を重視した未来の可能性を探っています。
-
レジリアンス
resiliance
ある環境が災害など負の環境インパクトを受けた際の回復能力のこと。
-
在来知 ざいらいち
Local Environmental Knowledge
地域社会に存在する、世代を超えて経験し蓄積されてきた周辺環境と生物に関する知恵(知識)と工夫(技術)の実践複合体。在来環境知。
閉伊川 へいがわ
岩手県中央部,北上高地の兜明神岳付近に源を発し,蛇行しながら深い峡谷をつくって東流し,宮古湾に注ぐ。全長 75.7km。上流から川内(かわうち),箱石(はこいし),川井(かわい),腹帯(はらたい),茂市(もいち)の各集落があり,河口の三角州低地に宮古市がある。これら本流のほか、小国川など240本を超える支流があります。
これら流域には、宮古湾を中心として、縄文時代以来の人々の暮らしと生活の工夫を伝える考古資料が豊富にあります。たとえば、宮古市崎山貝塚遺跡からは、縄文時代前期から後期(約6,000~3,500年前)の動植物遺存体が豊富に出土しています。
ACTIVITY 研究内容
-
在来知研究

地域住民によるヤマ・カワ・ウミの複合的な利用の中で培われたきた在来知の実態を扱っています。
具体的には、小規模生産農家および漁家を中心とした聞き取り調査、参与観察調査、歴史文書・行政文書による文研調査、人為的な二次植生や淡水魚類の生態調査を行っています。
-
レジリアンス研究

震災によって大きな影響を被った東北地域では、在来知や科学知が、小規模な生産活動の持続と回復のために、どのような役割を果たしているのか/果たしうるのでしょうか?小規模生産者やコミュニティの人々への詳細な聞き取り調査や、土壌の化学分析などを通じて明らかにします。
-
環境教育実践研究

在来知研究班とレジリアンス研究班の成果を、水圏環境教育のイベントやワークショップ、在来知マップなどを通じて、地元の方々と共有します。
MEMBER 研究メンバー
(「在来知と環境教育」研究会 )
本研究会は文化人類学、社会学、考古学、経済学、植物学、農学などをを専門とする研究者と、
地元のNPO関係者などで構成されています。
リーダー
-
羽生 淳子
総合地球環境学研究所 教授
在来知研究班
-
福永 真弓
大阪府立大学 准教授
-
William Balee
テューレーン大学 教授
-
濱田 信吾
大阪樟蔭女子大学
-
大石 高典
総合地球環境学研究所 プロジェクト研究員
-
内藤 大輔
総合地球環境学研究所 プロジェクト研究員
レジリアンス研究班
-
羽生 淳子
総合地球環境学研究所 教授
-
David Slater
上智大学 准教授
-
後藤 康夫
福島大学 教授
-
後藤 宣代
奥羽大学 非常勤講師
-
金子 信博
横浜国立大学 教授
環境教育実践研究班
-
佐々木 剛
東京海洋大学 准教授
-
日下 宗一郎
ふじのくに地球環境史ミュージアム
-
飯塚 宣子
NPO平和環境もやいネット事務局長
- 泉 正一
NPO早池峰山荘/かわい元気社 専務理事
-
山根 幸伸
宮古湾の藻場・干潟を考える会 会長
- 水木 高志
NPOさんりくESD閉伊川大学校 事務局長
CONTACT お問合せ