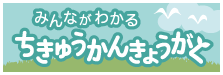ポイント
- 2011年の東日本大震災後、東北大学大学院生命科学研究科の生態適応センター、企業やNGOなどで構成した環境機関コンソーシアムのメンバーを中心に、生態系からの恵みを活かした復興を行う「海と田んぼからのグリーン復興」という活動を開始。
- 震災後8年が経過したなかで、活動を総括した著書「生物多様性は復興にどんな役割を果たしたか:東日本大震災からのグリーン復興」が地球研の叢書として出版。様々な地域で取り組んできた復興の歩みを、グリーン復興という視点から見つめなおし、今後に繋げたい、という思いでまとめた本を出版。
- 本の出版を記念して、12月1日に東北大学大学院生命科学研究科生態適応センターと地球研の共催にて、グリーン復興の反省と今後の可能性について議論するシンポジウム「自然資本を活かした防災と震災復興:東日本大震災からのグリーン復興と今後の展開」を開催。
概 要
2011年の東日本大震災から8年が経過しつつあります。その間に、熊本地震、北海道北海道胆振東部地震、2018年台風21号による高波被害など大きな被害をおよぼした災害に直面しましたが、その備えや対策は、東日本大震災の経験が活かされているとはいえない状況です。
また、震災後、巨大な防潮堤などにより災害からの被害を軽減するという対策が優先されてきました。東日本大震災後、東北大学大学院生命科学研究科・生態適応センター、企業やNGOなどで構成した環境機関コンソーシアムのメンバーを中心に、震災直後、議論を重ね、東北地方の農林水産業が享受すべき将来の生態系からの恵みを見据え、海や田んぼの生態系の豊かさや、生物多様性を育む復興を行うことで、農林水産業とともに生きてきた地域が、より着実に、復興するという理念のもと、「海と田んぼからのグリーン復興」という活動を行ってきました。
これまでに様々な地域で取り組んできた復興の歩みを、グリーン復興という視点から見つめなおし、今後に繋げたい、という意図で、「生物多様性は復興にどんな役割を果たしたか:東日本大震災からのグリーン復興」という本を地球研叢書として出版しました。
また、本の出版を記念して、東北大学大学院生命科学研究科・生態適応センターと地球研との共催でグリーン復興の反省と今後の可能性について議論するシンポジウム「自然資本を活かした防災と震災復興:東日本大震災からのグリーン復興と今後の展開」を12月1日に開催します。
地球研叢書について
タイトル
『生物多様性は復興にどんな役割を果たしたか:東日本大震災からのグリーン復興』
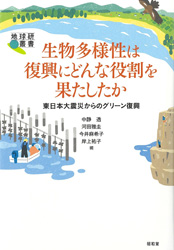
中静透・河田雅圭・今井麻希子・岸上祐子編
- Ⅰ. 山と海のつながりが町を復活させる―南三陸町のチャレンジ
- Ⅱ. 松島湾のめぐみが復興を支える―浦戸諸島の自然に生きる
- Ⅲ. グリーン復興の可能性を探る
- Ⅳ. 防潮堤は必要なのか
- 終章. 生物多様性や生態系は復興にどんな役割を果たしたか
出版記念シンポジウムについて
シンポジウム「自然資本を活かした防災と震災復興:東日本大震災からのグリーン復興と今後の展開」
- 日 時
- 2018年12月1日(土)14:00より
- 場 所
- 東北大学大学院生命科学研究科生命科学プロジェクト総合研究棟1階 講義室(⇒ アクセス)
- 主 催
- 後 援
- 東北地方環境事務所
- 対 象
- 一般
- 備 考
- 事前申込不要、参加無料
- 趣 旨
- 2011年の東日本大震災後、東北大学大学院生命科学研究科生態適応センター、企業やNGOなどで構成した環境機関コンソーシアムのメンバーを中心に、生態系からの恵みを活かした復興を行う「海と田んぼからのグリーン復興」という活動を始めました。震災後8年が経過したなかで、活動を総括した著書「生物多様性は復興にどんな役割を果たしたか:東日本大震災からのグリーン復興」が出版されました。様々な地域で取り組んできた復興の歩みを、グリーン復興という視点から見つめなおし、今後に繋げたい、という思いでまとめた本です。本の出版を記念して、グリーン復興の反省と今後の可能性について議論するシンポジウムを企画しました。
- 内 容
- - 趣旨説明
河田雅圭 (東北大学教授) - - 人口減少時代における生態系を基盤とした防災・減災(Eco-DRR)の推進
一ノ瀬友博 (慶應義塾大学 教授) - - 地域の自然資本を活かした防災と復興 ~環境省の取組~
鳥居敏男 (環境省大臣官房審議官) - - 「いのちめぐる」サスティナブルなまちをつくる
太齋彰浩 (一般社団法人サスティナビリティセンター) - - 海とたんぼからのグリーン復興を振り返る
中静透 (総合地球環境学研究所 プログラムディレクター・特任教授) - - 総合討論
- - 趣旨説明