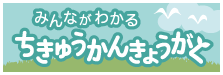- 日 時
- 2019年4月22日(月)14:30 - 17:00
- 場 所
- 総合地球環境学研究所 セミナー室 1・2 (⇒アクセス)
- 主 催
- 平成30年度所長裁量経費
「地球環境学の理論的基礎としての風土論/風土学の概念分析とリフレーミング」 - 連絡担当者
-
研究部FEASTプロジェクト 太田和彦

今日、「風土」は、持続可能な地域計画や資源管理、世代間対話の分野から高い関心が寄せられている概念の一つです。地球研のホームページで「風土」という語句が用いられた記事は493件、科研費で「風土」をキーワードとしている研究課題は50件、存在します(いずれも2019年4月11日閲覧)。
先行する研究プロジェクトにおいて、風土概念は、私たちが場所や共同性についての新しい知見や記述、選択肢を見出すことを助けるための、いわば"思考の補助線"として多く用いられています。しかし一方で、そのような運用のただなかにおいて風土概念がどのように変化・改訂されつつあるか、あるいは変化・改訂の期待に応えうるかという観点からの研究は十分になされていません。
平成30年度所長裁量経費を用いたグループ研究「地球環境学の理論的基礎としての風土論/風土学の概念分析とリフレーミング」では、和辻哲郎やオギュスタン・ベルクらによって検討された風土概念が、地球環境学に資する概念としてどのようにリフレーミング可能かという観点から検討しました。今回の勉強会では、本グループ研究の成果、および「風土概念という"レンズ"の性質」・「学際研究・超学際研究手法への寄与」・「“ローカルな環境倫理”との接続」という3つの軸のもとでの風土論研究の展開の可能性についてご報告いたします。
あわせて、熊澤輝一さんに、これから人工知能やロボットが当たり前になっていくとしたら、風土論はその世界をどう切り取ることができるのか、という問いを検討する調査・実験企画をご紹介いただきます。また、早稲田大学の塩谷賢さんを交えて、風土概念はどのような学術分野と併せて(あるいは比較して)、どのような方向性のもとで用いることで議論の射程を広げうるのかについて意見交換の機会を設けたいと思います。ご関心がございましたら、ぜひお気軽にご参加ください。
※当日参加も大歓迎ですが、参加をご希望の方は、事前にご一報いただければ幸いです。
++プログラム++
- 14:30 - 15:30
- 15:30 - 16:00
- 16:00 - 16:45
- 16:45 - 17:00
報告「2018年度グループ研究『風土論のリフレーミング』の成果と課題」(太田和彦)
提題「人間と計算機が知識を処理し合う未来社会の風土論」(熊澤輝一)
コメント(塩谷賢)
まとめ