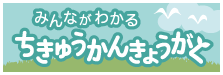- 日 時
- 2016年2月12日(金) 10:00 - 17:00
- 場 所
- コープ・イン京都 会議室204、205
- 主 催
- 総合地球環境学研究所
- 使用言語
- 発表者によって日本語・英語になります。
- 問い合わせ
 蒋 宏偉
蒋 宏偉
【 プログラム 】
- 10:00 - 10:15
- 10:15 - 10:30
- 10:30 - 11:00
- 11:00 - 11:45
- 11:45 - 13:15
- 13:15 - 14:00
- 14:00 - 14:45
- 14:45 - 15:15
- 15:15 - 16:00
- 16:00 - 17:00
人間文化研究機構エコヘルスプロジェクトの概要
ハイン・マレー(総合地球環境学研究所)
人間文化研究機構エコヘルスプロジェクト・民博ユニット報告
文明における食文化の布置(Constellation of food and foodways in the civilization)
野林 厚志(国立民族学博物館)
From sustainable landscapes to sustainable diets: How foodscapes, diets, and ecological health are inter-related
Steven R. McGreevy (総合地球環境学研究所)
Gochiso: Food sharing and Social Dining Platform
Philip L. Nguyen (京都大学)
昼食
Food representation and choice
濱田 信吾(大阪樟蔭女子大学)
The changing human-nature relation in Sundanese rural areas
Budhi Gunawan(Padjadjaran University, Indonesia)
コーヒーブレーク
健康の再考:グローバル化社会での健康を考える
門司和彦(長崎大学)
総合討論/パネル討論
【 趣 旨 】
人間の健康を考える際、生存の基本要素となる「食」及び「食」を供給する環境を避けてはいけない。言い換えれば、安全な環境で生産された食から適量の摂取によって、健康が維持できる基礎が保たれることである。しかし近年、アジアの地域社会における急速な近代化は、地域従来の食生活及び「食」を提供する環境に大きな変化を与えてきた。外的要因の変化には、大量生産・大量消費を前提とする食生活の近代化、近代農業を基礎とする食料供給のグロバール化などがある。一方、健康意識、健康食の考え方などという内的要因は、調整が遅れていて、地域従来の文化がまた根強く残されている。これらの内外要因の変化及び相互作用は、地域住民の栄養改善、感染症の低下などに貢献したものの、農薬・化学肥料の使用による環境汚染と劣化、食品の安全性の低下、さらに住民の環境汚染に起因する疾病と生活習慣病の増加など負の影響ももたらした。いわば、近代化は、必ずしも持続的に人々の健康改善に寄与してこなかった。
このような状況を緩和するために、保健学と農学の研究は、それぞれの立場から健康食の摂取、運動の促進、農薬ポジティブリスト制度などの提案を行ってきた。しかしこれらは、あくまでも対症療法であり、問題の根本的な解決に資することがなかった。問題の解決には、アジア地域社会における伝統的な「健康」、「健康食」、「食環境」、そしてこれら三つの側面にめぐる内外要因の変化を整理・分析する必要がある。
今回の国際ワークショップは、人間文化研究機構・広領域連携型基幹研究「アジアにおける「エコヘルス」研究の新展開」の総合地球環境学研究所(地球研)ユニット、国立民族学博物館ユニット及び地球研プロジェクト「持続可能な食の消費と生産を実現するライフワールドの構築」が共同企画した研究会である。研究会では、三グループの研究者は、各自の研究調査を踏まえつつ、アジア地域社会における健康の考え方に焦点をあて、地域食文化及び食糧生産供給の歴史と現状から、問題点を報告しつつ、健康・食・環境のあるべき関係と姿を幅広く議論する予定である。