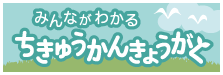総合地球環境学研究所(地球研)では、地球環境学のためのリモートセンシング(遠隔画像解析)とドローン(無人航空機)の使いみちについて最新の情報を共有するため、下記の通りワークショップを催しました。
- 日 時
- 2015年6月9日(火) 13:30 - 17:00
- 場 所
- 総合地球環境学研究所 セミナー室3・4(⇒アクセス)
- 対 象
- 所内外の研究者
- お問い合わせ
- 総合地球環境学研究所 研究高度化支援センター 近藤康久

参加無料・事前申込不要
プログラム
- 13:30
 PDF
PDF - 13:45
 PDF
PDF - 14:45
 PDF
PDF - 15:15
- 15:30
ライトニングトーク(各5分)
- 「ドキュメンタリー映像における空間使用はどこまで可能か?」臼田乃里子
 「ドローンによる空撮技術を用いた湖面の観測」上原佳敏(地球研)
「ドローンによる空撮技術を用いた湖面の観測」上原佳敏(地球研) 「4D-IMADAS-GGRFとUAVカメラキャリブレーション」長谷川博幸(ジオネット)
「4D-IMADAS-GGRFとUAVカメラキャリブレーション」長谷川博幸(ジオネット) 「ドローンを利用した森林樹冠計測」小野田雄介(京都大学)
「ドローンを利用した森林樹冠計測」小野田雄介(京都大学) 「3Dモデリングで測る植物の成長」淺野悟史(地球研)
「3Dモデリングで測る植物の成長」淺野悟史(地球研) 「多様化するリモートセンシングデータの有効活用と現状の検討課題」山下浩二(Exelis VIS)
「多様化するリモートセンシングデータの有効活用と現状の検討課題」山下浩二(Exelis VIS) 「ドローンはなぜ落ちる?50の墜落事例からみた6つの理由」益田 岳(京都大学)
「ドローンはなぜ落ちる?50の墜落事例からみた6つの理由」益田 岳(京都大学)
- 16:15
- なぜドローンを使う必要があるのか。ドローンを使わなくてもいいのでは。
- ドローンの普及とカメラの性能向上により、写真測量のコストは下がった。技術的な敷居は確実に下がっている。逆に、なぜドローンを使わないのかと問いたい。
- ドローンは観測の実用にたえるようになった。これまで実現できなかった高分解能と高度で、鳥の視点で、自由な観測ができるようになった。
- 現場で多くの人が使えることが重要。
- 農業にドローンを使って、リアルタイムでモニタリングを実施したい。
- 墜落事故やいたずら事件が増えているので、倫理と安全面が課題。
- Google EarthとQuickbirdのインパクトがあったのが2005年頃。リモートセンシングも技術の敷居が下がり、現場で多くの人が使えるようになってきた。
- 村の地図を作るのは、フィールドワークに決定的に重要。
- 人に関わる情報は、フィールドワークでしか得られない。
- 地図を読むには、リテラシーが必要である。
- ビジュアルデータマイニングは、コミュニケーションツールとして使える。
- データは共有するのが大事である。
- 17:00
趣旨説明「リモートセンシングってなに?ドローンってなに?」近藤康久(地球研)
事例報告1「ドローンと衛星を活用した地球観測の可能性」渡辺一生×Exelis VIS
この2,3年の間に、ドローン(小型無人機)が様々な分野で急速に利用されるようになりました。今後、地球観測の分野では、中・高解像度の衛星画像を用いた広域な空間把握と、超高解像度のドローンを用いた局所的な空間把握とを組み合わせた観測システムの構築が進むと考えられています。本報告では、ドローンを用いた地球研の3次元モデルの作成を事例にしながら、ALOS-2などの最新の地球観測衛星とのベストミックスについて考えてみました。
事例報告2「全球時系列衛星画像アーカイブを使ってみる」小寺昭彦(地球研)
もしも誰もが気軽に衛星リモートセンシングと可視化技術を利用できるようになれば、今まで見たかったもの、見えてなかったものが、これまで以上に見えるようになるかもしれません。今回は、そういった活用を目指して作成された、全球時系列画像アーカイブと、研究・調査シーンにおける様々な活用事例、そして「水土の知」プロジェクトの現場での新しい試みについてお話ししました。
休憩
全体討論「リモートセンシングとドローン、地球環境研究にどう使う?」
司会:近藤康久(地球研)
全体討論では、無人航空機(ドローン)とリモートセンシングの地球環境学、特にフィールドワークへの応用について活発な意見交換が行われました。以下にその要約を記します。
無人航空機について
リモートセンシングについて
(文責:近藤康久)
終了