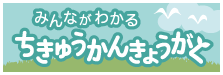ジル・クレマン
1943年生まれ。庭師、修景家(ランドスケープ・デザイナー)、小説家など、数多くの肩書きをもつ。植物にとどまらず生物についての造詣も深く、カメルーン北部で蛾の新種(Bunaeopsis clementi)を発見している。庭に植物の動きをとり入れ、その変化と多様性を重視する手法はきわめて特異なもの。代表的な庭・公園に、アンドレ・シトロエン公園(パリ、1986-98年)、アンリ・マティス公園(リール、1990-95年)、レイヨルの園(レイヨル=カナデル=シュル=メール、1989-1994年)などがある。おもな著作として、庭園論に『動いている庭』(1991年)、『惑星という庭』(1999年)、『第三風景宣言』(2004年)、小説に『トマと旅人』(1997年)ほか。
2月23日 地球研で開催された講演会「地球という庭」の様子。(撮影:和出伸一)
ごあいさつ
自然と文化の関係ほどわかりやすく、わかりにくいものはない。いったい何が自然で何が文化なのか?
この問いに、庭師という立場からアプローチしているのがジル・クレマンだ。フランスといういわば庭園の本場で庭を作りながら、その庭は決して一般に思われている庭園ではない。
クレマンは、パリのアンドレ・シトロエン公園の庭やケ・ブランリー美術館の庭の作成で知られ、同時に、その作庭の背景にある思想が注目を浴びてきたが、これまで来日の機会がなかった。初来日となる今回、3回の連続講演・シンポジウムを企画した。それぞれ彼の中心的な概念である「動いている庭」「惑星という庭」「第三風景」をめぐるものだ。
たとえば、「動いている庭」。そこでは、草や木が自然の遷移の作用として移動し、その移動のダイナミズムの中での庭が再構成される。それは自然なのか、文化なのか? 庭の再構成は,従来の自然と文化を截然と切り離す二分法に基づく思考の再構成を促す。
地球環境を考えることとは、自然と文化の関係を考えることでもある。初来日するクレマンの京都と東京での連続公演を通じて、新たな地球環境への視座が開かれるはずだ。
- 連続講演会
- Ⅰ. 都市のビオロジー
- Ⅱ. 地球という庭
- Ⅲ. 庭のかたちが生まれるとき
2015年2月21日(土)16:00 - 18:00
日仏会館 1階ホール(⇒アクセス)
講演:ジル・クレマン
パネリスト:山内朋樹(関西大学)
司会:シルヴィ・ブロッソ(早稲田大学)(撮影:エマニュエル・マレス)
都市にも植物の空間――庭や公園、寺社仏閣の敷地――はある。けれども、空き地や放棄地、線路脇にも、世界中の植物が混ざりあう奇妙な植生が人知れず息づいている。クレマンのいう「第三風景」とは、こうした土地の名だ。人間が意識しない見捨てられた空間だからこそ、そこはさまざまな生物にとっての保護区にもなっている。この散在する多様性の避難所をひとつの風景として見なおすとき、都市のありようは異なるものへと変わってしまうだろう。
2015年2月23日(月)13:00 - 17:00
総合地球環境学研究所 講演室(⇒アクセス)
講演:ジル・クレマン
パネリスト:篠原徹(滋賀県立琵琶湖博物館館長)、村松伸(地球研教授)
司会:寺田匡宏(地球研特任准教授)、エマニュエル・マレス(地球研研究支援員)(撮影:和出伸一)
「この惑星は、庭とみなすことができる」――庭も地球も、一方は土地の境界に、他方は生物圏という薄い皮膜に包まれた有限な空間であり、その囲まれた土地のなかに「最良のもの」が集められている。庭に蒐集された異国の珍しい花々、薬草、果実、そして地球に凝縮されたおびただしい生物種とその多様性。この惑星を庭とみなすことで、ひいては人類を庭師とみなすことで、クレマンは激変する現在の地球環境をめぐって、新たな思想を紡いでいく。
2015年2月27日(金)18:00 - 20:00
アンスティチュ・フランセ関西-京都 稲畑ホール(⇒アクセス)
講演:ジル・クレマン
パネリスト:田瀬理夫(プランタゴ代表)
司会:山内朋樹(関西大学)(撮影:エマニュエル・マレス)
植物ーーーとりわけ一年草や二年草ーーーが転々と移動し、かたちを結んでは、ほどけていく。ジル・クレマンが荒れ地や放棄地の植生から着想した「動いている庭」では、植物、動物、庭師、来園者、それらをとりまく環境といったさまざまな要素の動きが交錯し、そのなかから庭のかたちが生まれてくる。こうしたクレマンの姿勢と実践は、庭やランドスケープ・デザインにとどまらず、広くこれからのものづくりのあり方を照らしているだろう。
- 企 画
- 寺田匡宏(地球研)、エマニュエル・マレス(地球研)、
山内朋樹(関西大学)、小川純子(みすず書房) - デザイン
- 和出伸一(地球研)
- ビデオ
- 澤崎賢一、矢野原佑史
- 主催・共催
- お問い合わせ先
- 総合地球環境学研究所 コミュニケーション部門
エマニュエル・マレス
■□■ PDF ■□■