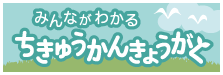2019年12月22日、滋賀県立琵琶湖博物館にて第30回地球研地域連携セミナー「『楽しさ』がつなぐ森里川湖 ~身近な環境 守る楽しみ つながる喜び~」を開催しました。
基調講演では、三橋 弘宗先生(兵庫県立 人と自然の博物館 主任研究員 兼 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 講師)に「小さな自然再生の大きな役割」と題し、ご講演いただきました。講演では、大規模な公共事業をしなくても、生態系の仕組みを良く知ることで、少ない資金でも地域の人々や行政と水辺の生態系保全にとりくめる戦術を、事例を交えて紹介されました。
次に、地球研の栄養循環プロジェクトのメンバーである岩田 智也先生(山梨大学 准教授)より、「鳥の眼から見た野洲川流域の生物多様性と栄養循環」と題し、話題提供が行われました。あらゆる生物にとって重要な栄養素であるリンの起源を、安定同位体分析を用いて調査した結果や、土地の利用と底生生物の関係などの報告がなされました。
その後の流域の活動紹介では、
- 甲賀木の駅・大久保里山再生委員会・SATOYAMA+の中島 教芳さん
- 小佐治環境保全部会の一宮 義男さん
- 湖南流域環境保全協議会の桐畑 孝佑さん
- 杣川(そまがわ)と親しむ会の森嶋 克巳さんと滋賀県立甲南高等学校の生徒さん
総合討論では、栄養循環プロジェクトにも参画いただいている脇田 健一先生(龍谷大学教授)と佐藤祐一さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター専門研究員)をコーディネーターとして、流域で活動されている皆様と更に意見交換をいたしました。
登壇者からは、見る、知る、食べる、などの日常生活の中からささやかながらも楽しさが生まれたり、目に見える形にすることで感動を覚えたりするこという意見が出されました。今回のセミナーのキーワードは「楽しさ」で、まさにこの「楽しさ」を生み出す知恵やアイデアをお互いに知ることができました。またその楽しさが人から人へつながり、活動が盛んになることで、乱開発の抑止力にもなっているということも確認できました。
当日は95名の来場者がありました。寒い中お越しくださった皆様、ありがとうございました。栄養循環プロジェクトは5年間の研究期間(2015年度~2019年度)を終えようとしておりますが、これまでの活動が野洲川流域の交流や、上流と下流の環境の違いを理解することにつながっていけばと思います。
■当日の様子
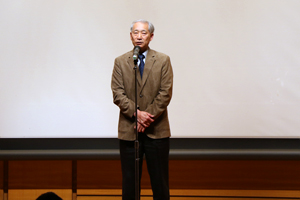
高橋啓一 琵琶湖博物館長による開会挨拶

奥田昇 地球研准教授による趣旨説明

三橋弘宗先生による基調講演

岩田智也先生による話題提供

総合討論の様子

安成哲三 地球研所長による閉会挨拶
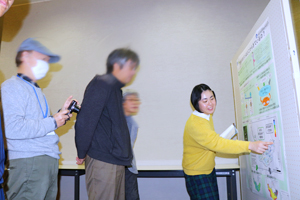
ロビーで行われたポスター展示の様子