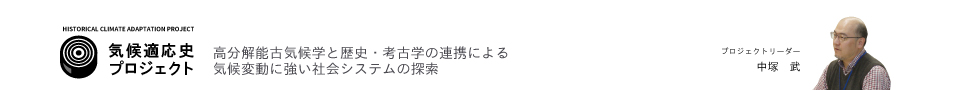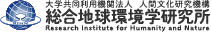- HOME
- > PUBLICATIONS
PUBLICATIONS
出版物
気候適応史プロジェクトでの成果をまとめた報告書などを掲載しています。
成果本
気候変動から読みなおす日本史(仮) 臨川書店より刊行予定
成果本「気候変動から読みなおす日本史(仮)」・・・2019年刊行予定
- 第1巻 新しい気候観と日本史の新たな可能性(仮)
- 第2巻 古気候の復元と年代論の構築(仮)
- 第3巻 先史・古代の気候と社会変化(仮)
- 第4巻 気候変動と中世社会(仮)
- 第5巻 気候変動から近世をみなおす―数量・システム・技術(仮)
- 第6巻 近世の列島を俯瞰する―南から北へ(仮)
成果報告書
成果報告書1
WORKING PAPERS 1
- 2014年度 気候適応史プロジェクトの活動について 中塚 武
- 2014年度 古気候学グループ・気候学グループの活動 佐野雅規
- 2014年度 先史・古代史グループの活動 村上由美子
- 2014年度 中世史グループの活動 伊藤啓介
- 2014年度 近世史グループの活動 鎌谷かおる
- 気候の変動に対する社会の応答をどのように解析するのか?―新しい形での文理融合を目指した統計学的アプローチ― 中塚 武
- 石垣島の化石サンゴ年輪による9~12世紀の海洋環境復元 阿部 理・森本真紀・浅海竜司
- 伊勢神宮スギ年輪の炭素14年代測定(AD1540~AD1990) 坂本 稔
- 年輪セルロース酸素同位体比の年層内変動データを用いた年代照合の可能性に関する検討 庄 建治朗
- 藤木久志『日本中世災害史年表稿』を利用した気候変動と災害史料の関係の検討―「大飢饉」の時期を中心に― 伊藤啓介
- 東北地方における名子制度・刈分小作と凶作・飢饉―1930~70年代の研究史を読み直す― 菊池勇夫
- 江戸時代の災害文化を考える―弘化3年(1846)江戸水害の避難者名簿から― 渡辺浩一
成果報告書2
WORKING PAPERS 2
- 2015年度 気候適応史プロジェクトの活動について 中塚 武
- 2015年度 古気候学グループ・気候学グループの活動 佐野雅規
- 2015年度 先史・古代史グループの活動 中塚 武
- 2015年度 中世史グループの活動 伊藤啓介
- 2015年度 近世史グループの活動 鎌谷かおる
- 琉球列島の造礁サンゴ年輪を用いた海洋表層の長期塩分変動の復元
阿部 理・浅海竜司・高柳栄子・森本真紀・小林文恵・平井 彰・福留綾里紗・井龍康文 - 気候変動データと『日本書紀』の記載 生田敦司
- 工具鉄器化の時期をさぐる―年輪酸素同位体比年代測定の応用例として― 村上由美子
- 磯貝富士男氏の業績と初期中世の気候変動に関する覚書 田村憲美
- 書評 水野章二著『里山の成立―中世の環境と資源―』 伊藤啓介
- 東北地方における名子制度・刈分小作と凶作・飢饉―1930~70年代の研究史を読み直す― 菊池勇夫
- Climate Change, Human History, and Resilience in Premodern Japan:
A Brief Survey of the Existing English-Language Literature,
with Implications for the Publication of Research Results
from the “Historical Climate Adaptation Project” Bruce L. Batten
リーフレット
ポスター
もみあげ将軍大ピンチ!室町時代のきんきのききん
もみあげ将軍大ピンチ!室町時代のきんきのききん
2016年度地球研オープンハウスで使用したポスターです。室町時代の人びとが、飢饉に対してどのように対応したか説明しています。
地域連携セミナー要旨集
地域連携セミナー(大阪)要旨集
地域連携セミナー(大阪)要旨集
- 日本史の背後にある気候変動の概観 中塚 武
- 弥生時代から古墳時代へのムラの変化と気候変動 -淀川流域を対象として- 若林邦彦
- 河内平野における水田稲作の展開と気候変動 -弥生時代から中世まで- 井上智博
- 近世における淀川水系の水害と地域社会 鎌谷かおる
- 米切手相場と気候変動の関係 -堂島米市場を舞台として- 高槻泰郎
2018年12月16日(日)に、大阪歴史博物館で行なわれた地域連携セミナー(大阪)の要旨集です。