第11回 地球研フォーラム
「“つながり”を創る」
が開催されました
7月8日(日)、国立京都国際会館において第11回地球研フォーラムが開催され、170名を超える参加者が集まりました。今回のテーマは「“つながり”を創る」です。これまでの地球研フォーラムでは、研究プロジェクト成果を反映させながらテーマを設定してきました。今回の地球研フォーラムで「つながり」をとりあげた理由は2つあります。1つは、東日本大震災以来、「つながり」の重要性が広く認識されてきたことです。被災地域には日本だけではなく世界の多くの人々から有形無形の支援が寄せられています。それまで被災地域とは縁がなかった人々、縁が薄かった人々も震災・復興をきっかけに新たな「つながり」が作られはじめています。2つめは、地球研の研究プロジェクト運営方法に関係しています。地球研では、すべて任期制のもとスタッフが集まり、定められた期間において研究を進め、プロジェクト終了後には他の機関へ移っていきます。これまで地球研に在籍した人数はのべ1万人にも及びます。震災という未曽有の危機を迎えるなか、地球研の流動的な特徴を生かしながら、研究者同士のつながり、研究組織、企業、行政との「つながり」をどのように構築していけるのかを議論することが、今回の地球研フォーラムの狙いであったのです。そして今回の地球研フォーラムの準備段階において、新たな試みとして、地球研内でプレ・フォーラムを開催してスタッフ間の議論を深めてきました。
縄田浩志准教授(総合地球環境学研究所)による趣旨説明のあと4名の講師が「つながり」をキーワードに話題を提供しました。
「自然派企業」として知られるサラヤ株式会社の更家悠介代表取締役社長からは、企業の環境問題に対する取り組みをお話しいただきました。そこでは顧客だけではなく、原料生産やそれを取り巻く環境にも配慮することの重要性が強調され、さらに最近取り組みはじめたアフリカ、ウガンダにおける「手洗い運動」も紹介されました。
震災被害からの復興に尽力する碇川豊大槌町長からは、壊滅的被害を受けた大槌町の住民主体の復興プランが示されました。防潮堤の高さの問題、地域資源を生かした今後の計画案、どれもが地域の人々との「つながり」に基礎づけられたものですが、それを実現するまでの困難な道のりも紹介されました。
学問分野の枠を超え、超領域的な知と方法づくりに取り組み続ける井関利明名誉教授(慶應義塾大学)は、環境企業の取り組み、震災復興を踏まえながら、人やモノの関係こそが第一義的な意味を持つという「関係主義」の視点が紹介されました。これまでのモノ中心のネットワークではなく、「関係」に重点を置きそこから発展する「つながり」を考えることの重要性が指摘されました。
阿部健一教授(総合地球環境学研究所)からは、地球研がこれまで取り組んできた文理融合、学際的研究を超えて、企業や行政といった社会のさまざまな「専門家」との協働が地球環境問題の解決に重要であることが指摘されました。
講演に続くパネルディスカッションでは、上記4名の講演者に加えて窪田順平教授(総合地球環境学研究所)、石山俊プロジェクト研究員(総合地球環境学研究所)、さらには、会場のサラヤ株式会社若手社員や大槌町役場職員を交え、それぞれの「つながりへの思い」を披露しつつ「異業種間」の今後の協働のあり方が議論されました。 (総合地球環境学研究所研究員 石山 俊)



写真左から、立本成文 地球研所長挨拶、縄田浩志 地球研准教授、更家悠介 サラヤ株式会社代表取締役社長

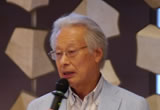

写真左から、碇川豊 岩手県大槌町町長、井関利明 慶應義塾大学名誉教授、阿部健一 地球研教授



写真左から、窪田順平 地球研教授、石山俊 地球研プロジェクト研究員、ディスカッションの様子

会場の様子