連載
晴れときどき書評
このコーナーでは、地球環境学にかかわる注目すべき本、おすすめの本、古典などを幅広く取り上げて紹介します。
王 智弘(外来研究員)
小さく暮らして、大きくつながる
『やま・かわ・うみの知をつなぐ──東北における在来知と環境教育の現在』
羽生淳子・佐々木剛・福永真弓編著
東海大学出版部、2018年
A5判、306ページ
本体2,700円+税
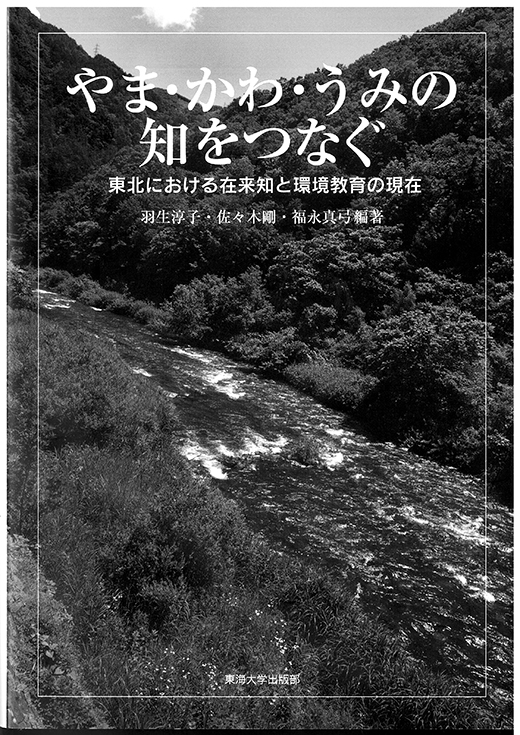
あたりまえのように過ごしている平穏な日常や便利な生活基盤が、どのような自然・社会環境の上に成り立っているのか。甚大な災害や気候変動への対応から、模索がつづく社会のあり方について、本書は「在来知」、「環境教育」、「レジリエンス」をキーワードに検討する。その土地で暮らす人びとが培ってきた知識や知恵に価値を認め、これを科学知とともに次世代に継承することで、自然環境の異変や災害に強い社会をめざす。考古学や人類学、教育学、社会学の研究者らを中心とする学際的研究チームが、復興の途にある岩手県宮古市や福島県をフィールドに、地域住民と取り組んだ実践の記録を紹介する。
スモール・イズ・レジリエント
本書が災害への備えを見て取ろうとする北上山地の山村は、産業別人口に占める第一次産業の割合が5%に満たず、人口の半数以上が都市部に暮らす日本において、多くの読者には発見に満ちた世界だ。平坦な土地が少ないうえに、ヤマセによる冷害で知られる自然環境のなかで、聞き取りや史料から明らかにされるのは「小規模で多様」な生業と食を蓄える知恵である。第二次世界大戦後に水田稲作が本格化するまでは、畑地での「二年三毛作」による複数の主食(ヒエやムギ、アワ、大豆)の栽培のほかに、クリやクルミ、トチ、山菜やキノコといった林産物の採集、それに現金収入源となる養蚕や畜産など、複数の生業に労力を配分する暮らしが営まれていた。
飢饉や災害に備えるための意識的な、あるいは長い時を経て習慣になった行為を事例に論じられるのが「レジリエンス」の概念である。レジリエンスとは、本書のことばを借りると「天災や人災に対するコミュニティの弾力性や、災害などから回復する力」を意味する。水田単作を例にとるとわかりやすい。単一作物の栽培に労力や時間のぜんぶを割り当てることは、作業効率や収量の点では優れている。しかし、まれにでも凶作となれば命取りである。単純な生産規模の大きさに目を奪われると、不都合な環境の変化に備える山村の知恵が見過ごされてしまう。一つひとつの生産性は小さくても、多様な生業で周年サイクル全体を組み立てる戦略に、本書はレジリエンスを理解するための鍵を見る。
山村の食を支える女性の存在
凶作や飢饉への備えには、生産面の工夫だけでなく、蓄える技術も不可欠である。寒風にさらしてつくる凍み豆腐や凍み大根は在来知の結晶といえる。過去には茅葺屋根の天井からドングリを詰めた「かます」が発見されたという貯蔵の習慣は、今日、ストッカー(大型冷蔵庫)の高い保有率に受け継がれている。冷蔵庫を開くと、そこは環境が育んだ食文化と災害に備える意識の高さを垣間見せるフィールドとなる。食べるという日常の行為から捉えた、山村における自然との関係は、都市部の暮らしがめざす環境に負荷をかけない生活様式にはない迫力を感じさせる。
食に注目する本書には多くの女性が登場する。書中には、著者たちをもてなした食卓、手づくりの食材や収穫物をうれしそうに手にする女性の姿など、数葉の写真も掲載されている。日々の料理はもちろん、農業や産地直売所の運営、さらには食文化の継承に活躍する女性の存在が目をひく。数年をかけてキビの育種・選抜をした「おばあ」には驚かされる。食をめぐる在来知や、社会ネットワークの維持につながる日々の実践が、レジリエンスの基盤をつくるのだ。
地図から心象風景へ
コミュニティということばから連想する小集団の在来知を基礎に、山川海をふくむ流域社会の拡がりのなかでレジリエンスを捉えようとする本書では、「今ここ」の環境に縛られがちな人間の想像力を拡げる二つの実践例が報告されている。「閉伊川サクラマスMANABIプロジェクト」は、夏に海に下り、春に遡上するサケ科のサクラマス(陸封型がヤマメ)の生活史を教材とする環境教育活動である。その知識が、宮古市のサーモンランド宣言の一節、「鮭のごとく力強く活動するまち」に表れる比喩の精神と結びつくことで、定住を選んだ人間にも流域で生きるサケと同じ環境認識が可能になるのだろう。
他方、閉伊川を下った宮古湾沿岸の藤原・磯鶏地区で制作された「記憶の絵解き地図」では、1948年と1977年の空中写真を呼び水に、著者らによって聞き取られた場所にまつわる記憶が沿岸上空から眺めた鳥瞰図絵に記載されている。見慣れた天気予報図のように鉛直方向から眺めた地図とのちがいは明白だ。山川海のつながりを意識するには、隣接する領域がないがごとく行政区画で切り出された地図ではなく、遠景に描かれた山向こうにも世界の存在を暗示する鳥瞰図がふさわしい。一人ひとりの記憶が重ねられた鳥瞰絵図が、世代や空間の広がりのなかで心象風景を思い出すよすがを与えてくれる。
規模や経済の論理、あるいは平地の論理以外の選択肢として、やま・かわ・うみと暮らしてきた人びとの、これからも暮らしつづけるための論理を本書は提示する。教育やシンボル、地図の再検討は、これまでの社会を組み立てていた根本的な要素を見直す作業でもある。しなやかに自然環境の変化を生きる共同体像の模索が東北の地で始まっている。