特集1
インタビュー
地球環境学と国際学術出版の未来
話し手●アントワーン・ブーケ(シュプリンガー・ネイチャー日本法人代表取締役社長)
聞き手●ダニエル・ナイルズ(准教授)
翻訳・報告●小林邦彦(プログラム研究員)+ 押海圭一(特任専門職員)+ 王 智弘(外来研究員)
2018年4月に、地球研では国際的な発信の強化を目的に、国際出版室を立ち上げ、国際ジャーナル『グローバル・サステイナビリティ(Global Sustainability)』の編集などに参画している。地球研の成果は、これまでにも英文学術叢書Global Environmental Studiesシリーズとして刊行してきた。国際出版室を設置したいま、情報技術の利用やオープンアクセスの普及が進む出版界で、研究成果をどのように世界に届けるのか。学術出版界をリードするシュプリンガー・ネイチャー日本法人のアントワーン・ブーケ代表取締役社長を訪ね、学際研究と学術出版の未来を語っていただいた
ダニエル●シュプリンガー*1とネイチャー・パブリッシング・グループ(以下、ネイチャー)*2は2015年に合併しました。ブーケさんはどちらの会社にいらしたのですか。
ブーケ●ネイチャーに2001年に入社し、2012年にマネージング・ディレクターとして就任し、3年前からシュプリンガー・ネイチャーとして活動する日本法人の代表を務めています。
175年の歴史をもつ2社の合併
ダニエル●シュプリンガー・ネイチャーという社名を耳にしたのは最近の印象ですが、合併の動きはかなり前から進んでいたのですね。
ブーケ●そのとおりです。すでに多くの部門は統合しましたが、社内にはまだそれぞれのビジネスを軸とする部門、たとえばシュプリンガーの雑誌と書籍事業を担うグループや、おもにネイチャー関連の雑誌を扱うグループなどが混在します。しかし、175年の歴史をもつ2社が合併するのですから、3年は短いくらいでしょう。
ダニエル●2社のビジネスにはどんなちがいがあるのですか。
ブーケ●大きなちがいは書籍です。シュプリンガーは学術書出版の最大手の一つですが、ネイチャーは書籍を扱っていません。
ダニエル●オープンアクセスへの取り組みについてはいかがですか。
ブーケ●両社ともその先駆者で、合併後はより力を入れるようになりました。たとえば、シュプリンガーは早くからBMC(旧Biomed Central、バイオメド・セントラル)を買収していますし、ネイチャーにはScientific ReportsやNature Communicationsなどのオープンアクセスのジャーナルがあります。このように、2社のあいだには多くの共通点があったので、合併をことさら意識することはありませんでした。顧客のなかには、一つの会社のなかに、シュプリンガーとネイチャーがそれぞれ独立していると思っている方も多いのですが、そうではありません。私たちは多くの価値観を共有しています。
研究サイクルの一部として発見を促進する
ダニエル●この10年から20年のあいだに生じた学術出版界の劇的な動きや、知識を生み出すプロセスやパターンの変化についてはどのように捉えていますか。
ブーケ●私もかつては科学者だったのでわかるのですが、科学者の多くは出版のプロセスについて知識や関心がほとんどなかったと思います。出版と研究とはそれぞれ別の世界で、研究のあとに出版物がつづき、出版物の内容をふまえて次の研究に着手する。
ダニエル●それが一般的な認識だと思います。
ブーケ●私たちは、出版社も知識の発展を促進するサイクルの一部だと考えています。従来の考え方からすれば、出版社が関与するのは、投稿された論文を査読し、受理し、出版・頒布することであり、おそらく研究サイクルの3分の1、4分の1にすぎないと思われがちです。けれども、シュプリンガー・ネイチャーがめざす役割は、それだけではありません。私たちの事業は、知識生産のサイクルのすべての部分で研究者に影響を与えます。
多様な手段を用いてひらめきを探そうとする研究者にとっては、そのすべてが発見のプロセスです。私たちは、より優れた研究者になるよう支援もしているのです。私たちは、ネイチャー・マスタークラス(Nature
Masterclasses)やネイチャー・リサーチ・アカデミー(Nature Research
Academies)の活動を通じて、より優れた研究を行なうためのツールを提供したり、翻訳サービスや、論文執筆のためのライティング講座などのサービスも提供したりしています。私たちも知識生産サイクルの一部なのです。
ダニエル●興味深い側面ですね。
ブーケ●ネイチャーではオープン・ピア・レビューなど、査読システムについて多くの実験をしています。また、論文の背後にある研究データにかんたんにアクセスできるように、業界全体をリードする取り組みに尽力してきました。論文をより価値あるものにし、科学の発展を加速するのです。
ダニエル●それが、シュプリンガー・ネイチャーが追求する価値なのですね。
ブーケ●そうです。私たちはこれを「知識の発展(Advancing discovery)」と表現しています。それが私たちの提供している価値なのです。出版と研究のサイクルにおいて、オンライン出版や発信はもちろん、対価が支払われない隠れた仕事もふくめて、そのすべてが私たちの役割なのです。
オープンアクセス化のインパクト
ダニエル●知識生産のプロセス、あるいは、科学の発展において、出版社がじつに多面的な役割を果たしていることはわかりました。では、オープンアクセスのながれは、出版社のビジネスモデルに、あるいは科学全体にどのような変化をもたらすのでしょうか。
ブーケ●私たちは合併前の早い時期からオープンアクセスの出版をリードする存在でした。事実、いまではオープンアクセスの分野では最大規模の出版社であり、出版論文の3割がオープンアクセスです。2017年の1年間で、9万以上のオープンアクセス論文を出版しました。
ダニエル●その数字のインパクトはどう評価すればよいのでしょう。
ブーケ●じつのところ、数字は重要ではありません。ほとんどの著者や研究者にとって、オープンアクセスか否かは、ジャーナルを選択するさいの重要な判断材料にはならないでしょう。重要なのはジャーナルの出版目的、評判や読者などです。論文の内容と読者の求める情報がマッチしていないと論文は世に知られません。その判断の先に、オープンアクセスであるかが問題になるのですが、オープンアクセスが資金提供団体の条件である場合、出版に係る掲載料の問題で選択できない著者も多いのは事実です。それから、オープンアクセスが増えることで、図書館の役割も変わってきます。
ダニエル●オープンアクセスをめぐる論点の一つですね。
ブーケ●私たちは、オープンアクセスも、そうではないビジネスモデルもそれぞれに妥当性があると考えています。掲載する論文の選定が問題にならないジャーナル、メガジャーナル*3とよばれる媒体には、オープンアクセスが有力なビジネスモデルになります。
ダニエル●「選定が問題とならない」とはどういう意味ですか。
ブーケ●たとえば、Scientific
Reportsは、論文のインパクトよりも科学的妥当性を重視して掲載します。幅広い分野を対象とする傾向があり、学際的な研究論文が掲載されやすい。オープンアクセスはそのようなメガジャーナルに適しています。メガジャーナルのビジネスモデルが論文の掲載本数を奨励しているからです。
いっぽうで、たとえば、学会が出版する多くのジャーナルは、高度に専門化しているため、対象分野や論文の質、インパクトがより重要です。このような場合、出版業界内での競争と市場の確保のためには、掲載する論文数よりもそれぞれのジャーナルが扱う分野に該当する論文を選定することがだいじにされます。
ダニエル●そういった意味で、オープンアクセスは「選定」が問題にならないのですね。そのなかでシュプリンガー・ネイチャーの立ち位置は……。
ブーケ●私たちは、幅広いニーズに応える必要があると強く感じています。オープンアクセスはその一部を満たすもので、近年、そのニーズはますます高まっています。同時に、オープンアクセスが適さないジャーナルやコミュニティの需要に応えることも重要です。ですから、私たちは100%オープンアクセスをめざしているわけではありません。
ダニエル●オープンアクセス化が進む現状を好ましいとお考えでしょうか。
ブーケ●オープンアクセスの善し悪しについて、私たちは不可知論者なのです。ただ、人びとがそれを求めるのであれば、私たちはそれに応えたいと考えています。
多様化する学術出版メディア
ダニエル●今後、学術出版はどのように変化してゆくのでしょうか。
ブーケ●20年後には、オープンアクセスは主流になっているでしょう。ただし、ここで問われるべきはビジネスモデルではありません。研究論文が現在と同じものであるかどうかが重要な視点です。研究論文は時代によって形を変えるものです。近代の研究論文の形式は、第二次世界大戦前後につくられました。17、18世紀にさかのぼれば、研究者のあいだで交わされたレターが研究論文として出版された時代もありました。
ダニエル●興味深い指摘ですね。
ブーケ●近年はさらに、従来にはないタイプの記録も増えています。データの公表や引用可能なデータを備えることは、科学を記録する方法として欠かせないものになりつつあります。一般的に研究論文には結論があって、それが審査されるのですが、たとえば、BMC Research Notesで見られるような、研究者がこれから取り組もうとすることの記述もあれば、研究論文に必要な要件を満たさないプレプリントもあります。ソーシャルメディアに目を向けてみると、140文字のツイッターを記事として、そのリツイートを引用として定義できるでしょう。
ダニエル●メディアが今後さらに多様化する未来が見えてきますね。
ブーケ●記録や発信の形式よりも、むしろ、人びとがなにを読んでいるのか、なにが役にたつのかが重要な問題になるのです。さらに言えば、もうすでに、人だけが読み書きをする時代ではありません。発見とその共有のプロセスに機械技術や人工知能が介在しています。だからこそ、データマイニングがより一層重要になり、従来型の研究論文もそれに応じた形に変化するでしょう。
このながれは、論文の方法論のセクションや補足データに必要な要件、データを公開することを出版社が義務化していることなどに、すでに見られます。データマイニングが進めば、伝統的なジャーナルは、その動きをさらに加速するでしょう。こうした変革期に、私たちシュプリンガー・ネイチャーがどのように対応してゆくかは興味深いポイントです。理念と価値は基本的に変わらないと思いますが、いまは思いもつかない必要ななにかを提供しているかもしれません。
ダニエル●いっぽうで、書籍の出版はシュプリンガーの重要な役割です。たとえば、電子書籍については、どのようにお考えですか。
ブーケ●シュプリンガーは電子書籍出版の分野でもリードしています。本の執筆は雑誌論文の執筆とはかなり異なります。数百本の論文を書くような生産性の高い研究者でも、書籍は10冊も書けばすごいことですし、ほとんどの研究者は1冊でも書ければよいほうでしょう。研究者は書籍に雑誌論文とは異なる思い入れをもっていると感じます。ただし、読者はそうは感じません。読者が科学書に求めるのは、一般的な娯楽書にあるドラマチックな展開ではなく、必要な情報を迅速に得られるかどうかです。ですから、科学書は雑誌論文と活用方法が似てきているように思います。この変化への対応には、電子書籍のほうが優れています。
ダニエル●では、書籍は論文に近づくのでしょうか。
ブーケ●書籍には、ビデオコンテンツや、電子的な補助資料を入れるなど、雑誌論文にくらべて多様なタイプの情報を掲載できます。さらにレファレンス・ブックなどのコンテンツをリアルタイムに更新してゆく取り込みを始めています。
ダニエル●図書に関するもう一つの論点として、単著ではなく編書が増えていることが挙げられます。とくに電子書籍の編書には、本質的には中心となるものがありません。編書のかたちでの出版の意義は、どうお考えですか。
ブーケ●優れた編集者による、書籍の編集作業はとても重要だと考えています。もしその作業がなければ、書籍はただの寄せ集めになり、読者にとって有用なものにはならないでしょう。私たちの仕事は書籍を売ることですが、電子書籍がつかわれているかを検証するために、書籍そのもの、あるいは章ごとのダウンロード数や引用数を指標化してモニタリングしています。その結果、思った以上に引用されていることや、ジャーナルにくらべて引用される期間が長いことがわかってきました。
人類の課題に取り組む学際研究
ダニエル●話の印象から、シュプリンガー・ネイチャーは技術や科学に軸足を置いているようですが、それがこれからさきも関心の中心になりますか。
ブーケ●2社の合併によって、私たちの基盤はより幅広くなりました。私たちは人文・社会科学分野の学術出版社の大手でもあり、社会科学のジャーナルも発刊しています。明らかなことは、科学技術分野においても学際性が強まっている傾向です。
ダニエル●「学際性」は、環境問題をテーマとする地球研としても、その重要性を実感しています。
ブーケ●私たちは近年、新たなネイチャー関連誌として、サステイナビリティ、気候変動、エネルギー、人間行動学をテーマにしたジャーナルを創刊しました。いずれも、人類が挑戦すべき大きな課題だからです。
ダニエル●ネイチャー関連誌の拡充は印象的でした。
ブーケ●気候変動については、いまでも懐疑論が多くあります。Nature Climate Changeの発刊の目的は、気候変動を人類の現実の問題として認識すること、ネイチャー関連誌に加えることでその研究に社会的信用を与えることです。エネルギーやサステイナビリティに関するジャーナルも同様です。これらの新刊は、研究者をとりまく社会の実状に反応したものです。成果が見えにくい分野に社会的な注目を集めるのはとても困難ですが、ネイチャーのシリーズとして出版することで耳目を集めることができます。
ダニエル●明確なキーワードがジャーナルのタイトルに掲げられていることは、読者にはわかりやすいメッセージですね。
ブーケ●70年代から90年代にかけて発行されたジャーナルは、学問領域を第一に定義しましたが、ここ15年間に新たに発刊されたジャーナルはそうではありません。たとえば、ナノテクノロジーは学問領域ではなく、一定のサイズ以下のものを表す概念ですが、ナノテクノロジーという切り口でさまざまな科学分野の話ができます。雑誌のカテゴリーが変化し、新たに展開することは興味深い現象です。
ダニエル●出版事業を科学の発展と一体的に捉える視点と、オープンアクセスをめぐる認識は、学際研究である環境学の発信を考えるうえでとても参考になりました。環境問題に取り組むコミュニティにとって、地球研が社会に信頼される情報基盤であること、あるいは活躍の場を提供することの意義についても、あらためて認識することができました。きょうはありがとうございました。
〈2018年5月25日、シュプリンガー・ジャパンにて〉
*英語でのインタビュー内容をもとに日本語に翻訳・編集しています。
*1 シュプリンガー(Springer)は、1842年に設立されたドイツに本社を置く学術出版社。出版物のなかには、200人以上のノーベル賞受賞者の著作がふくまれる。(https://www.springer.com/gp/about-springer/media/press-releases/corporate/nobel-laureates-publish-their-research-at-springer/830716/
より)
*2 ネイチャー(Nature)は、1869年11月4日にイギリスで創刊された学術雑誌。論文の影響力を示す主要な指標の一つである「インパクトファクター」は、2017年時点に41.577で、総合科学誌として世界1位となっている。
*3 最初のメガジャーナルとして知られるPLOS
ONEの発行元PLOSの当時のCEO、ピーター・ビンフィールドによれば、メガジャーナルの定義は、年に1,000本以上の論文を掲載し、著者支払い型を採用し読者は無料で読めること、研究の重要性などを考慮した人為的な取捨選択を行なわないこと、広い分野を対象としていることとしている。(横井慶子「学術雑誌出版状況から見るオープンアクセスジャーナルの進展」2013年)

アントワーン・ブーケさん

ダニエル・ナイルズさん

棚からネイチャー誌を取り出し、説明するブーケさん
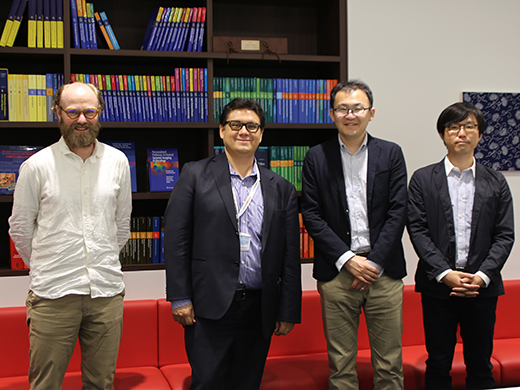
(左から)ダニエルさん、ブーケさん、小林さん、押海さん
アントワーン・ブーケ(Antoine BOCQUET)
オーストラリア生まれ。ブリスベンのグリフィス大学を卒業後、東京大学大学院に入学。1993年に、同大より理学博士(物理学)を取得。アジア太平洋地域の学術出版業界で20年以上の経験をもつ。現在、シュプリンガー・ネイチャーの日本、東南アジア、オセアニア地域を管轄するヴァイス・プレジデント・セールス。ネイチャー・ジャパン株式会社とシュプリンガー・ジャパン株式会社の代表取締役社長を務める。
おしうみ・けいいち
地球研IR室特任専門職員。専門は法学︎。2011年から地球研に在籍し、2015年7月より現職。地球研らしさをデータからみる方法を模索中。
こばやし・くにひこ
実践プログラム2「多様な資源の公正な利用と管理」の研究員。専門は生物多様性条約を中心とした国際環境法。環境省、岐阜大学での勤務を経て、2017年4月から地球研に在籍。
NILES, Daniel
専門は地理学。地球研研究基盤国際センター准教授。2008年から地球研に在籍。