特集4
座談会
エコヘルス研究の過去・現在・未来 「健康」の歴史をたどり、社会に活かす
話し手●ハイン・マレー(教授) + 蒋 宏偉(特任助教)
聞き手●三村 豊(センター研究推進員)
編集●三村 豊
「アジアにおける『エコヘルス』研究の新展開(略称・エコヘルスプロジェクト)」は、2016年にスタートして研究期間は6か年。人間文化研究機構が推進する「異分野融合による新領域の創出」をめざす広領域連携型基幹研究プロジェクトの一つである。機構を構成する総合地球環境学研究所、国文学研究資料館、国立民族学博物館が連携して実施している。「健康の概念」を問い直すエコヘルス研究の狙いと研究計画を、統括代表者のハイン・マレーさん、メンバーの蒋 宏偉さんにうかがった
三村●エコヘルス研究はかつて、地球研独自のプロジェクト「熱帯アジアの環境変化と感染症」として、門司和彦(現・長崎大学)さんを中心に2006年から2014年にかけて進められていましたね(『地球研ニュース』21号参照)。国際的な学術雑誌である『エコヘルス』によるエコヘルスの定義は、健康と生態系の接点における研究とプラクティス。ハインさんは、新しいこのプロジェクトでどういう研究をしようとされているのですか。
ハイン●実施したい研究はたくさんあります。まず、日本のエコヘルスの研究とその考え方、思想の歴史を解明したいですね。環境問題として取り上げられている公害問題では、当初は人体にどのような影響を及ぼしているのか。たとえば、どうして水俣病になるのか、その化学的メカニズムすらわからなかった。それをまず明らかにしようとしてきた。でも、学問の発展によってそういう狭い問題として捉えるのではなくて、もっと大きく生態系の全体の問題として考えるべきだ、という発想に少しずつ変わりましたね。
三村●人の健康を蝕む公害病とよばれるものが、日本の工業発展の陰で、いくつか発生しましたね。1950年代後半から70年代前半にかけての「水俣病」「第二水俣病」「四日市ぜんそく」「イタイイタイ病」が四大公害病とされました。
ハイン●ところが、水俣病にはかなり政治的な面もあって、研究したがらない研究者もいた。そこで、広い意味での「人間」と「生態系」と「健康」の問題を考えるようになった。じつは、エコヘルスというカタカナのことばをはじめてつかったのは日本人なのですよ。1979年ころのことです。英語でつかわれるようになるより、だいぶ早かったのです。
日本発のエコヘルス概念はどのように浸透したのか
三村●1970年代は、デニス・メドウズの『成長の限界』や「持続可能性」の議論も始まっていますね。環境問題を根本から考えないと人類に未来はない、そういう思潮が生まれるなど、ターニング・ポイントでした。そういうときに、日本でエコヘルスという考えが生まれたのは、どういう文脈からだったのでしょうか。
ハイン●いろいろあったと思いますが、環境問題への取り組みと関連して、公害と化学的なしくみ、薬学的分析などの研究も活発になりました。そのいっぽうで、公害とは直接には無縁のパプア・ニューギニアなどの閉鎖的で未開とよばれた地域や社会における健康問題にも関わるようになった。これは最終的に、蒋さんたちがしてきた人類生態学の分野に発展した。人間の集団としての健康問題、ようするに疫学的な観点での分析や、その発生を統計的に調べる研究だけでなくて、複雑な生態系の一部として理解しようとしてきた。
蒋●生態系のなかでの集団的な健康はどう守られるのかという話ですね。それがスタート地点だと考えられます。
エコヘルスということばを提案されたのは、鈴木庄亮先生でした。そういう流れのなかで健康を考えるときに、人間は社会的動物ですから、自然生態系だけでなくバイオ&ソーシャル・サイエンス的な側面もするべきだと。70年代半ばに入ってからはとくに、人間と環境のインタラクションを観察するために、なるべく外部の影響が少ない人間の生活生態系を研究するという理由で、パプア・ニューギニアなどの「閉鎖的集団」を対象に研究を展開してきたといえます。
三村●そうした流れの過程で、個人のヘルスとともに集団のエコヘルスを考えるというように、ヘルスからエコヘルスに変化したということでしょうか。
蒋●そう、ですからエコヘルスは基本的に複数の人、地域社会などの集団的健康を考える研究です。
ハイン●エコヘルスは個人の健康増進だけでなく、集団としての人間と自然との調和の話ですね。
健康の概念は文化を超えるのか
三村●地球研が主体的に担う役割と、ほかの研究機関と歩調をあわせて研究するむずかしさがあるように思います。エコヘルス研究では、集団として「健康」を捉え、それに6年をかけて取り組むとなると、ある種の哲学的な発想も必要かと思うのですが……。(笑)
蒋●最近よく思うのですが、私たちは健康について調べていると、健康という概念が医学者の考え方と少しちがっているように思えます。医学者は血液や触診などの指標を見て、「これはなになに病だ」と診断する。しかし、「健康とはなにか」とは、はっきり言えない。十人十色というように、文化的背景や人によって、あるいは同じ人でもちょっとしたことで答えは異なる。
三村●短期的に捉えるか、長期的な側面を捉えるかで異なるということですか。
蒋●そうですね、その人のライフコース(一生の道筋・人生の軌跡)によって、たとえば週末はよく食べられて健康的だとか、よく寝られるとかいうことがありますね。時間や状況が変わると、ちがう理解と答えが出てくるかもしれない。
ぼくの理解では、私たちがめざしているのは、アジアのちがう地域や文化的な背景のもとで人が健康をどう理解しているのかを調査し、それに歴史資料などを加味することで、「健康とはなにか」をあるていどあきらかにすること。そして、その過程で重要なポイント、共通する要素、項目を見いだすことかもしれない。
ライフコースを考えると視点も変わる
ハイン●じつは、地球研、民博(国立民族学博物館)、国文研(国文学研究資料館)の三つの組織が同じテーマのもとに、異なる出発点から研究をはじめたから、最初はそうとう広い枠組みを設置しました。つまり、「健康とはなにか」という課題からはじめた。予備研究(FS)の期間が2年ありましたから、そのFSの段階でいろいろな研究会を開きました。
最初の「健康とはなにか」は健康の定義だと捉えて、健康ということばについて研究しました。日本語や中国語、西洋の健康ということばは養生とどう関係するか、とかですね。すると、たくさんのことが発見できました。
たとえば、オランダ語や英語では、健康と健全の区別はかんたんではありません。そこから発展させて私は最近、エコヘルスや生態系の健全性についての問題、ワンヘルスやプラネタリーヘルスとの関係について、論文をまとめました。ことばの定義だけでなく、どんな意味かまで発展させて言及しないといけないからね。
人間は、生まれてから死ぬまで、自分の体といろいろな経験をします。それはつまり、すべてのライフコースにわたってよい友だちであるのか、あまりよくない友だちでいるのかということでもあります。しかも無意識にいろいろな健康的な概念をもって、自分の体とのつきあいを解釈・経験する。このこともとても重要ではないかと思うのですよ。
三村●ライフコースで考えると、死生観に関わってくるということでしょうか。
ハイン●ええ、議論はしているが具体的な研究までできていないですが、「死ぬことをどう捉えるか」という問題があります。死がないと生の意味はない、人生だとか生命だとかいうのは意味がないですね。死があってはじめて生というものができるのだからね。そこには、もしかしたら宗教的とか哲学的な意味あいの側面があるということです。
日本のように、とくに高齢化社会では最期の何年かは物理的な健康がそうとう衰えますね。平均寿命はだいぶ延びましたが、体になんらかの不自由が発生してから最期までの期間はあまり変わっていません。平均寿命や最期までの時期は統計的な研究でわかってしまうから、その結果を社会的にどう扱うかは、とても重要になると思います。ですから、三つか四つくらいの調査地を経験して、最期の時期の質を考える視点を磨くことは必要です。
もし、ラオスだけを研究すれば、高齢化とか死ぬことはあまり視野に入らないでしょう。死はどうでもよいことではないにしても、マラリアとか寄生虫と懸命に闘っているようなところだと、あまりフォーカスを当てないでしょうね。
だから、私自身が健康の意味の答えをすでにもっているわけではない。6年間にわたるこのプロジェクトで、少しずつ理解しようとしているところです。
地球研×民博×国文研の交流と学際研究
三村●民博と国文研との共同研究で、互いによい刺激となっていることがあれば教えていただけませんか。
ハイン●研究会を開くとなかなか楽しい議論になりますよ。2016年9月の研究会では、地球研がラオスと日本の話をしました。また、地球研のメンバーの福士由紀(首都大学東京)さんは歴史を担当しているから国文研との接点がやはり多い。歴史を担当するのは中国、韓国、日本の人たちで、地球研も国文研も似たようなメンバー構成です。
三村●国文研はおもにどのような研究ですか?
ハイン●国文研の研究者たちは、書物で歴史を研究している。歴史のなかのエコヘルスですね。最初は出版物を総覧して、どのような書籍がむかしに出版されたかレビューして、中国から日本に入ってきてどんな読者に向けて翻訳・出版されたのか、あるいは日本からなにが逆輸入されたかなどの見当をつけていました。そういう出版活動を検討すると、漢方や養生、たくさんのものが行き来していたことがわかります。
韓国では、19世紀に宣教師の役割が大きくなりますが、やはり宣教師なりの健康観を持ち込んでいますね。
私たちと異なる研究をしている人たちとの共通点を見つけて議論することは意味があるし、楽しいですね。
三村●国文研の強みである歴史資料の蓄積から、健康概念を歴史的に読み解くというのはずいぶん刺激的ですね。
民博が担当する「文明社会における食の布置」は、食がメインになるのですか。
ハイン●そうですね。これに応じて、私たちも食について考えるようになりました。(笑)中国の海南島での質問票調査には、「なにを食べているのか」、「なぜそれを食べるのか」という食事動機の調査 がふくまれています。「なぜそれを食べているのか」という質問は民博が提案した方法で、私たちも同様の質問をすることで国際比較ができます。このプロジェクトがなければしなかったことをする、そういうよい波及効果が生まれている例です。
蒋●国文研のメンバーは中国や日本の古い時代の医学書で、養生とか身体観に関わるものを研究されていて、地球研の歴史グループとの補完的な面がかなりあります。地球研がおもに対象とする年代は近代史だからです。
近代に入ってからの医療や養生などの話ですが、国文研はもうすこし時代が古い。たとえば、薬用植物等を研究する「本草学」は、江戸時代の日本にどう入って、当時の翻訳者はそれを日本スタイルにあわせてどのように訳したかなどを調べている。このプロジェクトを全体的に考えると、意義ある連携だと思いますね。
民博は人類学者のメンバーも加わっていて、国文研と同様に古典籍の研究をしている人もいて、同じ地域を対象に共通する調査ができるのではないかと、期待を膨らませています。食事動機の調査も、その一例です。食が健康の根本ですから、その意味では、民博とシェアできる領域がかなりあるように思っています。
ハイン●中国の医学史をされている人から、「未病 」という概念が紹介されました。健康と病気との中間的な状態が存在すること、中国の医師はそれを同定できたことが刺激的でしたね。発想がずいぶんちがうのだなと。とにかく、このような交流がないと、新しい発想は出てこない。
学問の開拓か、社会実装か
三村●エコヘルス研究のゴールは、研究のシーズを芽生えさせる、新しい学問を切り拓くことなのか、あるいは社会実装をめざすのか。ハインさんが考えるイメージはどのようなものですか。
ハイン●私は社会実装を強調しています。国際援助・開発の分野で健康と生態系との関係性を考えるときは、トランスディシプリン的発想です。研究は現実世界の問題解決に貢献すべきだというスタンスです。
三村●最良の実践モデルのようなものをお考えなのですか。
ハイン●国際的にヘルシー・シティ(健康都市)づくりの運動があって、ヨーロッパを中心に環境改善を推進する提案が1980年代後半にありました。WHO(世界保健機関)を中心に、健康づくり国際会議も開かれました。1986年の第1回会議では「健康づくりのためのオタワ憲章」も採択されて、そこでは都市に注目する指摘もありました。地球研でしているのはこれに似た文脈で、私たちの役割は、国文研と民博との共同研究をいかに統合するかです。
三村●ほかの機関と共同研究を進めるにあたり、社会実装の話はむずかしいのですか。
ハイン●フィールドに出る民族学や人類学は人に近い研究ではありますが、あまりそこに関与しない研究も多いですね。
90年代の終わりにエコヘルスの概念が出てきた当時から国際的にエコヘルス研究に取り組んでいる研究者らは、アクションリサーチに力を入れています。研究のための研究ではないと。
三村●エコヘルス研究が社会実装する一つの例が示せればよいですね。その具体的な対象地域や地域との連携については、どうお考えですか。
ハイン●いまは三か所で調査しています。長崎市の南の伊王島と中国の海南島、それにラオス。そういう地域の調査にむけて質問票の準備をしています。とくに食生活の質問票ですが、地域住民がみずからの生活領域がどういう地域なのか、通勤や仕事などの日常身体活動、社会経済発展レベルなどの要素もふくんだ質問票です。
私たちが調査しているラオスの農村は車が通れる道もない村で、焼畑農業で生計を立てています。ここでは、感染症対策と健康転換をどのように進めるかが研究課題です。日本は人口転換が進んでいますから、少子高齢化の問題が中心になりそうです。
私がまえから強調してきたのは、場を出発点に問題の発見と解決に取り組むことです。もちろん思考的な枠組みでは、エコヘルスとはなにかにつながります。しかし、抽象的には、地域研究とけっこう近い方法です。
(2017年6月6日 地球研にて)
エコヘルスの社会実装の一例
映像作品「Walkability in Urban EcoHealth: Megacity for Tropical Monsoon Region」から
オランダで発祥した「カー・フリー・デイ 」は、ジャカルタを中心にインドネシア国内で拡がりつつある。車やバイクに依存する社会から、「歩くことができる社会」へ。ジャカルタは交通渋滞が多く、事故などの危険性や熱帯モンスーン気候という条件から歩くことが困難な都市。そんななか、「カー・フリー・デイ」はNGOが主体となって、住民・行政を巻き込むようにしてはじまった運動である。そこには明確なメッセージがある。日々の健康と価値の転換、そして環境への配慮である。彼らにとっての「健康とはなにか」。本映像作品は「ヘルシー・シティー」へと鼓動するジャカルタのいまを記録したショートムービーだ。(三村 豊)
URL: https://youtu.be/91kRouDEQJo


おのおののペースで歩いたり、自転車に乗ったりと楽しんでいた。Selamat Datang Monument(歓迎の塔)周辺にて、2017年2月撮影

一般市民やNGO団体、研究者などさまざまな方に「健康とはなにか」について聞き取りを行なった。Research Center for Limnology-Indonesian Institute of Sciences (LIPI) にて、2017年2月撮影

「エコヘルス」研究の関連性についてのプロジェクト研究交流会のようす。地球研講演室にて、2017年9月撮影
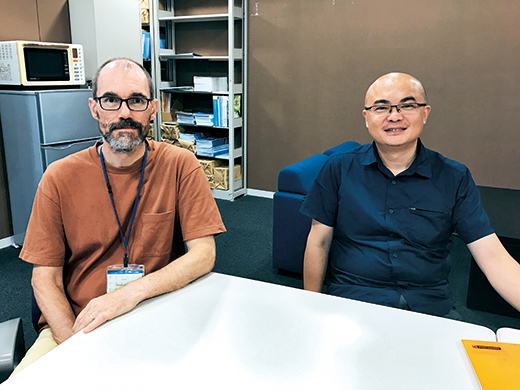
ハインさん(左)、蒋さん(右)
MALLEE, Hein
専門は社会科学。研究基盤国際センター教授。2013年から地球研に在籍。
じゃん・ほんうぇい
専門は人類生態学。研究基盤国際センター特任助教。2010年から地球研に在籍。
みむら・ゆたか
専門は建築・都市史、歴史GIS。2012年から地球研に在籍し、2016年から研究基盤国際センターセンター研究推進員。