わたしと地球研 ………… リーダーのまなざし ❺
このコーナーでは、地球研に在籍、もしくはかつて在籍していたプロジェクトリーダーが語り部となって、1枚の写真を手がかりに、自分の研究内容や将来の夢をひもときます。
社会に必要とされる生態学をめざして
奥田 昇 (地球研准教授)
私は、地球研の連携機関である京都大学生態学研究センター(生態研)から赴任してきた手前、専門を尋ねられたら、とりあえず「生態学」と答えるようにしている。しかし、自身のアイデンティティに対する葛藤もしばしばある。ふり返ってみると、ここにたどり着くまでずいぶんと回り道をした。
■回り道の研究人生
バイオテクノロジーブームが勃興した1980年代、DNAという遺伝暗号を読みとくことで生命現象を理解できるという生物観に惹かれて分子生物学に没頭した。しかし、のちに複雑なポストゲノムの迷楼をさまようことになる、この還元主義的生命観に早々と見切りをつけ、大学院では生物の進化を個体レベルで理解する行動生態学に執心した。ここで得た知識は、ヒトをふくめた動物の行動原理を理解する礎となった。その後、ポスドクとして環境科学のプロジェクトに従事し、生態系における目に見えないモノの流れを「見える化」する安定同位体に関する知識を身につけたことが、現在の研究スキームにも活かされている。
生態研に赴任した当時、部局のミッションとして「生物多様性および生態系の機能解明と保全理論」が掲げられた。回り道ばかりの研究人生だったが、生物多様性をミクロからマクロまで階層横断的に理解するうえでは、これまでの経験がおおいに役だった。生態研に身を置いて、ヒトをふくめた生物と環境の相互作用を理解する生態学という学問は、自然科学の諸分野を取り込むことができる懐の深い学問であることを実感した。
■なぜ、生物多様性は必要か
生態研ですごした10年間、生物多様性の生態系機能の解明に腐心した。しかし、その一端を明らかにしてもなお、心のなかのモヤモヤが晴れることはなかった。生態研では、琵琶湖流域の生物多様性保全に関する研究に取り組んだ。「生物が多様であることの意義を科学的に示せば、社会は生物多様性の保全へとむかう」と信じて研究を進めたが、現地調査で行き会う住民から怪訝な顔をされることこそあれ、感謝されることはなかった。研究の内容を説明すると、たいてい、こう返される──「なんかようわからんけど、それを調べてなんの役にたつの?」。生物多様性の生態系機能を解明し、科学的にインパクトの高い雑誌に論文を公表することが社会還元だと、どうやら勘違いしていたようだ。科学者の一元的価値を一方的に押しつけるだけでは、社会の変革など起こせないことを悟った。
科学や技術によって解決できることには限りがある。生物多様性の問題を根本から解決するには、一人ひとりが問題と向き合い、意識や行動を変えねばならない。そのためになにが必要か、自問自答をくり返し、地球研にたどり着いた。
■地域との信頼関係を育む
地球研に赴任して多様なモノの見方を学んだ。環境社会学を専門とするプロジェクトメンバーとフィールド調査に同行するたびに「地域研究は贈与の関係」と諭された。「なぜ、生物多様性が必要か」という問いの答えは、科学者が導くものではなく、そこに暮らす住民の生活や生業の文脈のなかで生まれてくるものだと。生物多様性の生態学的な意味を住民に説くまえに、科学者は生物多様性の意味を住民から学ばねばならないことにようやく気づいた。そして、フィールドで得た科学知は地域の価値として、社会に還さねばならない。
最近、フィールド調査に出かけると、地域住民から「ありがとう」と声をかけられるようになった。研究のやりがいを感じる瞬間だ。
ヒトは感謝されることで自身の存在意義を認識し、それが、他者への贈与の原動力となる。本プロジェクトの主要概念である「Well-being」とは、その字のごとく「よいあり方」である。個人の幸福感を超えて、より良い社会のためにわれわれがどうあるべきか問うてみたい。他者を思いやり、未来可能な社会をつくるために他者と価値を共有・共創することで、めざすべき学問の際
を超えられるかもしれない。この超学際プロセスこそ、環境問題が解決へとむかう第一歩と考えるに至った。
■社会の道具としての超学際科学
科学者が「社会のために」つくり出した技術が現在の環境問題を生み出している現実を内省し、「より良い社会のために」必要な科学知の共創をめざしたい。そのために、科学は、万人がつかいこなせる道具でなければならない。生態学には、知の共有をとおして、社会と科学とのギャップを埋めるポテンシャルがあると信じる。

フィリピンのラグナ湖流域で聖なる泉を保全する婦人会の皆さん。泉を利用する生活の知恵をとおして、人と自然とのかかわり、人と人とのかかわりが見えてくる
■研究プロジェクト
生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性
栄養バランスの不均衡が引き起こす流域の環境問題と地域固有の課題をともに解決するにはどうしたらよいか。おもに琵琶湖をフィールドとして、地域の自然を見直し、住民と協働して、その再生に取り組む。地域の栄養循環を再生させることで、持続可能な未来像を描く。
雑誌『地理』(古今書院、2017年)の1月号。プロジェクトメンバーとともに「超学際科学に基づく順応的流域ガバナンス」を寄稿

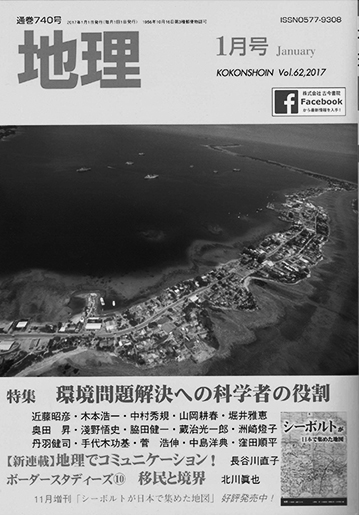
おくだ・のぼる
研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」のプロジェクトリーダー。調査フィールドは、水気のあるところならどこでも。徹底した現場主義。人と自然と酒をこよなく愛する。地球研には2014年から在籍。