わたしと地球研 ………… リーダーのまなざし ❸
このコーナーでは、地球研に在籍、もしくはかつて在籍していたプロジェクトリーダーが語り部となって、1枚の写真を手がかりに、自分の研究内容や将来の夢をひもときます。
学際的、超学際的、そして国際的な共同研究をめざして
羽生淳子 (地球研客員教授、カリフォルニア大学バークレー校教授)
私の専門は縄文時代の考古学である。考古学とは、遺跡に残された物質文化(遺物)から過去の人びとの暮らしを推測し、それにもとづいて文化や社会の変化のプロセスを考える学問である。しかし、発掘された遺物を眺めているだけでは、それをつかっていた人たちの生活はわからない。たとえば、縄文時代の矢じりはハート形の石だが、いままでに矢じりを見たことがない人には、その外見だけから機能をいいあてることはむずかしい。
遺跡や遺物を解釈するためには、考古資料と人びとの生活とをつなぐ理論が必要になる。考古学者は、生物学など他分野のモデル(数理的な一般法則)を借用したり、民族学の事例を参照しながら、物質文化と人びとの行動とのあいだの相関関係を推測する。だから、考古学は、学際研究(他分野の研究者との共同研究)が不可欠な学問である。
■ホッキョクグマに囲まれた発掘
1991年夏、カナダのマッギル大学人類学科の大学院生だった私は、北極圏内のサマーセット島で、チューレ文化(西暦1000~
1500年ころ)の住居跡を発掘した。サマーセット島の気温は、真夏でも日本の12月くらい。いちばん近くの集落でも40km以上離れている。6週間あまりの滞在中に見たホッキョクグマは、のべ35頭。けっして楽なひと夏ではなかった。
しかし、この地域では、考古資料を解釈するのに役だつ民族誌が豊富で、しかも永久凍土中の遺物の保存状態が良好である。つまり、物質文化から人びとの暮らしや行動の解釈をめざす考古学者にとっては、好条件のそろった地域である。この発掘で、北極圏の考古学者が民族学や生態学の知識と理論をどのように応用しているかを学ぶことができたのは、大きな収穫であった。
■地球研訪問と学際的研究
その後、私は、カリフォルニア大学バークレー校で職を得て、同校で考古学を教え始めた。2010年には、地球研に招へい外国人研究員として在籍し、縄文時代中期(約5,000年前)の生業の特化(つまり食の多様性の減少)が、当時の経済システムの脆弱化と人口減少につながったのではないか、とする研究成果を発表した。これをきっかけとして、地球研に所属するさまざまな分野の研究者との交流が始まった。
研究をつづけるうちに、人類の歴史のなかで、食の多様性がどのような意味をもっているのかを考えるようになった。近現代の事例では、食の多様性の維持は、経済・社会システムの長期的な安定性を保つためにだいじであることが知られている。たとえば、農業では、モノカルチャー(単一作物栽培)の弊害がさかんに論議されている。同様の問題の起源は歴史的にどこまでさかのぼるのだろうか。そして、このような問題はどうすれば回避できるのだろうか。
■小規模経済プロジェクトと学際・超学際・国際的な共同研究
小規模経済プロジェクトの原型となるインキュベーション研究は、これらの疑問から始まった。その後、2年間の準備期間を得て、2014年からは本研究を開始した。3年めの今年で、プロジェクトは最終年度を迎える。
東日本と北米西海岸をおもな研究地域とするこのプロジェクトでは、過去と現在に関する研究成果を積み重ね、その成果をもとに、実践・普及活動や未来への提言を行なう。学際研究はもちろん、ネイティブ・アメリカンや地域の住民、農家・漁家の方、NPOのメンバーなど、多彩なステークホルダー(研究対象とさまざまなかかわりのある人びと)との超学際研究をめざしている。
小規模経済プロジェクトのメンバーは、海外35名を含む81名。このなかには、環境にかかわる諸分野で、世界最先端の意欲的な研究を行なっている研究者も多い。メンバーの中には、今年5月に地球研外国人招へい研究員として来日し、農家の方や研究者と活発な意見交換を行なったミゲール・アルティエリさん(カリフォルニア大学教授)や、『タオ自然学』の著書で知られるフリッチョフ・カプラさんも含まれる(写真)。彼らのような自由な発想の人たちと、学問領域の枠を超えた議論ができるのは楽しい。
私の夢は、これらの学際的、超学際的、国際的な議論を通じて、食料生産のモノカルチャー化や、大規模な環境破壊に対抗できる世論をつくることである。ことばや文化のちがいがあっても、いっしょに研究をするうちに気心が知れてきて、多少の不便さは気にならなくなる。地球研とは、そういうことが可能な研究所だと思う。

農業生態学者ミゲール・アルティエリさん(左)、筆者(中央)と、物理学者フリッチョフ・カプラさん(右)。バークレー校近くのコーヒー・ショップにて
■プロジェクト
地域に根ざした小規模経済と>長期的持続可能性──歴史生態学からのアプローチ
地域に根ざした食料生産活動を機能させるにはなにが必要なのかを考える。社会ネットワークに支えられた小規模な経済活動と、それにともなう人間と環境の新しい相互関係性の構築を提唱する。

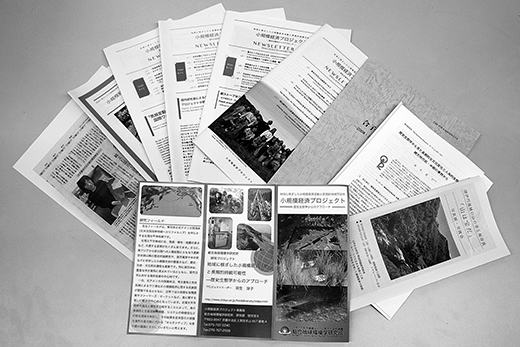
遺跡発掘報告書、学術論文、ニューズレター、新聞記事などのプロジェクト成果物
はぶ・じゅんこ
環境考古学者、人類学者。2014年春から、地球研教授・小規模経済プロジェクトのリーダーとして赴任。現在は、地球研客員教授として同プロジェクトのまとめにたずさわっている。カリフォルニア大学バークレー校教授。