連載
晴れときどき書評
このコーナーでは、地球環境学にかかわる注目すべき本、おすすめの本、古典などを幅広く取り上げて紹介します。
王 智弘 (地球研プロジェクト研究員)
深くおもしろく傍流を渡る
『野蛮から生存の開発論──越境する援助のデザイン』
佐藤 仁著
ミネルヴァ書房、2016年
四六判、344ページ
本体3,000円+税
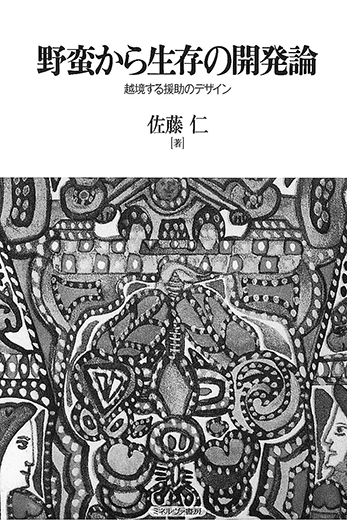
たとえば、熱帯雨林を大農園に変えるとき、開発は環境問題の原因であり、焼畑移動耕作を森林減少の原因として定住型農業の普及をめざすとき、開発は環境問題の対策である。かくも環境問題と密接な関係にある開発とはなんなのか。環境学とは切り離せないテーマである。
本書は、未開な「野蛮」の開化に始まり、貧困や経済格差の解消、そして地球の南北を問わず「生存」を脅かす環境問題対策へと展開してきた開発の潮流を描きだす。開発は時代により理念やアプローチ、ターゲットを変えるが、そこに国と国、人と人がかかわりあうドラマをみるからこそおもしろい。道義と功利、実践と論理、さまざまな考え方や立場が織りなす綾を読み解く著者の思考のステップを世に問う1冊である。
パズルと問いを見つける
貧困や環境問題を「おもしろがる」というと不謹慎に聞こえるが、著者の意図はこうだ。開発を、そして世界をよりよくするには、動機はなんであれまずは開発に興味をもつ人を増やさなくてはいけない。そして、実務や現場を経験するまえの、知識や学問から開発を知る人、たとえば、将来開発分野を志す若者には、知的好奇心を喚起する「パズル」の提示が必要である、と。複雑な問題は、解決の糸口がすぐには見つからない。だからこそ、現象を紐解くおもしろさを体験することがだいじになる。パズルの提示は開発に対する諦観や無関心に抗う知的な仕掛けなのだ。
そのためのもうひとつの仕掛けであろう。本書に散りばめられた「問い」の密度の高さは目を引く。目次に並んだタイトルは、序章と終章をのぞいて、すべて「問い」のかたちに仕立てられている。たとえばこうだ。開発・援助の知的技術を論じる第1部では「貧しい人々は何をもっているのか」と問い、不足を見つけて補うという開発・援助に根深い発想から離れて、開発そのものを問い直す。あるいは、「たった一つの村を調べて何になるのか」と問いかけて、深い理解をめざすフィールドワークの意義をていねいに検討する。
驚きから可能性の世界へ
多くの緊急物資がありながらなぜ必要な者の手に届かないのか。豊かな資源がありながらなぜ貧困が存在するのか。第2部の「開発・援助の想定外」で探求されるこれらの問いは、期待や予想からのずれという「驚き」に彩られている。その驚きから組みたてられた仮説は、どれも「穏便」ではなく論争的だ。そこに開発の本流からはずれた傍流を泳ぐおもしろさがある。傍流とは、通説とはちがった仮説であり、経済学や政治学などの学問分野の中の開発研究のことである。その傍流を注意深く渡ることで見えてくる可能性があり、本流が想定する前提に異議を唱える論理が生まれる。そうして新しい世界の拡がりを見るというわけだ。
定説の圧力を受けとめながら開発の理解を押し拡げてゆくさまは、深く水に潜る人が好きだといったアメリカの作家ハーマン・メルヴィルのことばを思いださせる。海底で潮流を見上げる者や潮流の中を漂い泳ぐ者が棲む世界で、だいじなのはそれぞれの見聞をもちよることで世界についての認識を豊かにすることだ。数は少ないが、あらゆる深度を自在に泳ぐクジラのような存在に求められるのは、未来にむけて各層の対話を促す構想力と好奇心である。
アイディアを育む風土の開発
第3部の「開発・援助と日本の生い立ち」に織りこまれた1950年代の日本の経験も、本書の開発論に深い色あいを加えている。海外からの原料に強く依存しながらも開発・援助への関心は低い。その屈折した構造の起源はどこにあるのか。著者は戦後まだ貧しかった日本が、アジア諸国への経済協力と原料の確保・輸出市場の拡大を抱きあわせて構想していた事実に注目する。ところが、その後の国際貿易をつうじた原料確保の実現により、日本の開発・援助はその切実さを失う。他方で、戦後という強い制約のなかで育った日本の開発・援助は、商業主義や縦割り体質が問題視されながらも、幅広い民間の活力と専門家の力を引き出したという。日本の開発・援助は批判一色で染めるには惜しい経験なのだ。
日本の経験にたち返る開発論は、終章でアイディアを育む風土への視点で締めくくられる。援助する側・援助される側を問わず、その国に人びとの知力やアイディアが活かされる環境があるかどうか。物的な資源の充足に劣らず開発の重要な論点である。そして日本にはその鍵を握る存在、すなわち、専門家ではないが専門家の仕事を鋭く批評し、あるいは読者として生産された知を享受する「アマチュア」が多く存在するという。経済が優先されて後手に回りがちな環境問題への取り組みも社会全体の活動からいえばまだまだ傍流だ。ならば、アイディアを支える「アマチュア」の拡がりが環境学にもほしい。そう考えるとこう自問してみたくなる。環境学はおもしろいか。そのおもしろさは伝わっているか。