特集1
巻頭座談会 〈トランスディシプリナリー・シリーズ その2〉
環境とアートとがつながる地平
話し手● 山内宏泰(リアス・アーク美術館学芸係長)+関口正洋(株式会社アートフロントギャラリー)
聞き手● 阿部健一(地球研研究基盤国際センター教授)
編集● 阿部健一
地球研は、環境問題の根っこには文化の問題が存在するという立場をとる。では、その文化とはなにか。
それを探る端緒として、宮城県気仙沼市リアス・アーク美術館で学芸員を務める山内宏泰さんと、新潟県十日町市・津南町で「大地の芸術祭
越後妻有アートトリエンナーレ」を企画・運営するアートフロントギャラリーの関口正洋さんを地球研に招いた。気仙沼市は、東日本大震災で津波の被害がきわめて大きかった港を抱える。新潟県十日町市は過疎・高齢化に苦しむ豪雪地帯の山村。自然の厳しさを残酷に突きつけられる地域において、芸術はなにを求められているのか。風土とアートにどういう結びつきがあるのか
阿部●アメリカ自然保護の父とよばれ、20世紀前半に活躍したアルド・レオポルドは、「ものごとは、生物共同体の全一性、安定性、そして美しさを保つ傾向にあるときに正しい」と述べています。人間が根源的に感じる美しさは、環境を考えるうえでだいじな問題です。きょうは、芸術の分野で活躍されているお二人に、日本の風景や風土についてお聞きしたいと思います。
まず、リアス・アーク美術館ですが、あの常設展示は東日本大震災の展示と、北三陸の食文化を紹介する展示ですね。この展示は山内さんが担当されたのですか。
山内●ええ。私は1994年の開館と同時に学芸員になったのですが、驚いたことに館所蔵の美術作品がまったくない。バブル期にはやった「箱物行政」の典型でした。
開館当初の企画展示会社による常設展示は、気仙沼地方の歴史・民俗系の資料を並べただけの「押し入れ美術館」。「なぜ物置に転がっているガラクタを見るのに金を払わなくてはいけないのだ」、地域住民の評判はさんざんでした。民俗学的な価値はあっても、背景の解説がなければ理解されない。
阿部●それでやり直したのですね。公立の美術館にしては、企画した人の個性が出ているなと思いました。
外の人との交流が地元に生きる活力に
山内●京都の美術館なら、掛け軸や仏像など、ふさわしい展示はおのずと想像できますね。しかし「気仙沼ならこういう美術」というイメージがわかなかった結果です。そもそも美術は、人の暮らしがあって、そのうえに生まれるものです。ですから、地元の人間が誇りにしているものを展示しようと。観光客が気仙沼に期待するのは海の幸。地元が誇る食べものです。食文化を軸にした常設にしようと……。
阿部●食材を獲るところから食べるところまでのストーリーがみごとにできている。
山内●子どもむけに手描きのイラストでわかりやすくすると、学校の先生や地域づくりの活動をする人が訪れるようになった。偶然だったのですが、「食による町づくり」を始めていた時期と重なって、初めて評価される文化施設になりました。
阿部●「大地の芸術祭」は、過疎・高齢化の進む越後妻有の地域(十日町市・津南町)を舞台に展開する国際芸術祭ですが、どのように始まったのですか。
関口●平成の大合併によって新潟県は市町村の数が112から30になり、県の合併施策の一環でスタートしました。十日町地域の市町村の合併を前提に地域の新しい青写真を描こうとしたことがきっかけです。越後妻有は山奥の豪雪地帯ですが、現代アートを地域で展開することで、場所の魅力や力を引き出すことができないかと。
阿部●参加するアーティストは、この地域に何日か住み込んで、土地と密接に関連する作品をつくる。ほかの芸術祭とくらべてユニークだと思いますね。
関口●いまでこそ十日町の施策の柱になりましたが、当初はものすごく反対がありました。「アートでまちがつくれるのか」と。でも、そんなムードを少しずつ変えたのは、参加した作家の仕事ぶりや姿勢です。作家には個性の強い人も多いのですが、逆にいえば独特の観点をもっています。それが、見慣れた地域の風景の新しい見方、切り口を提示してくれます。なにより、作品ができてゆく過程がおもしろそうだと。最初は遠目で見ているのですが、好奇心のある人はだんだん作家の手伝いを始める。それに首都圏のサポーターの存在です。孫ほど歳の離れたサポーターたちが、作家を手伝う。その過程で、民家を訪ねて材料や情報を集める。その一所懸命さに、地域の人も応えようと思うようになります。サポーターの活動は、アートと地域とを結びつける媒介になったのだと思います。
阿部●これまで何回開催されましたか。
関口●2000年から3年に一度開催していて、去年が第6回。2004年には新潟県中越地震があって、2006年の第3回を開くかどうかの岐路に立たされました。すると、それまで2回の芸術祭に参加した作家やサポーターたちが手伝いにやってきた。
阿部●復興の支援ですか。
関口●そうです。震災があっても自分たちの地域と結びついている外の人たちがいる。その存在を意識したことが、芸術祭をつづける地元の意欲になったのだと思います。
コミュニケーションを促して
価値観を転換する
関口●越後妻有でも、「自分たちの土地にはなにもない」という声をよく聞きます。ないと思い込んでいる。アートにはその見方を変える力と役割があります。
阿部●地元の人は地域の魅力に気づかない。
山内●子どもは展示資料を見るとおとなに質問しますね。しかしじつは、おとなもよくわかっていない。その点、リアス・アーク美術館では展示資料を子どもむけに解説しているので子どもに説明しやすい。そういう構図があると、どの親も「つまらないね」とは言えない。「おもしろいね」。そこで価値観を転換させる。
関口●越後妻有のアートも、当初地元民から「あれが芸術なの」と。でも、外の人(旅行者やサポーター)との交流をつづけるうちに見方が変わってきた。そしていまは風景の一部になりました。作品がないと寂しいと。
阿部●「棚田」という作品には感心しますね。
関口●ロシアの作家イリヤ&エミリヤ・カバコフの作品ですね。
阿部●越後妻有の人たちにとって棚田はありふれたもので、むしろこの風景からはつらい農作業を喚起させられる。棚田には機械も入らない。人の手か、せいぜい牛の力で耕作し、稲を植える。
カバコフの作品では、棚田で働く人の彫刻を棚田に置いてあります。地域の人にとってはつらい思いでも、外の人の目からは棚田は美しい。このギャップがよく表れている。あの棚田の持ち主も耕作をやめるつもりだと聞きましたが……。
関口●高齢化で、予定では2000年に耕作をやめるつもりだったのが、2006年までつづけられました。作品をきっかけに棚田への誇りを取り戻されたのだと思います。
山内●外の人とのコミュニケーションは、シャイな東北人は苦手。親子の会話はちがうはずですが、このごろは子どもの問いに答えられない親世代が多い。
阿部●家族構成が変わって、祖父母の知識や生活の智恵が伝わらなくなっている。
関口●十日町でも、世代ごとに積みあげてきた知識がスポッと抜けていて、逆に地域外の人のほうが関心をもっている。
山内●地域再生において、住民が地元に誇りをもつことは重要なキーになる。「外部の人にはわからなくても、自分たちにとってはだいじなものだ」と胸を張れるもの。
関口●逆に、地元民だけの選択だと、手間のかかる棚田は捨てざるをえない。「地域のものを自分たちが処分してなにが悪いのだ」と言われれば、所有権にもとづく自己決定には口をはさめない。どうすれば地域外の人の価値観を同じ土俵に載せてもらえるのか。「オラがムラ」から「ムラのオラ」に変わるステージを用意しないといけない。そこでは地域外の人も対等にかかわることができる。そのような場こそ、広い意味でのアートだと、私は思います。
阿部●離れたものをつなぐことで驚きや懐かしさを喚起したり、結びつくことで新しい見方が生まれるということでしょうか。
山内●接点として機能することは、作品がおもしろいかどうかを考えるうえで重要な要素。作品をとおして新たな視点が得られなければつまらない。
後世に伝えるべき記憶は未完
阿部●リアス・アーク美術館では東日本大震災の記録も展示していますね。この展示はどういう思いでつくられたのですか。
山内●展示には、津波が発生した瞬間からの写真があります。選りすぐった200枚の写真にはすべてレポートをつけました。美術館の展示ですが、一部の人に「この展示は山内さんの作品だね」といわれます。
学芸員は研究者であると同時に表現者だと私は認識しています。来館者と震災の話をしたい。会話するための資料、材料として提示している感覚です。記録をたんなる客観的資料として見てもらう気はないのです。
阿部●記録はどこかに客観的な部分があるのですが、あの展示は主観ですね。
山内●ただ、まったくの個人的な主観になってしまうと、受け手は人ごとだと思ってしまう。その人の感覚を共有できなくなる。私たちが考えているのは、みんなが分有できる、あるいは共有可能な相似の経験を提示することです。
阿部●どうくふうされましたか。
山内●津波で家が流されてすべてを失うという悲しみの経験は、体験しないとわかりません。たとえば、自分がだいじにしているだれかからのプレゼントが、ある日突然になくなったら懸命に探しますね。そういう言い方をされると、「そんな感覚で身の周りのすべてのものがなくなったら堪えがたいな」と思える。つまり、客観的な記録だけでなく、共有可能なストーリーが必要。
阿部●シェイクスピアのような普遍的なストーリー。
山内●物語にすることで伝わりやすい。
阿部●越後妻有でも、廃屋や廃校を利用してなにかを訴えかけようとする作品が多い気がしたけれど、どうですか。記録より記憶を重視しているように思いますが……。
関口●越後妻有の人びとはかつての暮らしを忘れようとしている、あるいは忘れたいと思っている。古い暮らしをモチーフに、汚い身なりで踊るパフォーマンスなんか、地元の人は「見たくない」という。「そんな時代の遅れたものを忘れたい」と。しかし、それはこの地域の文化をつくってきた土壌でもある。それを作家は思い起こさせようとしています。
阿部●気仙沼の人たちも、津波を忘れようとするベクトルをもっていますか。
山内●2種類あります。忘れようとするというのは、知っているということですから、そういう人たちは忘れてかまいません。忘れなければ生きてゆけないくらい強烈な記憶ですから。でも、いかにつらい記憶だとしても、伝えなければならないことがある。なぜなら、それを伝えてゆかなければ自分の子や孫が死ぬことになるからです。
しかし、地元の被災者ですらじつは震災をうまく認識できていません。「津波がきます」といわれて避難し、「避難所から出てもよいですよ」といわれて現場に行くと、すべて片づいて、まちのようすが変わっていた。記憶喪失の状態になっている。
阿部●後世に伝えるべき記憶が未完だとすると、記憶づくりをしなければいけない。
山内●まさにそのとおりです。
コンクリートの巨大な壁をつくるのも日本の風土
阿部●日本の自然は、世界各国とくらべて恵まれています。こんなに緑の濃い列島はそうはない。海の幸も豊か。しかし、地震や洪水など自然災害がきわめて多い。
山内●三陸沿岸部において地域文化を考えるとき、津波災害を度外視できない。今回も根こそぎ津波にもっていかれました。ですから、リアス・アーク美術館は、震災前から津波に関する展示をしていた。2006年には、1896(明治29)年の津波記録、「風俗画報大海嘯 被害録」を展示しました。ところが、みなさん興味や関心を示さない。津波をどこかでなめていた。高度経済成長期に防潮堤を大量につくり、津波は起こらないという前提で地域を開発してきたからです。近世以降、平均40年に1回は大津波が三陸地方を襲っていたにもかかわらずです。確実に津波が起こる前提でないと生きられない土地です。たとえば、豪雪地帯で雪を無視したまちづくりなんてありえない。同様の視点で自然環境との付き合い方を再確認するべきだと訴えているのが、私たちの展示です。
関口●「雪を待っている風景」というか、いちばん厳しい季節にあわせているのが越後妻有の風景です。世界の集落にも、自然の動きにあわせてつくられた集落の例はたくさんありますね。ふだんは通路として利用しているが、水があふれたときは川になる通路が集落の中を通っているメキシコのメヒカリチタン集落がある。イラクのチグリス・ユーフラテス川下流の集落には、沼沢地帯で2~3年で壊れるのが前提の家がある。
山内●越後妻有で民家の基礎が高いのは、そこまで雪が積もるからだとわかる。夏でも雪の存在を感じる。
関口●棚田も多くが地すべりの跡につくられています。十日町には平地がほとんどなくて、「豪雪、地すべり、平地がない」という負の条件をプラスに活かしたのが棚田。
阿部●大地の芸術祭では、かかしが芸術品に見えたりする。生活の必要性から生まれたものと芸術作品との境目が薄れる感覚がありました。棚田や砂防ダム、機能重視の建造物を美しいと感じました。
関口●越後妻有では、アートは暮らしと切り離されたものではなく、生活に光を当てるものとして位置づけています。大地の芸術祭では、砂防ダムを利用した作品があります。砂防ダムは、東日本大震災の翌日の長野県北部地震での土砂崩れのあとにできました。そのときの土砂の流路を可視化することで越後妻有の土地の力や、巨大な土木建築物がどう見えるかを問う作品でした。
阿部●景観と人工物という点で、防潮堤はどうですか。
山内●気仙沼に巨大防潮堤ができて、悪い意味で現代アート作品のように思えました。日常的機能を見いだせない巨大な建造物が、突然出現したからです。津波が発生しないかぎり、防波堤は無用の長物でしかない。私は、「防潮堤にボルダリングのコマをつけて、コンクリートの壁を登るスポーツの場にしてはどうか」との提案をしています。登りきると、海と町を同時に見わたせる。どうせ建ったのだから、アクティビティとして有効活用しながら、津波災害や減災、環境についてあらためて考える場にしてはどうなのか。
関口●なるほど。砂防ダムも、芸術祭の期間中は登れるようにしました。
阿部●地球研の客員教授だったオギュスタン・ベルクさんに気仙沼で建設中の防潮堤を見せたことがあります。防潮堤反対派のように、「海が見えない」と批判されるだろうと思っていたら、彼はたったひとこと、「これが日本の風土ですか」。善いか悪いかではない。長い歴史の末にあれをつくったのは、まさに日本の風土。海の景色は見えたほうがよいが、これからをどうするかという意識で考えなくてはいけない。
(2016年1月21日 地球研「はなれ」にて)

新潟県越後妻有の砂防ダム(2015年10月撮影)


新潟県十日町市松代に展示されたイリヤ&エミリヤ・カバコフの「棚田」(2015年10月撮影)

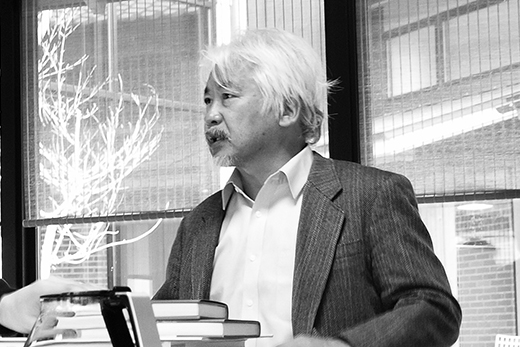

*この座談の後日、景観とアートの関係を探る下記のシンポジウムを開催した
地球研公開シンポジウム 懐景創景──Imaginary landscapes: The real and the possible
2016年2月27日(土) 13:00 - 17:00 〈南禅寺龍渕閣〉
開会挨拶 安成哲三(地球研所長)
趣旨説明 阿部健一(地球研教授)
-
第1部 基調講演
懐景創景──Imaginary landscapes: The real and the possible
……ダニエル・ナイルズ(地球研准教授)
-
第2・3部 パネリストによるプレゼンテーション
Borrowing a place ……柴田敏雄(写真家)
既成事実化された風景……広川泰士(写真家)
災害と風景について……山内宏泰(リアス・アーク美術館学芸員)
アートとランドスケープの新たな関係:越後妻有のケース
……関口正洋(アートフロントギャラリー)
作品、作家、鑑賞者が織りなす景観としての展覧会 ……北出智恵子(金沢21世紀美術館学芸員)
-
第4部 討論
【パネリスト】 (写真左から)北出智恵子/関口正洋/山内宏泰/広川泰士/柴田敏雄
【モデレーター】 阿部健一

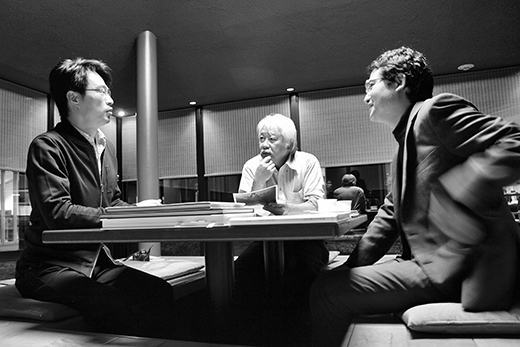
(右から)
せきぐち・まさひろ
1974年神奈川県生まれ。アートフロントギャラリーに入社後、第一回大地の芸術祭から現地業務のコーディネートにかかわる。現在は同社にて各種アートプロジェクトのマネジメントに従事。
あべ・けんいち
専門は環境人類学、相関地域学。地球研研究基盤国際センターコミュニケーション部門部門長・教授。2008年から地球研に在籍。
やまうち・ひろやす
1971年宮城県生まれ。リアス・アーク美術館学芸係長。美術教育、三陸沿岸部の歴史、民俗等を専門とする。