連載
晴れときどき書評
このコーナーでは、地球環境学にかかわる注目すべき本、おすすめの本、古典などを幅広く取り上げて紹介します。
太田民久 (地球研研究基盤国際センター研究推進支援員)
コトバの多様性と生物多様性
『シークヮーサーの知恵──奥・やんばるの「コトバ-暮らし-生きもの環」』
大西正幸/宮城邦昌 編著
〈地球研和文学術叢書〉京都大学学術出版会、2016年
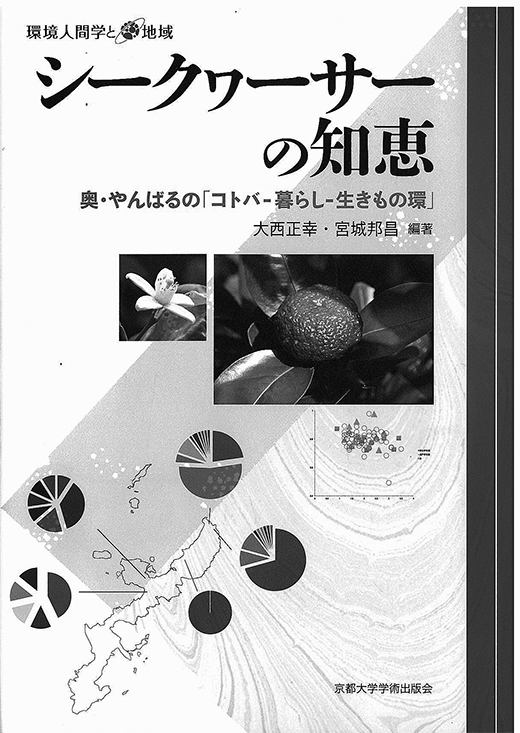
コトバ(方言をふくめた、その地域の固有言語)は、人間が生活するうえでさまざまな事柄を伝達するために用いられる。人間の生活の基本である衣食住を考えてみると、植物から繊維を採る、食物を採集するといったようにじつにさまざまな生物を利用していることがわかる。すると、とうぜん、それらに関連したコトバがつくられる。利用する生物が多様であればそれをさし示すコトバも多様化する。つまり、生物多様性とコトバ(文化)の多様性が関係しあっている可能性はある。本書は、やんばるの奥とよばれる集落を舞台としたモデル研究をもとに、その可能性に踏み込んでいる。
やんばるの奥集落に伝わるコトバと智恵
私が専門とする生態学の分野において、他の生物の生息地の環境条件を大きく改変する作用をもつ生物(例ダムをつくるビーバー、土壌を耕すミミズ)を生態系エンジニアという。人間こそ地球の歴史上最強の生態系エンジニアであろう。そして、人間が生物の多様性を損なわない生態系エンジニアであることは、持続的な社会の実現につながる。そのためには、地域のコトバの継承と維持が重要であると本書は論じている。
たとえば、奥集落の方がたは、じつに多様な生物を海や山から採集し利用している。その生物利用に関連するコトバもまた多様である。生物の呼び名だけでなく、その採集道具や方法、採集場所の微地形、採集する際の注意点等々、さまざまなコトバが本書には登場する。さらに、それら多様な生物を持続可能なかたちで利用・維持するための情報や智恵も、コトバのなかに存在している。これだけで、やんばるの奥集落の生物多様性が地域の人びとのコトバの多様性と密接に関係しあっていることがわかる。その代表例として、シークヮーサーが紹介されている。奥集落ではシークヮーサーの形質および遺伝的多様性が他の地域と比較してひじょうに高い。その理由として、集落の人びとがコトバによりシークヮーサーを形質ごとに分類し、用途を伝承してきたことが関係していると著者は考察している。
コトバの分布と生物との関係
生物多様性とコトバの多様性を考えるうえで、その地域でのみ使用されるコトバの分布パターンも重要な着目点であろう。本書では、東南アジアなど生物多様性が高い地域では、比較的狭い範囲に多数のコトバが存在することが紹介されている。このような関係の背後にはどのようなメカニズムが存在するのだろう。
一定数の人間が一所に留まって生活し、他の地域との交流が比較的少ない環境下でないと、コトバは生まれにくいと想像される。つまり、地理的に比較的近い集団があるにもかかわらず、コトバが発達するには、移動が困難であるといった地理的条件がまず考えられる。加えて、人間の生活が成り立つていどには、多様な生物が狭い範囲内に存在している必要がある。そしてその地域ごとに、生物を持続可能なものとする智恵がコトバのなかに存在することが推測される。
コトバの多様性の保全は、生物多様性の保全に通じるか
現在、世界各地において地域固有の言語は消滅の危機にあり、その情報や智恵は失われつつある。それに歯止めをかけるには、どうしたらよいのであろう。
地域や集団内において用いられるコトバは、人間のアイデンティティと深く関係している。私自身、故郷の方言を耳にするととても落ち着くことができる。「そういえばこの生きものはこう呼んでいたな」とふと思い出すことは、「やはり私はこの地の人間である」と再確認させてくれる。そのような、アイデンティティの形成から集団を維持する意識が芽生え、地域に固有のコトバを継承してゆこうという意志にもつながる。そのためにも、多くの地域におけるコトバ、およびコトバと生物との関係性をアーカイブすることの重要性を本書は伝えている。そして、多様な生物が存在し、地域住民との持続可能な相互作用系を維持している奥集落において著者らが実施した研究は、たんなる事例研究にとどまることはけっしてないだろう。奥集落における人びとの意識は、他の多くの地域において規範となるものである。
惜しむらくは、本書に記載された諸研究が、地球研のプロジェクトとして採択されなかった関係で、中断を余儀なくされた部分が多いことであろう。その無念さは本書の随所に感じられる。しかし、グローバル化の嵐が吹き荒れ、固有の言語や文化が消えつつある昨今、人類の幸せとはなにかを考え直す材料を与えてくれる、かけがえのない研究であることはまちがいない。