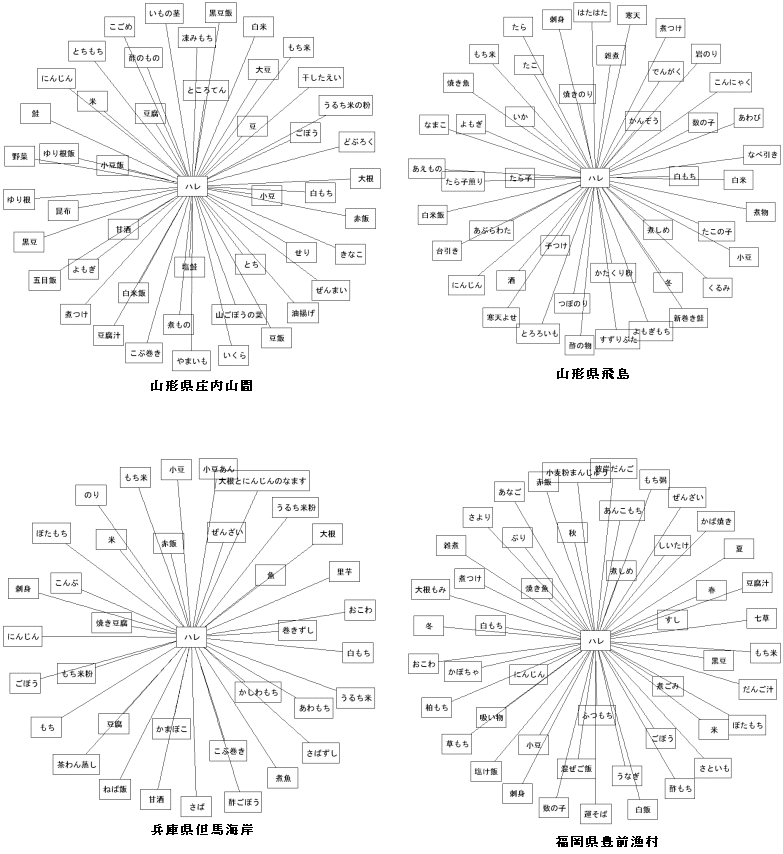���[�L���O�O���[�v
last update: 07.10.04��@ �F �Ð��� | �Ðl�� | �A���n��
�n�� �F �k�C�� | ���k | ���� | �ߋE | ��B | ��������
�X�y�V���� �F �}���n�i�o�`�� | �͔|�A���� | ������ | �ۑS��
�� ��@
�Ð��Ԕǁ`���{�ɂ�����ŏI�ԕX���ȍ~�̐A���ϑJ�Ɛl�Ԋ���
���[�_�[�F�@�����@���i���s�{����w��w�@�_�w�����ȁA�Ð��Ԋw�j
�L�[���[�h�F�@�A���ϑJ�A�C��ϓ��A�l�ׂɂ��A���ω��A��ƐA���j
�����̖ړI�C���e�C���@�Ɗ��҂ł��鐬��
�Ð��Ԕǂł́A���L��4�̉ۑ�ɂ��āA�A���n���ǂ�e�n��ǂƂ̘A�g�����Ȃ��猤����i�߂�BA�D�X��-�ԕX���ɑΉ������A���ϑJ�i�����C��ϓ��ƐA���ϑJ�j
-
�m�ړI�n�@���݂��܂ޒn������ł����l�I�̌㔼�ɂ́A10�����N�����ŕX���ƊԕX�����J��Ԃ���Ă������Ƃ����炩�ɂ���Ă���B���̋C��ϓ��ɑ��āA����̐A�����ǂ̂悤�ɕω����Ă������𖾂炩�ɂ���B
�m���҂���鐬�ʁn�@���{�̊e�n�ɂ����ĐV���Ȓ����̐A���ϑJ�f�[�^��B
[���@] �i1�j���{�e�n�ɂ����āA�ߔN�ڍׂɉ𖾂���Ă��Ă���ΎR�D�w���������Ԏ��ɂ��āA�����̐A���ϑJ�f�[�^��Δ䂷��B �i2�j���L�n��ɂ����āA�K�v�ȑ͐ϕ����̎悵�A���͂�i�߂�B �@�@�_�g�~�n�i���s�j�A���i�i����j�A���r���i����j�A����w�i����j�A�k�C���Ȃ�
-
�m�ړI�n�@���{�ɂ�����ԕ����͂��^�A����̂̌������ʂ���A�ŏI�X���Ő����ɂ�����A���Ǝ�v����̓���n����ъ��V���ɂ����镪�z�̊g��k���ߒ����𖾂���B
�m���҂���鐬�ʁn�@�A���n���ǂƂ̘A�g�ɂ���āA���݂̊e����̈�`�^�C�v�̕��z�Ƃ̊֘A���܂߂Č�������B�܂��A�����̕��z�g��k���ɋy�ڂ����������̉𖾁A���ɍŏI�X���ɂ������^�M���ނ̕��z���̉𖾁i�����n���w�A�l�Êw�Ƃ̘A�g�j�ɂȂ���B �Ƃ��ɁA�X�M�A�u�i�A�R�i�������A���~���A�g�E�q���A�c�K���A�`���E�Z���S���E�A�Ɨt���ȂǁB
[���@] �i1�j�ÐA���}�̍쐬�F�ŐV�̃f�[�^�Ɋ�Â��A�ŏI�X���ȍ~�̂������̎����ɂ��āA���{�̌ÐA���}���������邢�͐V�K�ɍ쐬����B �i2�j�Ɨt���A���ѐj�t���A�u�i�Ȃǂ̗��t�L�t���A�����ѐ��j�t���Ȃǂ̕��z�g��k���ߒ���}������B
-
�m�ړI�n�@���{�e�n�ɂ�����ꕶ����ȍ~�̐A���ω��Ɛl�Ԋ����̊W�𖾂炩�ɂ���B�Ƃ��ɁA�͐ϕ����̔����Y�ʂ̕��̓f�[�^������ɒ~�ς��A��ƐA���̊W�ɂ��Č�������B
�m���҂���鐬�ʁn�@�i�R�j�ŏڏq���钲���n��ɂ����āA�V���ȉԕ��A�����Y�Ȃǂ̃f�[�^�āA�����̃f�[�^�ƕ����邱�Ƃɂ��A�e�n��ɂ�����ꕶ����ȍ~�̐A���ω��Ɛl�Ԋ����Ƃ̊W�����炩�ɂȂ�B�܂��A�n��Ԃ��r���邱�Ƃɂ��A�l�����x��l�Ԃ̊����l���̈Ⴂ���A�ǂ̂悤�ɐA���ɉe�����y�ڂ����̂����炩�ɂȂ�B
[���@] �i1�j�ߋE�n���A���ɓޗǁE���s�́A�Ñォ��l�����W�������n��ł���B�����ł̐l�̊����ƐA���ω��̊W�ɂ��ĉ𖾂������߂�B �i2�j��������z���Ă����n��A�Ĕ����s���Ă����n��ȂǁA�e�n�ɂ�����l�X�Ȑl�Ԋ����ƐA���Ƃ̊W���𖾂���B �i3�j���L�̒����n�ɂ����ĘI���܂��͎�������͐ϕ����̎悵�A�����Y���́A�A���]�_�̕��́A�ԕ����͂Ȃǂ̌Ð��Ԋw�I��@�ɂ��A��L2�ۑ�ɂ��ĉ𖾂���B
���h�i�F�{���j�C�ŗt���i�F�{���j�C�����R�n�i���R���A���挧�A�������j�C�]�����i�ޗnj��j�C�O�㔼���i���s�{�j�C�O�g�R�n�i���s�{�j�C���i�Ή��݈�i���ꌧ�j
-
�m�ړI�n�@���{�ɂ������Q���N�O�̍ŏI�X���Ő������猻�݂܂ł̐A���ϑJ�Ɋւ���f�[�^�́A���Ȃ�[�����Ă��Ă���B�����̃f�[�^���A�Ð��ԕ���̌����҂����łȂ��A������̌����҂ɂ����p���Ă��炦��悤�A�f�[�^�x�[�X���쐬����B
�m���҂���鐬�ʁn�@���{�̌ÐA���f�[�^�ɂ��āA�f�[�^�x�[�X���\�z����B�f�[�^�x�[�X��NOAA��Global Pollen Database�iGPD�j�ɓo�^����B
[���@] �i1�j���{�̊e�n�ɂ킽���āA��v�ȉԕ����̓f�[�^�ɂ��āA�J�E���g�f�[�^�A�͐ϕ����A�n�_���Ȃǂ����W���āAGlobal Pollen Database�ɓo�^����B �i2�j�e�����҂��o�^���₷���悤�ɏ��������J���A�f�[�^�o�^�𑣂��B
����܂łɖ��炩�ɂȂ�������
A. �X��-�ԕX���ɑΉ������A���ϑJ�i�����C��ϓ��ƐA���ϑJ�j����܂ł̌����ŁA���݂̉��g���̐A�����A�ŏI�ԕX���₻��ȑO�̊ԕX���̂���Ƃ͈قȂ��Ă��邱�Ƃ�A�X��?�ԕX���ϓ��̂Ȃ��Ő�ł����킪�F�߂���ȂǁA���݂̐A�����l�����ŏd�v�Ȑ��ʂ������Ă���B�X���|�ԕX���ϓ��ɑΉ�����悤�Ȓ����̐A���ϑJ���L�^���Ă���͐ϕ��͑����͂Ȃ����A���i�A���s�{�_�g�~�n�A���쌧����w�ȂǁA�e�n�ő͐ϕ��̍̎悪�����Ȃ��A���͂��i�߂��Ă���B���̂ق��A�k�C�����B�ȂǂŐV�K�{�[�����O�n�_�̑I���i�߂Ă���B
B. �ŏI�X���Ő����ɂ������v����̕��z�g��ߒ��̉�����܂ŁA�ŏI�X���Ő����⊮�V���̂������̔N�ゲ�ƂɌÐA���}����Ă���Ă����B�������ŋ�10�N�ԂɁA�����I�ȐA���ϑJ�Ɋւ���V���ȃf�[�^���W�ς������B
C. �l�Ԋ����ƐA���̕ω��Â�����̐l���W���n�ł��������s�𒆐S�ɁA���s�~�n�k����O�g�R�n�ɂ��āA�ԕ����͂���ђY���Е��͂��Ď��{���A�ЂƐA���ω��Ƃ̊W���������Ă����B���̌��ʁA����܂ŌÕ�����ȍ~�Ƃ���Ă����}�c���ԕ��̑����J�n�����i�l�Ԋ����ɂ��X�єj�i�ގ����j���A�n��ɂ��O�シ�邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�܂��A�ߋE�n���ł́A���V���O���i1���N�O�`5000�N�O�j�ɉЂ������������Ƃ�A���Ȃ��Ƃ������ȍ~�ɂ́A�e�n�ŏĔ��ɂ��\�o�͔|�������Ȃ��Ă������ƂȂǂ����炩�ɂȂ��Ă����B
D. �ŏI�X���Ő����ȍ~�ɂ�����A���ϑJ�ɂ��Ẵf�[�^�x�[�X�f�[�^�x�[�X�o�^�̂��߁A���łɖ�90���̌ÐA���f�[�^���A�����̌Ð��Ԍ����҂̋��͂ɂ���Ď��W����Ă���B��������ƂɃf�[�^�̐����������Ȃ��A���͏����ɂ��Č������Ă���B
�A���n���ǁ`���{�ɂ�����A���̗��j�I�����ߒ��̉�
�@���[�_�[�F ����@�N�� �i��s��w�����A�A�����q���ފw�j
�@�L�[���[�h�F�@���q�A���n���w�A�jDNA�A�t�Α�DNA�AGIS�f�[�^�x�[�X
�����̖ړI�Ɠ��e
���{�́A��8000����̐A�������炷�鉷�ђn��ɂ����Ă͐��E�ɗނ��݂Ȃ��������l���̍����n���1�ł���B����ł́A���݁A��X�����{�Ŗڂɂ���l�X�ȐA���́A���A�ǂ�����A�܂��ǂ̂悤�Ȍo�H�œ��{�֓����Ă������̂Ȃ̂��낤���H
�{�����ł́A���Ɍ��݂̐A�����̌`���ɍł��傫�ȉe����^�����ƍl������ŏI�X���ȍ~�̖�2���N�̕ϑJ�������ΏۂƂ���B����ɌÐ���WG�ɂ���ē���ꂽ�ԕ����f�[�^�Ƃ̔�r�A�������s�����ƂŁA���E�ɗނ����Ȃ����̗ʂ���ю��̃f�[�^�Ɋ�Â����A�����̕ϑJ�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�{�����̍ŏI�ڕW�Ƃ���B����ɁC�{�����ł͈قȂ�A����Ԃŗe�Ղɂ��q�ϓI�Ɉ�`�I�����̒n���I�p�^�[�����r�ł���悤�ɁA��`�I�ψق̒n���I���z���f�[�^�x�[�X����GIS�ɂ���ĕ\������ׂ�������i�߂Ă���B�����̕��@
3�̍��ڂɂ��Č�����i�߂Ă���B-
����1. �e�����o�[�����{�̗l�X�ȌQ�n�i�Ɨt���сA�ėΎ��сA�j�t���сA���R�тȂǁj�ɐ��炷�鑽�l�ȐA����ɂ��ĕ��q�A���n���w�I��͂�i�߂āA���ꂼ��̎킲�Ƃ̈�`�I�ψق̒n���I���z�p�^�[���𖾂炩�ɂ���B
����2. �����o�[����͂������ꂼ��̐A����̎�����`�I�ψق̒n���I���z����Ԃŋq�ϓI�ɔ�r���A���ʂ���n���I�p�^�[���Ȃǂ����o�����Ƃ̂ł���f�[�^�x�[�X�E�V�X�e�����\�z����B
����3. ���{�ɐ��炷��A���킲�Ƃɂ�葽���̎���̈�`�I�ψفA����ɂ͂��̒n���I���z������悤�ɊjDNA�̐V���Ȉ�`�I�}�[�J�[���J�����A�����p���ĕ��q�A���n���w�I��͂��s���āA����ꂽ�������p���Ċe�F����̒n���I���z�̗��j�I�ϑJ�𖾂炩�ɂ���B
����4. ����ɁA�������f���Ȃǂ����p���āA�A����̒n���I���z�̕ϑJ�ɔ����āA����̈�`�I�ψق̒n���I���z���ǂ̂悤�ɕω����邩�ɂ��Ă̗��_�I�������i�߂āA���ۂ̐A���킩�瓾��ꂽ���q�A���n���w�I�f�[�^����A���̒n���I���z�̗��j�I�ϑJ�Ɋւ��Ă�葽���̏���ǂ݂Ƃ��悤�ɂ���B
����܂łɖ��炩�ɂȂ�������
-
����1�F�Ɨt���тɐ��炷��J�i�����`�A�ėΎ��тɐ��炷��c���o�i�A�z�I�m�L�A�A�J�V�f�A�E���~�Y�U�N�����ɂ��āA���N�x�A�V���ȕ��q�A���n���w�I�f�[�^���B
����2�F���q�A���n���f�[�^�x�[�Xplantgeo�̍쐬�D���N�x��GIS�f�[�^�x�[�X�̂���������\�z���邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��A����܂łɓ����Ă����{�^���{�E�t�E����уc���u�L�̃f�[�^��p���āA�f�[�^�x�[�X�̓��͍��ڂȂǂɊւ��Ď��s������s�����B
����3�F�V���ȊjDNA�}�[�J�[�̊J���D���{�̏Ɨt���тɗD�肵�Đ��炵�Ă���A�����1�ł���^�u�m�L�A���{�ɍL�����z���Ă���n�}�q���K�I�ɂ���EST���C�u�����[�̍쐬���s���Ă���B
�Ðl���ǁ`�Ðl�����͂ɂ����{�ɂ�����H�����̕���
���[�_�[�F ���{�M�a �i�����n�����w�������A�A�����Ԋw�j�L�[���[�h�F�l���A�R���[�Q���A�H�����A�ړ��A���ʑ�
�����o�[
�����ړI�Ɠ��e
�ŏI�X���ȍ~�A���{�ɂ����Đl�Ԃ͎��R����H���Ȃǂ̎����Ă������A�Z�p�v�V�ɂ���ċ}���ɂ��̎����l�����������߂����ʁA�������̑r���␅�������ȂǁA�ߔN�Ɍ���������������N�����Ă���B�ߋ��̐H���₻�̕ω��̎d���͒n��ԂŁA�܂�����ɂ���Ă͒n����̌l�Ԃł��傫���قȂ�ł��낤�B
�Ƃ���ŁC�ߋ��̐l�Ԃ��ǂ̂悤�ȐH����H�ׂĂ����̂��i����A���Ȃ̂��A���㓮���Ȃ̂��A�C�Y���Ȃ̂��j�A���邢�͂ǂ��̐H����H�ׂĂ����̂��́C�Ðl���Ɏc���ꂽ�^���p�N������ʌ��f�̒��ɋL�^����Ă���B�{�����v���W�F�N�g�ɂ�����Ðl���ǂ̌����ړI�́A�Ðl���̃^���p�N���i�R���[�Q���j����ʌ��f�̓��ʑ̕��͂ɂ��A���{�ɂ�����ŏI�X���ȍ~�̐l�Ԃ̐H�������A�y�т��̎���ω��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɂ���āA�l�Ԃ����R����ǂ̂悤�ȐH�������Ă����̂��A�Ƃ����l�ԂƎ��R�̊W���̎���ω��ɂ��ė������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B
�����̕��@
���{�ɂ����Ď�̏W�A���{�ɂ�����s��o�ρA���E�s��o�ς����B�����R�̎���敪�i�ꕶ�A�]�ˁA����j��ΏۂƂ���D
�ꕶ����y�э]�ˎ���ɂ��ẮA�{�����ň����Ðl�������{�ɂ����Ĕ�r�I�������@����Ă���B�{�����ł́A�]�ˎ���̌Ðl���𒆐S�ɉ��w���͂��s���B�܂�����ɂ����ẮA�l�Ԃ̖є�����{�e�n�ŕW�{���o����B�ꕶ�ƍ]�˂̌Ðl���A����̖є���Ώۂɓ��ʑ̕��͂��s���A���{�ɂ����铯�ʑ̂̒n��ԁA�n����̈Ⴂ�⎞��ɂ��ω��𖾂炩�ɂ���B
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
���݂����͓r���ł��邪�A�����_�Ŗ��炩�ɂȂ������Ƃ́A�ꕶ����ɉ����Ă͏W�c�i�g�ӊL�ˈ�Ձj���ɂ����Ă��A�^���p�N���̈ˑ��x�Ō����ꍇ�A�C�Y���ɋ����ˑ�����l��A����A���ɋ����ˑ�����l�ȂǁA�l�Ԃő傫���H�����قȂ��Ă������Ƃł���B�܂��]�ˎ���̕����̌Ðl���ɂ��āA�\���I���͂��s�����Ƃ���A�ۑ���Ԃ͂悭�A�T���v���͕��͉\�ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B���N�x���ɂ́A�]�˕����l���ɂ��āA���̐H�����̕�����l�Ԃ̐H���̈Ⴂ�����炩�ɂȂ�\��ł���B
�� �n��
�T�n�����E���C�B�ǁ`���{�C�k���n��ɂ��������X�V���̊��ϓ��Ɛl�Ԃ̑��ݍ�p�Ɋւ��鑍���I����
���[�_�[�F �����@�G�V �i������w��w�@�l���Љ�n�����ȁA��j�l�Êw�j
�L�[���[�h�F�@���{�C�k���n��A����X�V���A���Ί펞��A�������A�A����
�����ړI�Ɠ��e
���{�C�k���n��ɂ��������X�V���̋C��ϓ��Ƃ���ɔ������A��(��)�������̕ϑJ���A���Ί펞��̐l�Ԋ����Ƃ��̕����`���ɂǂ̂悤�ȉe����^�����̂��ɂ��āA����I�Ȏ��_�ƕ��͂���]����^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
����̃v���W�F�N�g�ł́A���Ί��ՁE�������E�ԕ������ꂼ��̊������ʂ̃f�[�^�x�[�X�\�z�A����ɐV���Ȗ�O�������v�悳��Ă���B����珔���ʂ̕�I�ȓ����ɂ���āA��萸���ő��p�I�ȕ������̒����҂����B
�����̕��@
�Ώےn��́A���V�A���C�n���A�n�o���t�X�N�B�A�T�n�����B�A�k�C������Ȃ���{�C�k���n��ł���B����X�V���̓��Y�n��́A�T�n�������A�k�C���A�瓇�������ɂ���đ嗤�Ɛڑ����A�����ԁA�u�ÃT�n�����|�k�C���|�瓇�����v���`�����Ă����B�܂����V���ƈႢ�A���Y���̋C��A�i�ρA�A�����A�������͂悭���ʂ��Ă���B����ɁA�����̐l�ޕ����́A�����̒n��ōL��������W�J���Ă������Ƃ�����������B����܂œ��Y�n��S�̂��J�o�[���錤���͂Ȃ��������߁A�{�����͑傫�ȈӋ`�������̂Ɨ\�z�����B
��̓I�Ȍ����ɂ��ẮA����X�V���̊��{�C�k���n��ɓW�J�����l�ސ��Ԍn���A���̍\���v�f�i�����v�f�A�������v�f�A�A�����v�f�A�i�ϗv�f�A�C��v�f�j�ɕ����č�Ƃ�i�߁A�V�X�e���_�̃t�H�[�}�b�g�Ŋe���ʂ����A���Y�n��̐l�ސ��Ԍn�̋ύt�ƕω��Ɋւ���]���������Ȃ��B�P�ɂ��ꂼ��̐��ʂ��ŏI�I�Ɏ������̂ł͂Ȃ��Ƃ���ɖ{�����̓��F������B
�e�����Ώۂ́A�n���w�I�Δ�̕��@����{�Ƃ��A�e�t���N���m���W�[�AAMS�N�㑪�蓙�̋��ʂ̕�������p���邱�ƂŁA���݂ɑΔ�\�ȃf�[�^��~�ς���B�Ȃ��A�A�����̌����ɂ��ẮA�Ð��ԃO���[�v�ɂ�錤���ۑ�ƃ����N���邽�߁A���ڂȘA�g���Ƃ��Č����𐄐i�����Ă����\��ł���B
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
�l�ޕ����Ǝ��R���Ƃ̊ւ��́A�l�Êw�̎�v�Ȍ����Ώۂ̂ЂƂƂ��Ď��H����Ă����Ƃ���ł��邪�A�ߔN�̌Ê������̒������i�W�ɂ���āA�ߋ��̎��R���ւ̐l�ޓK���Ɋւ����荂�𑜓x�̋c�_���\�ɂȂ����B
����X�V���̑S���I�ȋC��ϓ��ɔ����A���{�C�k���n��̐A�����E������������܂ōl�����Ă��������}���ɕϓ����Ă������Ƃ��A�ߔN�̌����̐i�W�ɂ���Ďw�E����͂��߂��B���Y�n��ł́A���⊣���ȋC���r�I���g�����ȋC��ւƎ����ɂ���ĉ��x���ω����A���A����������ɔ����ē���ւ���Ă����\�����������Ƃ����炩�ɂ���Ă���B
����A���{�C�k���n��ɓW�J�������Ί핶���́A�{�B�ȓ�̋��Ί핶���Ɣ�ׂāA����n�E����g���E�Ί�^���ȂǗl�X�ȓ_�ň�Ղ��Ƃɕψق��傫���Ƃ��������������Ă���B���̈�ՊԂ̕ψق́A�܂��N��I�ȈႢ�Ƃ��Ĕc������Ă��邪�A���Y�n��̒��Ŕ�r�I�L�x�Ȓ�����������k�C���ł̐�s�����A���Ȃ킿�l�È�Ղ̒n���ҔN�A�������ϑJ�A�A�����ϑJ�̑Δ䂩��́A���R���̕ω��ɑ��ւ��ĐΊ�Q���ω����Ă���\�����w�E����Ă���B���̂��Ƃ́A���{�C�k���n��̋��Ί�l���{�B�ȓ�ƈقȂ鎩�R���ɓK�����邽�߂̍s���헪�Ɛ����V�X�e����L���Ă������߂ł���Ɨ\�z�����B
�������A�k�C���̋��Ί핶�����l�X�ȕψق������Ƃ̌������A���ׂĎ��R���̕ω��ɋA�������Đ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���邪�A�傫�ȉe����^���Ă����ł��낤���Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B�����Q�n���߂܂��邵������ւ���Ă����ƍl���������X�V���̖k�C���Ŋ��Ɛl�ԂƂ̑��݊W�̌�����i�߂邱�Ƃ́A���ϓ����l�Ԃ̐����ɗ^�����e����K�͂ōl���Ă��������ł���߂ďd�v�ł���Ɨ\�z�����B���������������̔w�i���ӂ܂��A��萳�m�ŋ�̓I�Ȍ�����ڎw���Ƃ���ł���B
�k�C���ǁ`�X�т��߂���l�ԂƐ��Ƃ̑��ʓI����
���[�_�[�F �c���@���� �i�_�ސ��w�o�ϊw���A���{�o�ώj�j
�L�[���[�h�F �k�C���A�Ê��A��j�����A�L�ˁA�A�C�k�A�J���A���ƁA���t�E�͔ȗ�
�����ړI�Ɠ��e
�k�C���͍ŏI�X�͊��ȍ~�A���g�E����̊��ω��ƒn����̕ω����o�����A���A�����⑱�ꕶ���ɂ����Ă̎�E�̏W�����A����ɌÑォ�璆���̕������Ղɂ� ��ڂ��e���͑傫�������B�Ƃ͂����A���Ƃ��ƖL���Ȏ��������n�ł��邪�䂦�ɁA�ߐ��ɂ͂����ɋ��Ƃ�ړI�ɂ����a�l�̏o�҂���ڏZ���i�݁A�A�C�k�̒n�� �Љ�̕���̊�@�������炵���B���̈���ŁA���l���̉��H�R���i�Y�����Y�R���Ȃǁj�⍫��ޗ����͂��߁A�Z���d�Y�Ȃǂ̖؍ގ��v�̍��܂���������A�ޖ� �̔��̂��A�������ɉ�������Ă������B���R�A����ɂ��X�ѐ��Ԍn�Ƃ���ɔ����������Ԃ����ς��Ă������B�C�݂�͔Ȃɂ�����X�сA�����鋛�t�сi�����тȂǂ������̖��̂�����j��͔ȗт̔��̂ɂ�����ׂ���E���Ȃǂ��͊������Ƃ����Ă���B�ߔN�ł͂��̔��Ȃ���A��ɋ����̕w�l���𒆐S�ɐA�����i �߂��A���܂�s���̌㉟���������āu�k�̋����сv�Ƃ����ӎ��̂��Ƃɉ^�����W�J���Ă���B�����Ŗk�C���ǂł͐�j�`�ߑ�́u���Ƃ̓W�J�ƐX�ѐ��Ԍn�̕ω��v���ۑ�Ɍf���A���Ƃ̓W�J�ɔ������l�����H��l�Ԑ����ɂ����ċߗׂ̐X �ю������ǂ̂悤�ɗ��p����A����ɔ����ċ��Ǝ�����X�ю������ǂ̂悤�ɕω����A���̌��ʁA�X�ѐ��Ԍn�Ƌ��L�ނ̐��Ԍn���ǂ̂悤�ɕϗe���Ă����̂��� �ǁA�����̑��l���̊ϓ_����ߋ��A���݂ւƃA�v���[�`���A�l�Êw�A���j�w�A�����w�Ȃǂ̊w�ۓI�Ȍ�����i�߂�B���Ȃ킿�A���̒n��̐�j����̈�Ղ̗��n ����L�˂Ȃǂ̍l�Êw�I�����̕��͂���ߋ��̐l�Ԋ����ɂ��ĕ������A�ߐ�����ߑ�̐l�Ԃ��ւ�鐶�Ƃ̑��ʓI�Ȋ����̔�r������i�߁A���̐��ʂ��ߖ� ���ɂȂ�����̂ɂ������B
���̉ۑ�Nj��ɂ������Ă͓��ʁA�ϒO��������]�s�E���M�n��ɂ����Ă̎��R�Ɛl�Ԃ̂�������A�k�C���J��ƒn�拙�Ɓi��̓I�ɂ͍��A�ׂ� �ق��̋��Ɓj�A�X�ї��p�̗L�@�I�E�ۑS�I�W�ɏœ_�����āA�����������Ǝv���B�������A�ۑ�͂���݂̂ɗ��܂�킯�ł͂Ȃ��B�����Ώےn��ɂ�����l�� �\���R���݊W�̍l�Êw�I�E�����w�I�l�@���i�߂Ă���A�����̌�������V���ȗ��j�I��������������A�����̗��j�I���P�����邱�Ƃ��ł��A���o�ł������j �I�������u�����ȗ��p�v�������̂��ǂ��������炩�ɂȂ�ƍl������B
���t�тȂǂ̐X�ю����̕ۑS�Ɨ��p�Ɋւ��ẮA���̐A���^���Ȃnj��ォ�疢���Ɍ������ۑ�ɑ��ʓI�Ɋ�^�ł�����̂Ǝv����B
�����̕��@
�k�C���ǂ͓��ʁA���M�E�]�s�n����d�_�n��Ƃ��Č�������B���̒n��͊L�˂Ɍ�����悤�ɁA�ڈ�鸂��͂��߂Ƃ���L�ނ��l������ŁA�ߐ��ȍ~�A �ׂ���A���A�L�A�C�l�Ȃǂ̗D�ǂȐ��Y�n�тƂȂ��Ă���B�܂��A���M�͉ڈΒn�̒��ł͈�ԑ��������ƂȂ�A�����ȍ~�͊����A�i�z�g�J�A�E���W�I�X�g�b�N�� �̖f�ՊW����}���Ɏs�X�������n��ł���B�`�p�����ɂ���ĊC�ݐ����ω������B���̂悤�ȗ��j�I�ȓ��������n��ł���B�������A���̒n��ɂ͋ߐ����� �ߑ�܂ł̎��Ԃ�m�肤��Õ������������݂���B�{�����ł͂������������j���𒆐S�ɁA�l�Êw�▯���w�Ȃǂ̊w�ۓI�ȋ��͂ď��M�A�] �s�n��ɂ�����ۑ茤����i�߁A�ߐ�����ߑ�܂ł̐V���Ȓm���Ă������ƂƂ���B
�Ȃ��A�����̐��ʂ�n�}��ŕ\�������Ƃ��i�߂邪�A���̂��߂Ɍ�X���ȍ~�i�ߋ��P���N�ȍ~�j�̐ϒO�������ӂł̈�ՕϑJ�i�l�ԁ|�y�n���p�W�j�����A�������ɂ�����m�|�]�s�|���M�n��ł̊C�m�|�͐�A���Ȃ킿���������̕���Ɋւ���f�[�^���W�ς���B
�A�C�k�̊������߂����ẮA�]�ˎ���̉ڈΒn�̒����L�^�A���Ȃ킿�����j���̕��́A�ߑ㏉���̎��������̋L�^���́A���A���Ɛ����Ƃ̊W�������A�C�k��n�����͂��s�Ȃ��B�܂��A�A�C�k�����`���i���{��A�A�C�k��ɂ����́j�����́E��������B
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
�@ ���N�x�͗]�s���Y�����قƏ��M�s�����ق̋��͂̂��ƁA�Lj������ŗ]�s�E�m�E�Ԉ��E���M�����A��������s���Ă����B�]�s�́u�щƕ����v�A���M�́u����ƕ����v�u�R�ƕ����v�̌��J�E�{���������ł����B�A �����̏Ƃ���ɂ�鋙�l�̌����͓����̖������{�ɔF������A������b���]���B�������k�_�����i���k�C���������j��̊뜜�������āA���t�т��k�C���ɑ��鋙�ƂƗыƂ̐���ۑ�Ƃ��ďグ���Ă����j�������ꂽ�B
�B ��j����ɂ����ẮA�d�v�ȐH�Ƃ̈�ł���L�ނ̎����ɒ��ڂ��āA�{������i�߂邱�ƂƂ����B�L�ނ́A�C�i�A�C�ނɂ��C�m���̕ω��ɂƂ��Ȃ��q���ɐ�������ς��邱�Ƃ���A��j����̊L�˂��\������L�ނ̔�r�����������Ȃ����ƂƂ����B���ɁA�n�}�O���A�}�K�L�A�G�]�A���r�A�z�^�e�A�E�o�K�C�A���}�g�V�W�~�Ȃǂ��A�k�C���ł͎������Ƃɑ傫���ω��������Ƃ��킩���Ă����B����܂ŁA�]�s���Y�����َ����̎R�݃R���N�V�����A���|��Ղ̎����f�[�^���W�Ǝ����B�e�A�������������ُ����̖k�C���W�l�Î����̏����W�����{�����B
�C �ϒO�������ӂɂ��������ƈȌ�̎務�Ƃ̂P�ƔF�߂���X�P�\�E�L�������グ�A����A�O�R�̃X�P�\�E�L���֘A�����A�Õ����̏��ݒ����A�y�сA���W�ɂƂ߂��B�܂��A�t�B�[���h���[�N���s���A�X�P�\�E�L���̐��ڂ���Ԃ𑽊p�I�ɔc�����A��������Ƃ̊ւ������������B
�D �C�E��E�X�т̊֘A�ɂ��Ă̌����_���̏��ݒ����A�A�C�k�̗L�p�A���ɂ��Ă̌Õ����������s�Ȃ����B
�E ���t���тɊւ��鎑�������W�����B
���k�ǁ`���k�n���ɂ�����쐶�����Ɛl�Ƃ̂������̊��j?�k��R�n�̎���𒆐S�Ƃ���?
���[�_�[�F�r�J�a�M�i���������w�����فA�����w�E�n���w�j
�L�[���[�h�F���j�A�b�Q�A�j�z���U���A�N�}�A�I�I�J�~�A�n
�����ړI�Ɠ��e
���k�ǂł́A����E�̒��̓��k��A����{�̒��̓��k��Ƃ������_���ӎ����āA�쐶�����Ɛl�Ƃ̂������̗��j�i�Ƃ��ɁA�ߐ����猻�݂܂Łj�̕����Ɠ����̎Љ�E�o�σV�X�e���̉𖾂�ړI�Ƃ���B�Ƃ�킯�A�Ώےn��Ƃ��ẮA���k�n���̖k��R�n�Ƃ��̗אڒn��𒆐S�Ƃ��čl���Ă���B�Ȃ��A�����̒n��́A�]�ˎ���ɂ�����암�˂𒆐S�ɂ��āA���ˁA�H�c�ˁA�Ìy�ˁA���O�˂ɊY������Ƃ݂Ă���B
���łɁA�k��R�n�̌i�ςƂ��̐��藧���ɂ��ẮA�ߔN�A�����ꂽ�_���W�m��Z�ق���2005�w�X�̐��Ԏj�x�i�Í����@�j�n���o�Ă���B�{�����ł́A�쐶�����Ɛl�Ƃ̂������̗��j�ɏœ_�������Ă��邪�A���̗��j�͖k��R�n�̐X�т̌`���j�Ɛ[�����т��Ă���ƍl������B�Ƃ�킯�A�k��R�n�̐X�т̑�����2���I�A���i�ς���Ȃ邱�Ƃ�����A�쐶�����ɑ���l�ׂ̗��j�I��p�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��n��ł�����B�{�����ł́A��q�̖{�̓��e�̈ꕔ���z������̂���邱�Ƃ��߂����Ɠ����ɁA���{�S���ɓK�p�ł���悤�Ȗ쐶�����E�l�W�j�Ɋւ��n�惂�f���̍\�z�ɓw�߂�B
�����̕��@
���k�n���̂Ȃ��Ŗk��R�n�i���݂̐X���A��茧�A�{�錧�j���d�_�Ώےn��ɑI�ԁB���̗��R�́A�ȉ��̂悤�ɖk��R�n�̐l�b���j�ɂ́A�������ȉۑ肪�������c����Ă��邽�߂ł���B
�܂��A�ߐ��̓암�˂ł́A�k��R�n�Ŏ��{����Ă���n���I�I�J�~�ɏP���Ă��邱�Ƃ�����Ă���i�e�r�A���M�j�B���̌�A�����̏��߂ɂ́A�k��R�n�i��茧�j�ɂ́A�j�z���I�I�J�~�A�C�m�V�V�A�j�z���W�J�A�j�z���U���A�c�L�m���O�}�A�j�z���J���V�J�̂U��̑�^�M���ނ��������Ă����B�������������̏I���܂łɂ��̂����̃I�I�J�~�A�C�m�V�V�͐�ł��A�V�J�ƃT���͌���̌ܗt�R���ӂɌ���I�ɕ��z����݂̂ƂȂ�A�k��R�n�̑����̎R������p�������Ă��������Ƃ������Ă���i���A���M�j�B����������^�M���ނ̌����̌����ɂ��āA�l�X�Ȑ������邪�A���܂����炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B�܂��A�����̑�^�M���ނ̐����v���Z�X�Ƃ��̗v�����������f���́A���{�����̑��̒n��̖����l���邤���ŁA�d�v�ȎQ�Ƙg�ɂȂ�ƍl���Ă���B
���̈���ŁA�k��R�n�ɂ����铖���̎Љ�o�σV�X�e���̉𖾂��߂����{�����ł́A�Ώےn��������鎋�삩��̈ʒu�Â����s���ł���B���̂��߁A���k�����≜�H�R���̂悤�Ȓn��ł̖쐶�����E�l�W�j�̐��ʂƂ̔�r���d�v�Ȍ����g�g�݂Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă���B
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
2006�N4�����{�ɁA���k�ǂ̃����o�[���S���W�����āA���݂��̌����S�̂��肠�킹���̓I�Ȍ������e�ɂ��đł����킹�������B���̍ۂɂ́A�����o�[�̈ꕔ���G�R�\�t�B�A17���i2006�N4���A���a�����s�j�̓��W�u�z�����铮�������v�Ɋ֗^���Ă����Ƃ������Ƃ�����A���݂̏b�Q���̂���������_�ق��A���̕���Ɋւ���ŐV�̓��e���_�c���ꂽ�B
���̌�A�e�X�̃����o�[����̓I�Ɋ����ł��錤���e�[�}���������āA�e�������I�Ȍ������p�����Ă���B���̌����e�[�}�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@�e�r�E�v�F�w�k��R�n�̔n�i�n�Y�j�Əb�Q�ɂ���-�ߐ����̓암�ˁi�I�I�J�~�j�Ə��O�ˁi�N�}�j�̔�r����-�x
�A���@����F�w�k��R�n�̖쐶�����i�I�I�J�~�A�T���A�C�m�V�V�A�V�J�j�̏��łɂ���-�����E�吳���ɒ��ڂ��ā[�x
�B�O�ˍK�v�F�w�k��R�n�̃j�z���U���̕��z���ł͂Ȃ��N���������H-�吳�E���a���̓��k�n���̂Ȃ��ł̈ʒu�Â�-�x
�C�r�J�a�M�F�w�k��R�n�ɂ�����c�L�m���O�}�̏b�Q-���a�E�������ɒ��ڂ��ā|�x
�D���V�h���F�w���H�R�n�ɂ�����j�z���U���̏b�Q�̐��Ԏj�x
�ȏ�̂悤�ɁA�e�e�[�}�́A�ߐ����猻�݂܂ł̎��ԕ��ɉ����ĕ��ׂĂ���A�k��R�n�ڂɑΏۂ��錤���Ɩk��R�n�Ƒ��̒n��Ƃ��r������̂ɕ�����邪�A���҂̌����������邱�Ƃł�荂�x�ȓ����I�Ȍ����ɓ��B�ł���ƍl���Ă���B
�����ǁ`�����R�Ԓn��ɂ�����l�ԁ[���R�W�̕��݂ƌ���
���[�_�[�F �����@�q �i�����w�@��w�A���j�w�����{�����j�E�R���j���j
�L�[���[�h�F�@�R���E�X�ю����E����n��E���������E�Ĕ��E���
�����ړI�Ɠ��e
�����n���͓��{�̉���(���{�A���v�X)���\������R�x�n��𒆐S���Ɋ܂݁A���k�ɉ��f����[���R�n�тɕ���ꂽ�n�`������Ƃ���B�����ɓ��{�L���̑���n�тł�����A12������5���ɂ����Ă͐[����ɕ�����B����͖L���Ȑ��ɖ������ꂽ�X�ю����̟��{�ɂ��Ȃ���B�L�x�ȐX�ю����͂܂����l�ȓ��A����������݁A�����͐l�Ԑ����Ɛ[���ւ��������Ă���B
�����ǂł́A���Y�n�������Â���R�n�̐����ɏœ_�āA�����Ŏ��R�����ǂ̂悤�ɗ��p����A���ς���Ă������A�܂��������p�ɑ��Đl�ԎЉ�ǂ̂悤�ȃ��[���E�K�����\�z���Ă��������𖾂��Ă��������ƍl���Ă���B����͂Ђ��ẮA�R�n�����̎����I�A���邢�͋t�ɒf���I�ȗ��p�ɁA�l�ԎЉ�ǂ��ւ���Ă��������������������Ƃɂ��Ȃ�B
�����܂ł��Ȃ��������钆���n���̎��R���́A�l�ׂ�r���������R�I�J�ڂ̌��ʂł͂Ȃ��B�����Ɍ�����̂́A�L�j�ȗ��A�l�Ԃ����R�ɑ��ċy�ڂ��Ă������܂��܂ȉe���̕\��ɂق��Ȃ�Ȃ��B�ł͗��j�I�ɐl�Ԃ͂ǂ̂悤�Ɏ��R�ƊW�������Ă������B���͗��j�w�̕���ł́A�R���̐��������ɂ��Ă̌����͑�ϒx��Ă���A���������R�����̂ɑ���]����S���͂Ȃ͂����������Ƃ����̂�����ł���B�����ΏۂƂȂ�j�����̂����e�I�ɂ��`���I�ɂ����n�ɕ������̂ƂȂ��Ă����̂����̑傫�ȗ��R�ł͂��邪�A���������̌��ʂƂ��āA�����w�E�l�ފw�ɂ�����R�n���������̌�������o�ϊw�E�n���w�E�Љ�w�Ȃǂ��炷��R���Љ�\���̌����́A�O�ߑ�I�ȎR�ю������p�̗��Â����m�Ǝ������Ȃ��A�ߌ�����Ǘ��I�t�B�[���h�Ƃ�����̂ɂȂ肪���ł������B�Ƃ��ɁA���암�Ɣ�ׂĂ��܂��܂Ȋ�I���Ƃ������I�ɉc�܂��R���̂�����́A���̓I���삩�瑨������ׂ����̂ł���ɂ�������炸�A�e����j�̑O�j�Ƃ��Ă͈̔͂ł݈̂����邱�Ƃ����������B�����������������߁A�O�ߑォ�猻��܂ł̕ϑJ����т�������̒��ɑ����邱�ƂŁA�����̎��R���������ɂ��Đ������Ă��������������������Ƃ��ł���悤�ɂȂ���̂ƍl����B �����ǂł́A���̒����Ώےn�Ƃ��ĐM�z�����ɂ܂�����H�R�n����Ƃ肠����B���n�̑I��͗��j�I�j���̑��l�Ȏc���ƁA���w�₩�炽�т��ъS�������Ă������������̈⑶�ɂ�邪�A���̒n�̌����ɂ������ē����Ƃ��ĔO���ɒu���ׂ����ۂ���������������B
�܂����ɂ́A���n�����{�L���̑���n�тł��邱�Ƃł���B���̂��Ƃ����n�̎��R��l�Ԑ����ɑ���ȉe����^���Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���ɁA�l�ׂƎ��R�̊W�ɂ܂����ł��邪�A���n������̎�̏�Ƃ��ď��Ȃ��Ƃ������O���ȗ������d�v������Ă������Ƃ���������B����R�̑��݂́A�l�Ԋ����̎��R�ȉ���������Αj�Q���邱�ƂɂȂ�A���ꂪ���Ӓn��ɔ䂵�Ď��R���̓��ٓI�Ȏc���܂��͓W�J�����\��������B��O�ɂ́A�������l�Ԑ��E�̖��Ƃ��āA���n���M�z�̍����Ɉʒu���Ă������Ƃ���������B���E�̑��݂́A�����̐l�Ԋ����Ɉ��̋K�����͂߂邱�Ƃ������A�����ɂ����Η����Ԃ̖��O�ǂ����̑i�ׂ��䂫�N���Ă����B
�����̏��v�f�����R�Ɛl�Ԃ̋�̓I�ȊW�A�Ђ��Ă͍����܂ł̎��R���̑J�ڂɂǂ̂悤�ȉe����^���Ă������͂��ꂩ��̉ۑ�ł��邪�A�������������I�Ȗ��_�ɗ��ӂ��Ȃ���W�L�̖ړI�ɋ߂Â��Ă��������ƍl���Ă���B ���j�w����і����w�̕���Ɋւ��Ă����A���łɂ���܂łɐ��N�����\�N���x�ɂ킽�鎑�j���̒~�ς��o�Ă���A����T�N�ԂƂ��������������ԂŁA���݂Ɏc���v�Ȍ����f�ނ͎��W���I���邱�Ƃ��T�ˉ\�Ǝv���A�W�L�̉ۑ�ɔ��镪�͍͂s������̂ƍl������B
�����̕��@
�����n���R���Ƃ����Ă��A�삩��k�܂ő��l�ȓ����������Ă���A�K��������T�ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�{�����ł́A���t�B�[���h�Ƃ��Ē��쌧�������S�h���H�R�n��Ȃ�тɗאڂ���V�����������S�Ó쒬�H�R�n������グ���B���n�I��̗��R�́A���q���ォ��]�ˎ���Ɏ���O�ߑ�j�����H�L�Ȍ`�ł悭�c����Ă��邱�Ƃ���Ƃ���B���Ȃ킿�A���q�����k���E�����Ɏ���ݒn�̎�̓����������Ɏ����M�d�Ȏj���u�s�͕����v������A����ɋߐ��Ɏ���A����ɏH�R����T�Ԃ����ē������A���̐����������ڍׂɏ����c������ؖq�V�u�H�R�L�s�v�����s����Ă���B�܂��A�M�Z�H�R�n����NJ������ߐ��̖��쑺���哇�c�Ƃɂ́A�ߐ�����ߑ�ɋy�Ԑ���_�̌Õ����Q���c����Ă���A�H�R�Ȃ�тɎ��Ӓn��Ɋւ���M�d�ȏ�����Ă����B���쑺�Ǔ��̎}���ɂ��֘A�j�����������̂܂c����Ă���A�����𑍍����邱�ƂőO�ߑォ��ߑ�E����܂ł̑��̓I�Ȏ������p�E�Љ��̗l�������炩�ɂł���ƍl������B�܂��A�����w�E�n���w���Ɋւ��Ă��A���n�͒����n���̑�\�I�R���Ƃ��ČÂ�����S�̑ΏۂƂȂ�A�����̌������~�ς���Ă��Ă���B�Ƃ��Ɏ�Ɋւ��ẮA�`���I�Ȏ�������p������t�����݂����݂ł��邵�A�R�E�����̎������p���̂��͐������Ƃ͂����A�����������Ă���B�Ȃ��A��r�����̍ۂ̃T�u�t�B�[���h�Ƃ��āA�����n������̎R���n��ł���R�����싐���S���쒬������ɓ���Ă���B�����͓�A���v�X�ɓ��ڂ���і엦95�p�[�Z���g���鎩���̂ŁA�H�R�Ɠ������k�J�����ɗ��n������ɂ���B����R�����݂���ƂƂ��ɁA�ыƁE�Ĕ�������ɍs���A����p��������s���Ă����B���n�ł͑O�ߑ�j�������ł�16�N�ɂ킽���Ē������Ă���A���x�̎j���~�ς�����B
�����ɂ������ẮA�܂����Y�t�B�[���h���ǂ̂悤�Ȓn�`�I�����������A���̒��Ől�̋��Z�n���ǂ̂悤�ȕ����ɊJ����Ă������A�܂��ЊQ�����Ƃ̊W�ŏW���ړ����������̂��ǂ����A���Ƃ̓W�J������ƒn�`�I���F�Ƃ̊֘A�Ȃǂɂ��Č������s�����߁A���R�n���w�I��@�ɂ�钲����i�߂�B����ɁA���j����ɂ�����R�쎑���̗��p�Ƃ���ɑ���Љ�I�K���A���邢�͐��Ƃɂ܂��̎�ƍݒn�Ƃ̔�E�v�[�̊W�Ȃǂ���j�w�̕��삩�猤������B�ߑ�ȍ~�ɂ�����R�쎑���̗��p���̐��������ɂ��ẮA�����w�E�l�ފw�I��@�ɂ���ĉ����������ƂƂ��ɁA����Ɛ[���A�g���Ȃ��琧�x�I�E�Љ�I�ȑ��ʂ��܂߂Đl���n���w����o�ϊw�̕��삩�猟����������B
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
�����R�n���w�������n��̒n�`�E�n���T�v��c�����A�n���ׂ�n�`���z�}�y�ђi�u�ʋ敪�}���쐬���邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��A�ʐ^�����E���ǂ��A�܂����n�ώ@�ɂ���č�Ƃ�i�߂��B���̌��ʁA�n���ׂ�u���b�N���ɋ��݂��閄�v�i�u�I�w�̑��݂������n�_���m�F���ꂽ�B�܂��A��ԑ��ÁE��R�q�g�Ƃ݂���L��ΎR�D�w�̕��z�������n����̒i�u�ʏ�Ŋm�F�ł����B�N�x���܂łɏ�L2�}���쐬�̗\��ł���B
�����j�w���s�͕����y�ю�����Ɋւ����s���������E�������A�j���Ɍ�����n��̌i�ϊώ@�����{�����B�܂����ł�6�N�ɘj���đ����Ă��铇�c�ƕ����̒������p�����čs���A����R�G�}���܂ދߐ��G�}�ށE�ߑ�j���ނ��B�e����ƂƂ��ɁA�ߗׂ̍֓��ƕ����̒����ɂƂ肩����A����R�W�j���̑��݂��m�F�����B���c�Ƃ���͋ߐ��ߑ�ڍs���̎R�n���p�ԗl�̕ω����������������o�����Ƃ��ł����B
�������w�E���Ԑl�ފw���H�R�W�̖����w�����̒������s�����B�܂��t����̕�����蒲�����p�����A�ߔN�̌F�ߊl�Ǝ����Ǘ��̖��_�𒊏o�����B�F�͑O�ߑォ�瓖�n�ɂ�����d�v�Ȏ�����ł��邪�A�Ƃ��ɋߔN�A�t�ւ̕ߊl�����ƁA����ɖ�������B㩂ɂ�闐�l�̖��̂��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B
�����o�ϊw�����݂̎������p�y�ю����Ǘ��̏ɂ��āA����ł̕������ƃf�[�^����ɂ���Ċm�F����ƂƂ��ɁA�ό��E�R�ؗ��p�E��E���L�тȂǂ̃L�[���[�h�Ɋւ��ߔN�̎������p�W�_���̎��W���s�����B�܂��A���n�ώ@�ɂ���čs���f�[�^�╷�����������n�ɒ������A�k������n�̌�����t���m�F�����B
���l���n���w�������@���ǂɂ����ēy�n���p�W�̃f�[�^�����W����ƂƂ��ɁA�e�W�������Ċ�b�f�[�^�̎��W���s�����B�܂��A���n�ł̕�����蒲�������{���A�ߌ���ɂ����鐶�������̑傫�ȕω��̗v�f���m�F�����B�і쏊�L�W�}�A���L�n�ʒu�}�A�W���ʍ�t�ʐϐ��ڐ}���쐬�����B
�ߋE�ǁ`�A���������p�̎��ԉ𖾂��߂�����-���ɖG�藘�p�Ǝ{�Ƃɂ����`��
���[�_�[�F ��Z���� �i�X�ё����������E���x���A���сE���Ԋw�j
�L�[���[�h�F�G��A���R�A�y�n���p�A�A���������p�A�ߐ��E�ߑ�
�����ړI�Ɠ��e
�ߋE�ǂ͌����e�[�}�Ƃ��āu�A���������p�̎��̉𖾁v���f���A���̒��ł����ɖG�藘�p�̌`�ԂƖG��ю{�Ƃɂ����`���ɒ��ڂ��āA������i�߂�B
�W�����ӂ̐A�������́A�l�X�Ȗ���ɗ��p����Ă���悤�ɓ���̐����̒��ŗ��p�����ƂƂ��ɁA�؍ށA�d�Y�A�܂����p�юY���Ƃ��Č��Վ�i�Ƃ��Ă��p������B�����ɁA�X�т͒n��̊���ՂƂ��đ傫�ȉe���������߁A���̂ɔ��������̋K�͂⎞���A�Ԋu�A���̌�̊Ǘ��Ȃǂ̂�����͒n�搶�Ԍn���K�肷��v�f�ƂȂ�B
�܂��A���R�d�Y�тɑ�\�����悤�ɁA���p�����A�������́A�G��тƂ��ĊǗ��������̂������B�G��̗��p�́A���肵�����Y���\�ɂ��邾���łȂ��A�����ɔ�ׁu�߂̏��Ȃ��v�ނ̐��Y��A�@�ے��̒����A���̂Y�ł���Ȃǎ��I���P�ɂ����ʂ�����A�܂��A�ׂ��G��}���ʂɗ��p����ꍇ�Ȃǂɂ́A�����̂��̂��ʂɗp�ӂ��邱�Ƃ��ł���ȂNjK�i���̖ʂł����ʂ�����B�����Ȃǂŕ�����鎿�̂悢�ޗ��̑I���Ȃǂ́A�����ΖG��}���W���Ă��邱�Ƃ�����B
�ߋE�ǂ͐A���������p�ɂ��āA1�j�����ǂ̂悤�ɗ��p�����̂��Ƃ������C���x���g���[�I�������͂��߁A2�j�̎�E�Ǘ��Ɋւ�����i�����̎��j�A3�j���p�̋K�́i�����̋K�́j��c���A���m�������邱�Ƃɂ���āA�ŏI�I�ɂ͂����̗��p�ɂ��ǂ̂悤�Ȑ��Ԍn���\�z����Ă����̂�������ڎw���B
���������́A�����A�����Ƃ��ɗ��p���₷���ߐ��E�ߑ�ɂ��ċ�̂̏W����ΏۂɌ�����i�߂Ă������A�ߋE�͖퐶�ȍ~���ɐl�Ԋ������Z���ɉc�܂ꂽ�n��ł�����A�����̎���ɂǂ̂悤�Ȑ��Ԍn�������\�Ȃ̂��ɂ��Ă��Ð��ԔǂȂǂƘA�g���Ď��g��ł��������ƍl���Ă���B
�����̕��@
�ߋE�́A���E���s�E�ޗǂƂ����Â�����̓s�s�����A�W���͗��n�ɂ���ēs�s�Ƃ̊W���قȂ�B�s�s�Ƃ̌o�ϓI�Ȍ��т��̒��ŐA���������p�͑傫�ȉe�����Ă���ƍl�����A���̂��Ƃ������邽�߂ɁA���n���قȂ邢�����̒����n�Ŋe�Q���҂��ςݏd�˂Ă������ጤ����[�߂�r���Ă������Ƃɂ����i�}�Q�Ɓj�B
�����n�͂�������ߋE�ǎQ���҂�����܂ł̌���������ʂ��ăx�[�X���������Ă���ꏊ�ł���A�����̏ꏊ�ɑ��݂ɏ���������A��r������i�߂Ă��������Ƃ����B
�E�}���A�Ăւ̈ˑ��̑召�͔_���I�v�f����R���I�ȌX�����A�s�s�Ƃ̋����͌o�ϊ����ɂ��e���╨���A���̂��₷���f����A�w�W�I�Ȃ��̂Ƃ��Ď������B
�����̊e�n�ɂ����āA�������E�����E����Ȃǂ���A���������p����̓I�Ɋm�F���A�N��ƂƂ��ɁA�����̗l���⎞���A�Ǘ��Ȃǂ��L�q����B���p�̍��Ղ���Ԃ����n������Č������ɂ��m�F�ł���ꍇ�ɂ͐A�������A���p�ʐ���Ȃǂ��s���A�����ɔ������Ԍn�ւ̉e���𐄒肷��B
���ɁA���i�A����A�Ɖ��Ȃǂ͍ޗ����m�F���A�ǂ̂悤�Ȏ��̍ނ��D�܂�Ă��邩�ɂ��Ē�����i�߁A�G��Ǘ����p�ɂ��Ă̎����W����i�߂�B
�܂��A�����̗��p�͐A�����̎�����f���Ă��邱�Ƃ���A�G�������A�G��}�������̖؍ޑg�D�Ɋւ��錤���A��������Ƃ̔�r�Ȃǂ��s���B
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
�㐢���͐[���E���E��V�{��A�u�꒬�͑�Z�E�x����A����ނ͍��v�Ԃ炪���ɒ����n�Ƃ��Ċ������Ă����ꏊ�ł���A�����̎��W���i��ł���B
2006�N�x��
��B�ǁ`��B�����R�Ԓn�тɂ�����l�ԁ\���R���݊W�̗��j�I�E�����I����
���[�_�[�F�@ �я����i�i�ʕ{��w�@�����j�w�j
�L�[���[�h�F�@��A�X�A�Ĕ��A��Ă��A���c�J��
�����ړI�Ɠ��e
��B�ǂł́A���h�E�����E�����イ�̔����A�R�[�A��n�������t�B�[���h�ɐݒ肵���B���̒n��́A���h�𒆐S�Ƃ���ΎR�����̌��ʁA��K�͂ȃJ���f���~�n�A�L��ȑ�n�n�`�A���B��������Ȕ����n�`�ȂǁA���l�Ȓn�`���������Ă���B
�����ŁA�Â�����̐l�X�́A���̒n�`���E���R���ɍ��킹�Ȃ���A�������c��ł����B���̎��R������Ɠ��̓y�n�̗��p�@�����W�����B���̈����p�����y�n���p�@�ł���B�Ă����A��Ă��Ȃǂ�����ł���A�����ɂ́A���A���q�A����ȂǗl�X�ȗ��p�@������A���̂��Ƃ��A�����Ɏ���܂ŁA�Ǝ��ȑ��������`������v���ƂȂ����B������́A�L��ȎR�n�̂����炷�L�x�Ȓn�����𗘗p����y�n���p�ł���B���ꂪ��n������̉���J���f���~�n�ɐ��c���`�������A�₪�āA�Ζʂɂ��I�c���J���������B
�܂��A�����̐l�ԂƎ��R�̊W���Ǝ��ȐM�`�Ԃݏo�����ƂɂȂ�A���h�⍂���A�����イ�ɂ͓Ǝ��ȐM��������B
�{�����ł́A���j�w�A�l�Êw�A�����w�A�n���w�A�A���w�A�n���w�Ȃǂ̏�����̊w�ۓI�ȃA�v���[�`�ɂ���āA���̒n��ł̐l�ԂƎ��R�̑��݊W����j�I�E�����I�Ȗʂ���𖾂��悤�ƍl���Ă���B��B�ǂ̎Q���҂́A�u�l�ԁ|���R���݊W�̗��j�I�E�����I�����v�Ƃ������ʂ̔F���̂��Ƃɂ��ꂼ��̐�啪�삩�狌�Ί킩�猻��Ɏ��鎞�Ԃ̒��Ō����������A��������}��B
���҂ł��鐬�ʂƂ��ẮA
- �����n��̃{�[�����O�┭�@�����̒��ŁA�v�����g�E�I�p�[���A�ԕ��Ȃǂ̐A����̂̕��͂ɂ��A���Ί펞�ォ�猻��Ɏ���A�����̕ω��𖾂炩�ɂł��邱�ƁB
- �����I��Ă��ɂ���āA�ɂ��A���ω���ǂ��A�l�H�I����ƌ`���Ǝ��R���̊W�𖾂炩�ɂ��邱�ƁB
- ���j�����A�n�������A���������Ȃǂ̏N�W�E���͂ɂ���ĎR�x�n�т̎R�엘�p�̗��j�E�����𖾂炩�ɂ��邱�ƁB
- �R�x�n�т̒n�����A�N���A��Ȃǂ̒n���w�I�����Ƃ��炵�̒��ł̐����p�i��ˁA���c�̐����A���H�A���c�Ȃǁj�̒������s���A�B�Ƒg�ݍ��킹�Ȃ���A���Ɛl�Ԃ̂��炵�A���̗��j�I�A�����I�������s�Ȃ����ƁB�_�ЂȂǂ̐M�ɂ����ӁB
�����̕��@
�����イ�E���h�E�����
�@�A���E��
�����E���ԁ|�c��i�璬���c�j�|���̌Ó������ɂ����āA�{�[�����O�����������Ȃ��B
-
����18�N�x�@�����ՁE�Γc��ՁE�{����_�Ё@�i�|�c�s�v�Z�j
-
�B��猬��ՁA���Έ�ՁA�k������Ձi��d���j
���쐣�ˁA�R�z�x�o�R�������@�@�@�@�i���z�@���j
�����i�I�c�E��_���_�Ёj�n��@�@�@�i�ʕ{�s�j
-
�����S�@�i�|�c�s�������j
������n�i�|�c�s�j
����n�@�i�|�c�s�����j
���h�n���i�F�{�����h���Ȃǁj
���n���f�[�^�Ɛ����̒����i�ߋ��n���f�[�^�̏N�W�j�E�����̒���
-
��d�����ݍ̐_��ՁE���c����Ղ̔��@����
-
�̐_��Ձ@�@�퐶�E����
���c����Ձ@�@�Ñ�E�E�E�����`���Ƃ̊֘A���i�c����łƍĊJ���j
-
���ЊQ�l�Êw���̌��n
���l�Êw�I���@�������āA�璬���c�~�n�̔��@�����������Ȃ�
-
�����a�l�E���c�@�B�@�@�ЊQ�ƐA���̕ϓ��@�@�@�@��Ă��ƐA���̊W
-
���쐣�˒n��ɂ����āA�����I�u��Ă��v��2006�N2������5�N�Ԃɂ킽����{���A�u��Ă��v�ƐA���W���i�{�����͑啪�����{�̒����ł��邪�A�Q���j
-
�F�{��w�t�c�ǁ@�@���h�J�̏���n��𒆐S�ɐ����A�n���̒������s�Ȃ��B
�ʕ{��w�я��ǁ@�����イ���ӂ̐����p�A���c�J���̒����@
-
�ʕ{�s�����n��A�|�c�s�{����A�|�c�s�����n��A��d���c��n��A��쒬���ؒn��
-
�i��B�Y�@�@�@�����イ�A�R�Ɣѓc�����̓y�n���p�̖���
�i���@�ց@�@�@���h�ƒŗt�̔�r
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
- �l�Êw����
-
�̐_��Ղ������͖��c����Ղ̔��@�������s�Ȃ��ɓ������āA���������̂��߂̗\�����������{�����B�̐_��Ղɂ����ẮA�퐶����E���q����╨��\�ʍ̏W���邱�Ƃ��ł����B
���c����ՂɊւ��ẮA��d��⣂̌��n��ɂ����āA�\�ʍ̏W���������w���A�Ñ�̈╨���m�F���邱�Ƃ��ł����B���c����Ղɂ����ẮA�ߋ��ɑ啪�����璡�ɂ�蔭�@���������{����Ă���A��͂蓯�����Ñ�̈╨���o�y���Ă���B����āA�����`���Ɋւ��鎞���̈╨�邱�Ƃ��ł����Ղƌ����Ӗ��ł͏d�v�Ȃ��̂ƂȂ�B - �{�[�����O�E�Ê�����
-
10���̌�����Ń{�[�����O�����̈ʒu�����������B��Ղ̃f�[�^�̂���n��ɂ���Ώ��Ȃǂ̐Ղ�D�悵�A�I�肵���B
�ˋ@�B�{�[�����O�@�璬���c�A�{����A
�ˎ�{�[�����O�@���x�E�ѓc�����A�H���n�w
�@�ߋ��̃{�[�����O�E�Ê��̒����f�[�^���N�W����B
- �����j�w����
- �����n�撲���@���j�A�����E���c�\�������A�[�R�ˏĂ����˔��˒I�c�ƎR�엘�p�̕ϑJ�E�J���̗��j��z�肷��B
-
�{����n��@�@���Ǝs�̊W�D�{����_�Ђ̎s�i�������s�j�Ɠ��Ƌ��E�A��ƊقƎs�̊W���@
���h����n��@�����E�n�������D���h�J���f�������n�̊J���ߒ��E�q�Ɛ��c�J���̊W
�����E����ǁ`�����ʂɂ����鎩�R�������p�̗��j
���[�_�[�F ���k �V�n �i�R��������w�C�l�ފw�j
�L�[���[�h�F�����x�̋ʐ^�A���R�������p�̗��j�A�łƌ��ՁA�T���S�ʁA���R�E�K�C
�����ړI�Ɠ��e
�����E����̓����ł���A�������M�т̓��ׂƂ��������̂��Ƃɐ����������j�[�N�Ȑ������l���ƁA���Ƃ��Ύ������Ȗk�̂��ׂĂ̏����������傫�ȑ�������̓����ɂ������������ɂ݂���A���R�ƕ����̑��l���Ƃ��̐����̉ߒ��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ������̖ړI�ł���B
��̓I�ɂ́A�����哇�Ɖ������т��̎��ӂ̓��X�������ΏۂƂ��āA�����ʂɂ����ď��Ȃ��Ƃ�10�N�A�ł����20�N�ȏ�̌o�������l�𒆐S�Ɍ����`�[����Ґ����A�n���哱�Ŏ��R�╶���̌��������Ă������ʂȃO���[�v�̐l���Ɛ��ʂ�������\�����߂����B
�����Z���I�Ȍ����̎��ۂ��o�����A���n�挤���̃������ɂ��āA�S�����s���K�͂����L���邱�Ƃ��߂����āA���h�`���ɂ�鋤�����������N�x�ɐݒ肵���B�ċG�́A�����哇�A�~���͉���k���ł̋������������{����B �@�S�̂Ƃ��Ă̗Z�����߂����A�e�l�������Ȃ������̃��C���e�[�}�ƁA�A�g�̂��߂̃O���[�v�e�[�}��ݒ肵�Ă����B�ȉ��Ɏ����̂́A�ʌ����̃e�[�}�̗�ł���B
���R�����������[�_�[�Ƃ��A�A���w�̐������O���Ɠ����w�̑��Ύ������̋��͂āA�u�ʐ^�ɂ��y�n���p�ƐA���̕ϑJ�v�̌����������Ȃ��B����́A�ŋ߂ɂȂ��ė��p���\�ɂȂ����A1945�N�O��ɕČR���B�e����5000����1�k�ڒ��x�̍����ׂȋʐ^�����p���錤���ŁA�����哇�ł́A��a���Ɖ��v�C�ԓ��𒆐S�ɒ����������߁A����ł́A�]��������i�߂Ă�������x����сA���炽�ɉH�n��여��𒆐S�Ƃ����n��œ����ƕ������ɂ�钲�����s���B�܂��A����k���ɂ����ẮA��O�̔_�k��R�̗��p��̌��������X�̕�����蒲�����}���K�v������A�����̒��������s���čs���B
�n�v�n�����́A�u�T���S�ʒn�`�Ɩ����m���v���e�[�}�ɁA�T���S�ʂƂ����A���{�ł͉����E����ɏW���I�ɑ��݂��郆�j�[�N�Ȑ��Ԍn�Ɛl�Ԑ����Ƃ̂������𖾂炩�ɂ���ׂ��A�C�̒����ƁA�W���ɂ�����Ί_�̍ޗ������ȂǁA�T���S���p�̎��Ԕc����i�߂Ă����v��ł���B�����哇�≫��̂悤�ȍ������Ǝ��ӂ̒Ⴂ���̑Δ������ɂ���Č�����i�߂�B
�؉����q���́A�ߔN�������ꂽ�A�����ɂ�����7�`9���I�̃��R�E�K�C��ʏo�y��Ղ̕��͂�ʂ��Ă��̓��e��c�����A�����̗��j�����Ȃ���A300�N�ɂ킽�问���l�̃��R�E�K�C�������p�̎��Ԃ�c�����邱�Ƃ��߂����Ă���B�����̏o�y���R�E�K�C�̑S�����������āA���̃T�C�Y�𑪂�Ƃ������،�����W�J����B ���������́A�����w�̕������߂�������܂ł̋���E���������̐��ʂ��ӂ܂��āA�~���đ��ȂǁA�����ʂł͂���܂łɂ��܂蒍�ڂ���Ă��Ȃ�����������̕��z�ɂ��Ă̌�����i�߂�ƂƂ��Ɂu�����E����̐������l���Ɛl�Ԑ����v�ɂ��ẮA�r�W���A���ȋ��ނÂ����ʂ����u���R�ƕ����̌����ȗ��p�v�ւ̈ӎ������߂���w�K�̉\���ɂ��Ă̌�����i�߂�B
���k�M�q���́A�u�����ʂ͔̍|�A���Ɨ����̑̌n�v�����C���e�[�}�ɁA�\�e�c�Ȃǂ̓Ŕ����Z�p����Â���Ȃǂ̔��y�Z�p���A���{����ѐ��E�̋Z�p�̒��ł̃^�C�|���W�[�ƌn���I�Ȍ������s�����ƂŁA�����E����̃��j�[�N��������ɂ��邱�Ƃ��߂����B
���k�V�n���[�_�[�́A�S�̂̓������s���ƂƂ��ɁA�u�����ʂ̌��Ճl�b�g���[�N�̗��j�I�����v���e�[�}�ɁA�����ł̍����v�����e�[�V�����J�n�O��ł́A���X���������̕ω���A����Ɖ����암�̓��X���������o���D�Ȃǂ̒��������Ղ̗��j�Ƃ������A�ߑォ��ߐ��ɂ����Ă̐łƌ��Ղ̖����𖾂���B
傌��ꕽ���́A���\���ɂ�����C�m�V�V�̌�����i�߂Ă��邪�A�u�����ʂɂ�����C�m�V�V�̗��j�v���e�[�}�ɁA�����哇�E����ł��C�m�V�V�̎��ؓI�����������߂āA���{����ѐ��E�̒��^�ٓ��ނ�ΏۂƂ��������ɂ��Ă̔�r���������{����B
�����̌ʃe�[�}�ɉ����āA�O���[�v�e�[�}�Ƃ��āA�u�����ȗ��p�v��͍����邽�߂̊�b�����Â�����s���B��̓I�ɂ́A��������Z���^�[�Ȃǂ̋��͂āu���A���̗������������v�ƁA�쓇�n�������Z���^�[�Ƃ̋����Łu�����ʂ̒n�������v�̍쐬�E���\���v�悵�Ă���B
�����̕��@
�d�_�ΏۂƂ��ẮA�����哇�ɂ����ẮA5000����1�̕ČR�B�e�̋ʐ^������ł���n��Ƃ������ƂŁA�쓌���̑�a������ѓ쑤�̐��˓������v�C�ԓ���I�肵�āA�����������s���B����ł́A�k���n����d�_�Ɍ������s���B�������A���Ղ�A�T���S�ʁE���R�E�K�C���p�Ȃǂ��ꂼ��̌����̃e�[�}�ɂ��A�����̒n��ɗאڂ���ꏊ�ł̒����E�������s���B��̓I�ȕ��@�Ƃ��ẮA�ʐ^�Ɏʂ��ꂽ����̊m�F�ƌ��݂̒n�`�E�A���̒��������{����B���R�E�K�C�ɂ��ẮA�j�Ђ���S�̂̑傫��������ł����A����p���Čv���l����T�C�Y�𐄒肷��B���j�I�Ȏ����̈����ɂ��ẮA�����̐��Ƃ̏��������߂Ă��邪�A�߂������Ƀ����o�[�Ƃ��āA����E�����̌Õ�����ǂތo���������҂��}���邱�Ƃ��v�悵�Ă���B�����Ƃ�ɂ������ẮA���k�V�n�����[�h���āA�u�����n��Q�v���y�����A�L���ȓ`���������o���A���̓��e��n���̐l�X�Ƃ����L���Ă������Ƃ��ł���悤�ɁA���Ԃ������A�Ă��˂��Ɏ��{����B
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
����܂ŁA�����o�[�̂��ꂼ��́A�����ʂɂ�������n�������o�����Ă���A���ꂼ��̐��ɂ�����t�B�[���h��������Ȃ��s�����Ƃ��ł���\�͂����Ȃ��Ă���B���k���[�_�[�́A���k�M�q�Lj��ƂƂ���1974�N����p�����Ē����𑱂��Ă���Ƃ��납��A�����ނ˂ǂ̂悤�ȕ����⌤�����ʂ��~�ς���Ă��邩�A�܂��ǂ̂悤�ɂ���ΐl�������邩�ɂ��āA����܂��̂Ƃ��낪�킩��Ƃ�����Ԃɂ��������߁A�ۑ�́A�قȂ镪����������҂̊Ԃɋ���n���ɂ͂ǂ̂悤�ɂ���悢���A�Ƃ������Ƃɍi���Ă����B
����܂ł̉���≂���ɂ����錤���̖��_�́A�����̒����⌤�����s���Ă������A�����̑����Ƃ����_�ł́A�����̉ۑ肪�c����Ă���Ƃ��������ɂ���ƍl������B�������ʂ��悭���ꂽ�`�Ō��\����A�قȂ镪��̓��e�𑍍����āA�n��̖�������n��̐l�X���g�����L���A�s������菕���ƂȂ�Ƃ������Ƃ������A�n���ł͋��߂��Ă�����̂Ȃ̂ł��邪�A���̂悤�Ȏ��v�ɑΉ������Ă����͏��Ȃ��ƌ��킴������Ȃ��B���̂悤�ɁA�n�挤���̃������Ɋւ�����g�݂̕K�v�����A����܂ł̌����̔w�i���Ȃ����̂̒��ł͂����Ƃ��d�p�Ȃ��̂ł���ƁA�l����ꂽ�B 2006�N2���ɎR���ɂ����ď��̍��h�������Ȃ��A���{�v���W�F�N�g���[�_�[����A�{�v���W�F�N�g�̖ڎw���Ƃ�����A����̒����ɂ��Ă̑ł����킹�������Ȃ����B��P�ɂ��������ĕČR�̍쐬����5000����1���x�̐��ׂȋʐ^���番�͂ł��邱�Ƃ̖L�������m�F���A��ȃ����o�[�̂���܂ł̌��������Љ�������B������ӂ܂��A3���ɂ́A���R���������A�A�����J�����������قł̏����W�����{���邱�ƂɂȂ����B���ꌧ�������قƂ̘A�g�v���C�ɂ��A��^�̃X�L���i�[�̎g�p���\�ɂȂ������ƂŁA�v���ɏ���W�ł����B���̏��́A���̔ǂɂƂ��Ă����ɗL�p�Ȃ��̂ƂȂ邱�Ƃ͋^���Ȃ��B 8���ɂ́A���[�_�[�ƈ��k�M�q�Lj��́A�����哇�ɂ����āA3�T�Ԃ̗\���������s���A�̂�1000�L�����[�g�������āA�قڑS�W����K�₵���B���̌�A���̏������ӂ܂���1�T�Ԃ̍��h�����������Ȃ����B���R�Ȋw�ۓI���͋C�̒��ł̃t�B�[���h���[�N�Ƃ��āA�Â��ʐ^��p�����������⌻�n�����ȂǁA����A�ʂɖK�ꂽ�ꍇ���A�g�����}������Ă���������悤�Ɍ��n�̏Z���⌤���҂Ƃ̐l�ԊW����Ă邱�Ƃ���̖ړI�Ƃ������������ł������B 12�����ɂ́A5�����x�ʼn���k���ł̍��h������\�肵�Ă���A���N�x�ȍ~�̖{�������X���[�X�ɍs���邽�߂̏����Ƃ��Ă̖{�N�x�̗\���I�����́A����������Ċ������A�c���ꂽ���ԂŎ��W���������̋��L�ƕ��͂ȂǁA���N�x�ȍ~�̖{�i�I�����̏���������\��ł���B
�� �X�y�V����
-
�}���n�i�o�`�� |
�͔|�A���� |
������ |
�ۑS��
�͔|�A����
���[�_�[�F �R���T�� �i���{����w�������Ȋw�����ȁA�����A�����l���w�j
�L�[���[�h�F�@���R�����A�G���A�}���A�H�p�A���A�G��
�����ړI�ƃv���W�F�N�g�I���܂łɊ��҂ł��鐬��
�X�͂���k�Ɉړ������4�I�̏I���ɁA�l�ނ͑傫�����R���h������悤�ɂȂ�B���̊h���Ɉˑ����Đ���n���l�����A�̐��𑝂₵���A���Q���q�g���p���I�ɗ��p����悤�ɂȂ�ƁA�͔|�A����G����ƒ{�Ƃ�������Ȑ������i�����Ă���B���R�̐��Y���ɐH���ˑ����������Ƃ��Ă̐�������q�g���������A�͔|�A����ƒ{�ւ̐H�̈ڍs�ɔ����āA�l�Ԃ͕����╶������ɓ���邱�ƂɂȂ�B�A�������̌p���I���p�ɔ����A�V�����͔|�A���́A���ǂ��łł��������Ă���B�͔|�A����h���ˑ����A���́A���Y�n����̓`�d�Ƃ����V�i���I�ɉ���Ȃ��Ƃ��l�Ԃ̎���ɑ��݂ł���B
�H�����łȂ��A�߂�Z�̗v�f�ɂ��݂���悤�ɁA���R�Ƃ̒��ړI�W����q�g�̐������������Ă䂭���ԓI�v���Z�X�́A���{�łǂ̂悤�ɐi�̂ł��낤���H�͔|�A����G���͂��̃v���Z�X�̂Ȃ��Ői�����������A���ł��邩��A�������́A�l�Ԃ̍s�ׂɈˑ����Đi���������ʂ��͔|�A����G���Ɍ`�ԓI���邢��DNA�ψق̂������ō��ݍ��܂�Ă���ƍl���Ă���B���̂悤�Ȋϓ_����A�{�����ł́A�Ƃ��ɐA���������p�̊J�n���E�����̎��ԂƐ��ԓI�Ӌ`�A���p�p���ɂƂ��Ȃ��h�����ł̐A���̐U�镑���̍Č���_�l����B
�����̓��e�ƕ��@
�͔|�A���Ƃ��̋߉��쐶��̑��l������ѐl�Ԋh���n�ɐ��炷��G���̑��l������`�q���x������ь`�ԓI���x���ŕ��͂���B���A�W�A���Y�̎G���i�q�G�A�\�o�j�A�H�p�}���i�_�C�Y�A�A�Y�L�j�A���́i�������j�A���i���T�r�A���^�f�j�A�G���i�I�I�o�R�j�Ƃ��̖쐶������f���I�f�ނƂ��đI�сA�t�B�[���h�����ɂ���ė��p�Ǝ��R���z�̎��Ԃ�Ԃ𖾂炩�Ƃ������͍ޗ��i�����o���Ȃ��A����DNA���ӂ��ށj�����W���A����z�͂ɂ���čČ����̍������q����̌n�I�ɏW�߁A�`�ԓI�����̕��͂��܂߂Ĉ�Ղ�蔭�@�����A����̂̊Ӓ蓯������J�����Ȃ���A�i�������w�I��͂����݂�B
�t�B�[���h�����̑Ώےn�́A���{�S�y���܂݁A�����̏Ɨt���ёт��r�ΏƂƂ���B
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
���{�ł͌Â���Ղ���h���O���ނ̂ق��Y�������q�G���A���ƃA�Y�L�ނ̎�q�����@����Ă���B�C�l�A�_�C�Y�A�I�I���M�A�R���M�Ȃǂ̍����́A�N��I�ɂ�����x�ꂽ��Ղ�蔭�@����Ă���A��삪�W�J����O�Ɏ��R�����̗��p�ƌ����I�_�Ƃ��c�܂�Ă����`�Ղ�����B�����̒Y����q�͂���܂ŃC���h���Y�͔̍|�q�G����N�g�E�ƈ����Ă������A����`�w�I�����ɂ���āA���A�W�A�͔̍|�q�G�͖쐶�i�G���j�̃C�k�r�G���c��ŃC���h�̃q�G���Ƃ͗މ��̂Ȃ����ƁA�A�Y�L�̖쐶�c���̓��u�c���A�Y�L�Ń����N�g�E�Ƃ͉����������ƁA�_�C�Y�̖쐶�c���̓c���}���ł��邱�ƁA�C�l�̖쐶�c���E�쐶�C�l�͒����܂��͓�A�W�A�ɕ��z���邱�ƁA�I�I���M�ƃR���M�͒n���C�����Ő����������ƂȂǂ����炩�ɂ���Ă���A�q�G�A�A�Y�L�A�_�C�Y�͓��A�W�A���Y�ł���B
�Y����q�̔����Ȍ`�Ԃ��݂�ƁA�q�G���A���͖��炩��6�{�̂̃C�k�r�G���͔|��i�j�z���r�G�j�ł���A�A�Y�L�ނ́A�͔|�A�Y�L�����u�c���A�Y�L�ł���A�����N�g�E�Ƃ͖��炩�ɈႤ�B�����̃q�G��A�Y�L�q�n���w�I�ɉ�͂���ƁA�`�ԓI�ɂ悭�����߉��͔̍|���쐶��Ƃ͖��ĂȈႢ�������B��ɌŗL�̑}�������ψق�u���̓������g���ƁA���@��q�̎�ƌ��݂͔̍|�킪�������Ƃ͔���ł���B�������A�͔|��Ɩ쐶�c���Ƃ͍��̂Ƃ��뎯�ʂł����A���@������q�����͔|��ɂȂ����̂��͕s���ł���B
���̂悤�Ȏ���܂��āA�������͕��ތQ���g�����邩�����ŗ��p�`�Ԃ̈Ⴄ��ɂ����Đl�ԁ|���R�W�̗��j���ǂ̂悤�ȑ��l�������������炷�̂�������̂ɕK�v�Ȋ�Տ���~�ς��邱�Ƃɂ����B
�{�N�x�́A�t�Α̈�`�q�̐i���Ɗj��`�q�̐i���𑊌݂ɔ�r���邽�߂̊�ՓI������i�߂��B�q�G�A�A�Y�L�A�_�C�Y�ł́A���͍ޗ��̎��W�Ƃ��ɗt�Α�DNA���̒~�ς�����ɂ����߁A�j��`�q�Ɋւ�����̒~�ς��J�n���A�������i�I�j�����A�R�I�j�����j�A���T�r�A���i�M�^�f����уI�I�o�R�ɂ��Ă͖��_�̏��݂@����t�B�[���h�����ƂƂ���DNA�ψقɊւ��鏉���I�]���������߂��B
�q�G�ł͑��̕��q�n���������������邽�߂ɕK�v�ȍޗ����t�B�[���h�����ƕ����Ď��W�����B���N����̒����ɂ����Ė����n���ƕs�����n������N���I�n�r�^�b�g�Ƒ��N���I�n�r�^�b�g���Z�����Ă��邱�ƁA�������ւ̓K����͔|���ɔ����Ă݂��鑁�������������ƂȂ��N���Ƒ��N���Ƃ̒��ԓI�n���������B
�A�Y�L�ł́A�j��`�q�̑�\�Ƃ��ăA�~���[�[�Ȃ�4��̈�`�q�̔�R�[�h�̈���߉��쐶��ƂƂ��ɕ��͂������ʁA���l���̗��j������`�q���ƂɈႤ���Ƃ��m�F�����B
�_�C�Y���ł�Soja������Glycine�����ɂ��ėt�Α�DNA��4�̈�`�q�ԗ̈�̉���z����r�����BSoja������Glycine�����͂��ꂼ��قȂ�N���[�h���`�����A�O�҂͌���ꂽ����z�^�����������A��҂͑��l�Ȏ핪�����������^���������B�A�W�A�e�n����̃_�C�Y�ƃc���}����9��`�q�ԗ̈�3849������r����ƁA�t�Α̃Q�m����I+II�^��III�^��2�Q�ɕ������A���҂ɂ�5�̉���u�����ώ@����A�_�C�Y�ƃc���}��124�n���ɂ͗��҂̒��Ԍ^�͊ώ@����Ȃ������BI�^�AII�^�AIII�^�ɂ́A�n���I���z�̈Ⴂ���݂��AIII�^�̓c���}���̕��z��S�̂ɘj�邪�AI�^��II�^�͓��{�̓암�A�؍�����ђ����쓌���ɂ����Ȃ������B����͈قȂ����W�c�̊g���Ək���̉ߒ����o�����ʂƍl������B�_�C�Y�ɂ�I�^���D�肷�邪�AI�^�́A���{�ł͎l���A��B����юR�A�n���̋ɏ����̌n���ɂ����݂��Ȃ������B
�I�j�����ƃR�I�j�����ł́A����B����ђ��N�����̎����W�c�ł̕��z�������s���A�t�Α�DNA���^������ׂ��B���{�̃I�j�����͂قƂ��3�{�̂ŕ�n���ӂɐ��炵�A2�{�̂͑Δn�ɋǍ݂������A���N�����ł�2�{�̂��L�����z���A3�{�͉̂��|�I�Ɏg���Ă�����̂̕�n�ɂ͐��炵�Ă��Ȃ������B�R�I�j�����͂��ׂ�2�{�̂œ��{�ł͊C�݂Ɏ������Ă����B�͔|�̃������̓R�I�j�����݂̂ł������B�t�Α̂ɂ͑��^������A���̕��z�͌Òf�w��C���ŕ��f����Ă���X���ɂ������B�����Ɨt���ёт̌n���ɂ͑傫�ȑ}�������ψق��݂�ꂽ���A����u���ɂ����Ă͓��{�̌n���Ɨގ����Ă����B
���T�r�ł́A���{�Ǝ��̍��h��Ƃ��ĐH�������`�������w�i�̉�͂܂��āA�����n�ƍ͔|�̖����������s�����B�����{�𒆐S�ɑS��50�n�_�ȏ�����A���T�r20�n���Ɠ��{�ŗL�̋߉��쐶�탆�����T�r14�n���̗t�܂��͊������W�����B���R���Ɠ������͏����Ȏ������T�r�Ɛ��肳���3�W�c���m�F�ł������A�����ł͎������T�r�͍͔|���T�r�Ƌ�ʂ���A�͔|��Ƃ̌��G�ɂ��I����킪���ԂŐi�߂��Ă����B
���i�M�^�f�ł͍͔|���p�̑��l���ƍ͔|�̐����ߒ�����͂��邽�߂Ɉ��m���O�͘p�̒������鍲�v���Ŗ����A���w�I�����������߂��B�����w�I�ɂ̓��i�M�^�f�ɂ�����'��������'��'��������'��2��ނ�����A�����ł�'��������'�����ŏ`'�Ƃ��邽�߂ɔ��͔|���Ă����B���͔|��'��������'�͎����p�̔��ł��ڂ�킩��萶���ɂ���Ĉێ�����Ă������A���c�e�ȂǂɎ������郄�i�M�^�f�ł���'��������'�́A���Ă͍̎悵�ē��l�ɐH�ׂĂ������A���݂͗��p����Ă��Ȃ������B �I�I�o�R�ł́A��Ӑ}�I�Ȑl�h���������N�����Ă��鐶��n�N����ΐ쌧���R�Œ��������B���R�̈����R�шȏ�ɂ͖{�������t�L��I�I�o�R���ߔN�������Ă���B���R�̌ŗL��n�N�T���I�I�o�R�ł̃I�I�o�R�̐N���̈Ӗ���m�邽�߂ɗ��ҎG������A��`�q�Z���̎��Ԃׂ邽�߂ɁArDNA��ITS�̈���r�����Ƃ���A����ɂ͖��炩�ȈႢ���݂�ꂽ�B
�}���n�i�o�`�̎��R�j�ƐA���E�y�n���p�̗��j
���[�_�[�F �{��@�� �i���쌧���ۑS�������A�������Ԋw�E�ۑS�����w�j
�L�[���[�h�F�@�����A�n���n���AGIS�A�i�ρA�y�n���p
�����ړI�Ɠ��e
�ŏI�X���ȍ~�̋C��ϓ��Ɛl�Ԃ̓y�n���p�̕ϑJ�ɂƂ��Ȃ��A���{�ł��X�сE�����Ȃǂ̓y�n�핢�̕��z���ω����A�܂��������Ă����������ɐ���E��������A���E���������̕��z�₱���̐������S�����Ԍn�@�\�̂�������ω����Ă����ƍl������B���Ƃ��}���n�i�o�`�̂������̎�ł͒���Ƃ������̕��ʂ������L�����Ă���A���̍������z���ł��Ȃ������̐[���Ԃ������ɖK���K���������A���̂��Ƃɂ���Ă����̐A���ɂƂ��Č������Ȃ������҂Ƃ��Ă̋@�\���ʂ����Ă���ƍl�����Ă���B�������ߔN�ł́A����O�������Ɏw�肳�ꂽ�Z�C���E�I�I�}���n�i�o�`�̖쐶���ȂǁA���������W�ɑ���V���ȋ��Ђ��o�ꂵ�Ă���B
�{�����ł́A���{�̕��L�����ɓK�����U���A�����̐A���̏d�v�ȑ����҂Ƃ��ċ@�\���Ă���ƍl������}���n�i�o�`�e��ɂ��āA�i1�j���̒n���I�ȕ����̉ߒ��q�n���w�I�ȕ��͎�@�ʼn𖾂��A�i2�j���z�ƐA���E�y�n���p�Ƃ̂ނ��т����i�ϐ��Ԋw�I��@�ł����炩�ɂ���ƂƂ��ɁA�i3�j�K�Ԃ���A���Ƃ̑��݈ˑ��W���ǂ̂悤�Ȓn������݂����Ă���̂��Ԃ���ь`�Ԃ̔�r����𖾂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
����ɂ��A�i1�j�n���i���A�i2�j�i�ρE�y�n���p�A�i3�j��ԑ��ݍ�p��3�̎��ԓI�E��ԓI�X�P�[�����l�����������ۑS�ւ̃A�v���[�`�̂��������̗�Ƃ��Ď����ƂƂ��ɁA���̃X�e�b�v�Ƃ��ċC��ϓ���y�n���p�̕ω��A�O�������i�A���E�Z�C���E�I�I�}���n�i�o�`�j�̐N���Ȃǂ��ݗ��̃}���n�i�o�`-�A�������n�ɂǂ̂悤�ȕω��������炷����\�����A��̎w�j�ɖ𗧂Ă邽�߂̕��@�����f���I�Ɏ����i�K�ɓ��B���邱�Ƃ����҂����B
�����̕��@
�}���n�i�o�`�̓��[���V�A�嗤�̑����n�тɕ��z�̒��S�������A��l�I�̊���Ȏ���Ȃǂɓ��{�Ɉړ������ƍl�����A�{�B�����̎R�x��Ɩk�C���ɑ����̎킪��������ق��A���z��̋�����̂����̂������͓��k�n���ł��L�^����Ă���B�܂��k�C���Ɩ{�B�̂������ł������̎�Ɉ��탌�x���̕������݂���B�����R�x��̓t�H�b�T�}�O�i�n��̉ΎR�n�т��܂݁A�܂��×��̔n�̕��q�Ȃǂɂ��A�e�n�ɔ����R�������ێ�����Ă����B���̂悤�Ȓn��������A���z��̋����}���n�i�o�`�̎�Ƀ��t���W�A����Ă����\��������i���̂悤�Ȋ��́A��ł̂�����̂���`���E�ނ̑����̐����n�Ƃ��Ȃ��Ă���j�B
�����ł��̃v���W�F�N�g�ł́A���쌧�i���ɒ���s���Ӂj���d�_�Ώےn��Ƃ��A�}���n�i�o�`�̐����n�i�n�`�}���x���̓_���j�◘�p����A���Ɋւ�������̏�������ƂƂ��ɁA���n�����ł���������Ȃ��A�}���n�i�o�`�e��̕��z�Ɛ������Ɋւ���f�[�^�x�[�X���쐬����B�����Ă����̏����A���y���l����A���}�Ȃǂ�GIS��ŏd�ˍ��킹�A���ϗʃ��W�X�e�B�b�N��A���͂Ȃǂɂ��A�}���n�i�o�`�e��̐����n�̏������𖾂���B�܂����̂悤�ȕ��z��������炵�Ă������j�I�����������̎�����{�v���W�F�N�g�̑��̔ǂ̐��ʂȂǂɂ��ƂÂ��čl�@����B����ɂ����̏��A�y�n���p�ω��A�C��ϓ��A�O����̐N���ȂǂƊ֘A�Â����}���n�i�o�`�̐����\�n��̕ϓ��̗\����@�ɂ��Č�������B
���̏d�_�Ώےn��ł̒����f�[�^�ƕ��͌��ʂ���b�Ƃ��āA��r�̂��߂̒����n���ݒ肵�A�W�{�̃T���v�����O�ƕ��q�n�����͂������Ȃ��B�܂����ꂼ��̒n��̌��n�����ƕW�{�̑���Ȃǂɂ��ƂÂ��āA�}���n�i�o�`�ƐA���̐��ԓI�E�`�ԓI�ȑ��ݓK���₻�̒n�敪���A����т���ɂ������l�ׂ̉e���̎��Ԃ��𖾂���B
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
1996�N�ȗ�����܂łɁA�c���ɂ��}���n�i�o�`�̌n���n���w�I������{���ɂ�钷�쌧�Ń��b�h�f�[�^�u�b�N�̍쐬�Ȃǂ̂��߁A���쌧����10���3��̂̃}���n�i�o�`�̕��z���i��ɒn�`�}���x���̓_���j�ƖK�Ԃ����A���̎�ނɂ��Ă̏�����Ă���B���̂��������ȏ�́A2004�N�ȍ~�ɖ{�v���W�F�N�g�̌��n�����Ŏ擾�������̂ŁA���q�n�����͗p�̃T���v���̊m�ۂ�����Ɠ����ɂ����Ȃ��Ă���B���ɒ���s�ߍx�̗��R�ɂ��Ă͏d�_�I�Ɍ��n�����E�T���v�����O�������Ȃ��Ă���i���̒n��̗��R�̗��j�I�ω��Ɋւ��ẮA���쌧���ۑS�������ɂ��w�ۓI�����̒m��������j�B���쌧�Ń��b�h�f�[�^�u�b�N�ł́A�z���V���E�n�C�C���}���n�i�o�`���Ŋ뜜II�ށA���̃}���n�i�o�`3����i�����ɂ��Đ�������肪���肪�s�����Ă��邽�߁j���s����Ƃ��Ă���B
���N�x�́A2005�N�܂łɃ}���n�i�o�`���m�F����274��3�����b�V�����̃f�[�^�ɂ��ƂÂ��A���̓y�n�핢���ނ���}���n�i�o�`�e��̑��ۂ�\�����邽�߂̗\���I�ȕ��͂����݂��B�����ēy�n�핢��ϐ��Ƃ���ȒP�ȑ��d���W�X�e�B�b�N��A����A�z���V���E�n�C�C���}���n�i�o�`�ő����i������p < 0.1�����j�A�i�K�}���n�i�o�`��q���}���n�i�o�`�ō��R�A���∟���R�A���Ȃǂ������n�Ƃ��čD�K�ȌX�����������ʂ�����ꂽ�B�����ł��������Ƃ́A�X�X�L�����┰�̐Ւn�A�q���n�Ȃǐl�ׂ̉e���ňێ�����锼���R������l�H�����ł���A���������l�Ԋ�������Ŋ뜜��ł���z���V���E�n�C�C���}���n�i�o�`�̐��������ێ����Ă��邱�Ƃ��������ꂽ�B���̂悤�Ȋ��́A���̃n�i�o�`�ނ��ӂ��߂��푽�l�x�̖ʂł����̃^�C�v�̐A���������l�����������Ƃ���������Ă���i�{�� 2005�j�B
�}���n�i�o�`�̌n���n���w�I���͂ɂ��ẮA���A�W�A�Y�}���n�i�o�`�̈����E��E����̒n�惌�x���ł̕��͂������Ȃ��Ă���i�c�� 2001�j�B����ɂ��ƁA���{�ɐ�������}���n�i�o�`�́A��O�I�I�������l�I�ɂ����Ă̂��܂��܂Ȏ����ɑ嗤����ړ����A�핪�����Ƃ����\���������B
�}���n�i�o�`�Ƃ��̖K�ԐA���̌`�ԓI�ȑ��ݓK���ɂ��ẮAUshimaru & Nakata�i2001�j���g�L�\�E�ƃc���n�i�o�`�̑����n��ΏۂɉԊ��T�C�Y�̐i���ɂ��ĕ��͂������Ȃ������ʂ�����A���̎�@��{�v���W�F�N�g�ɂ����Ă����p���邱�Ƃ��\�ƍl���Ă���B�܂�����܂ł̕����f�[�^����}���n�i�o�`�e�킪���p����A���ɍ������邩�ǂ�����������\��ł���B
�Ȃ��A�ݗ��̃}���n�i�o�`�ƐA���̋����W�ɋ��Ђ������炵�Ă���O����Z�C���E�I�I�}���n�i�o�`�́A�k�C���ŋ}���ɕ��z����L���Ă���B���쌧�ł���O�ł̔����Ⴊ���邪�A�쐶���͊m�F����Ă��Ȃ��B����A�ݗ��̃}���n�i�o�`�̑������R���t���[�⃀���T�L�c���N�T�Ȃǂ̊O���A�������Ƃ����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�{�v���W�F�N�g�̂���܂ł̒����f�[�^���玦����Ă���B
�����ǁ`�A���̒n�於�̂Ɨ��p�@
���[�_�[�F ����@���� �i�x�R��w�l���w���A�Љ��w�j
�L�[���[�h�F�@�A�������@�����p�V�X�e���@�H�̉����@�A�������n�}
�����ړI�Ɠ��e
�i�ړI�j
��ʂ̃g���[�T�[�Ƃ��āu�A���̒n�����Ƃ̌Ăі��Ɨ��p�@�v
�A�������́A�A�����̔F���𖾂炩�ɂ���肪�����^����ƂƂ��ɁA�n��Љ�ɂ����鐶�Ƃ�����⎑���̌n�Ƃ��̔F���������Ă���B
�{�����ł́A���{�e�n�ɂ�����A���̖��̂����ƂɁA���{�ɂ�����A���ρA���E�ςƂ����ɐ[���ނ��т��Ă��邩�������A�A����b�����Ƃɂ������{�l�̊��F���̗��j�Ȃ�тɊ����p�̗��j��������ƍl���Ă���B
�i�v���W�F�N�g�I���܂łɊ��҂ł��鐬�ʁj
�P�A���{�C���ݒn��ɂ�����͔|�A���Ȃ�тɍ̏W�A���𒆐S�ɂ����A�H�Ǝ����̑̌n�Ƃ��̗��p�Ɋւ�������B
�Q�A���{�S��������ɂ��ꂽ�u�A�������n�}�W�v�̊��s
�����̕��@
���{�S���̋��y�H���痿������H�ނ����Ƃɒn�悲�Ƃ̊����p�V�X�e����B
�u���{�̐H�����v�i�_�����j�����Ƃɍ쐬�����f�[�^�x�[�X���痿�����E�H�ޖ��E�G�߁E�n���ƃP�ɒ��ڂ��ăf�[�^�x�[�X���쐬���A���o������C�ӂ̂Q��̃p�^�[���̕p�x�Əd�݂Â��𗘗p���A���o������B
���o���ɂ͋��o���p�^�[���̏d�v�x���v�Z���A�d�v�ȋ��o���p�^�[�����珇�Ƀl�b�g���[�N�ŕ\������B
����܂ł̔w�i�ƍ��N�x�܂łɖ��炩�ɂȂ�������
�R�`���̓������E�A�x�R���v�g����A���Ɍ��A�n�C�݂Ȃǂ̓��{�C���ݒn��ŁA�n���̐H�Ɋւ�����������A�H�̒n��������m�F�ł����B